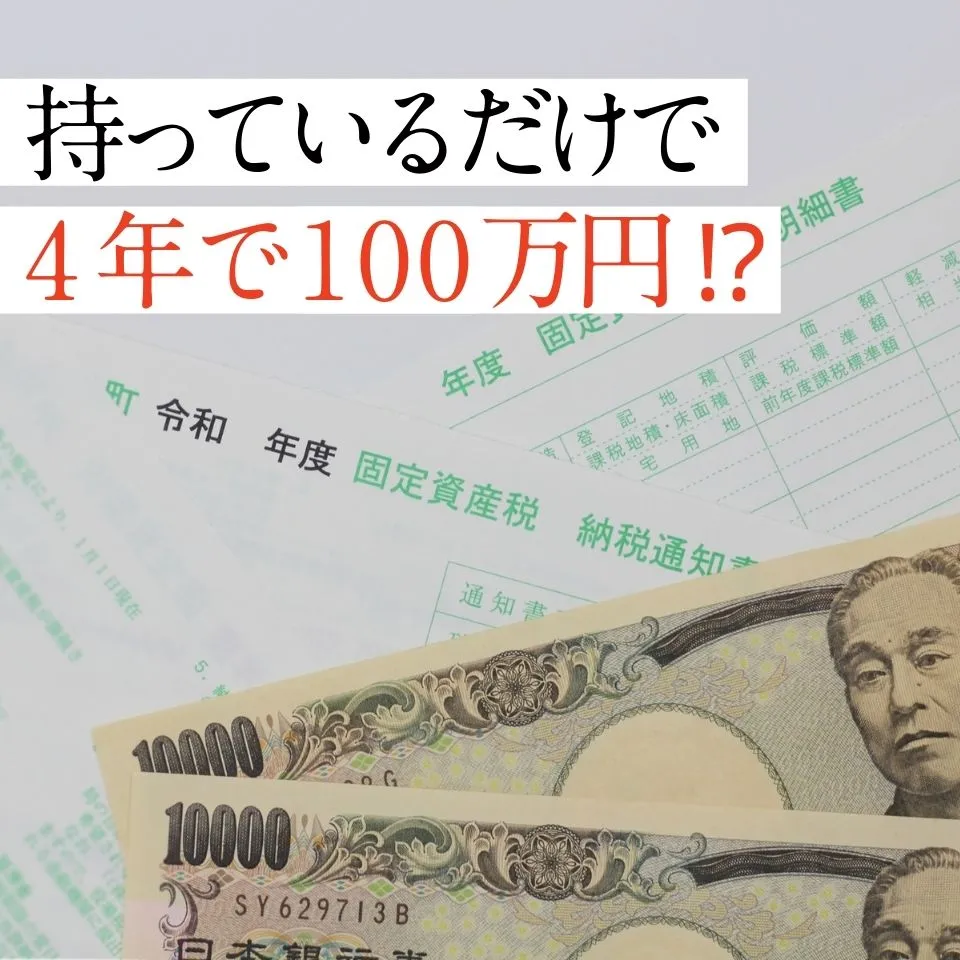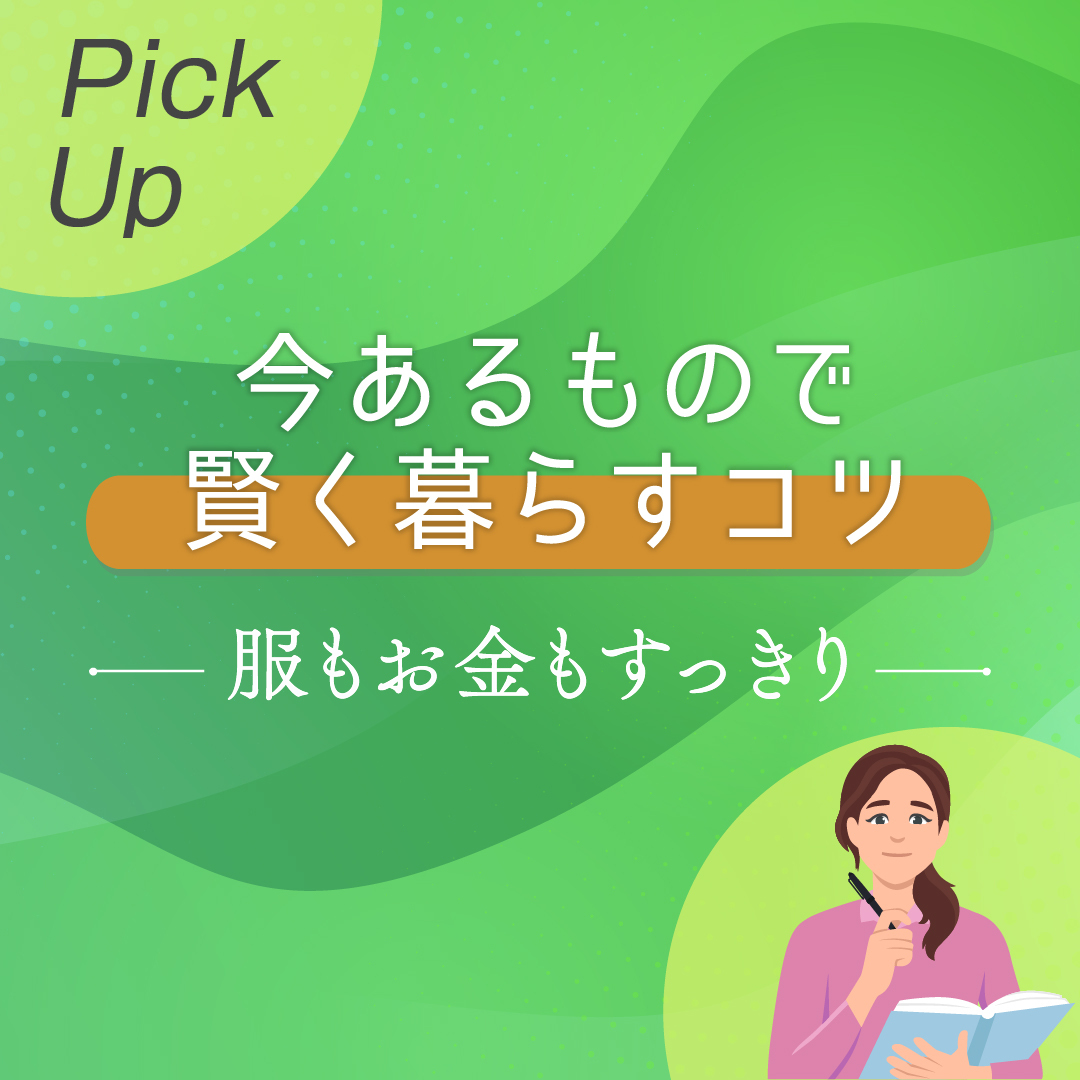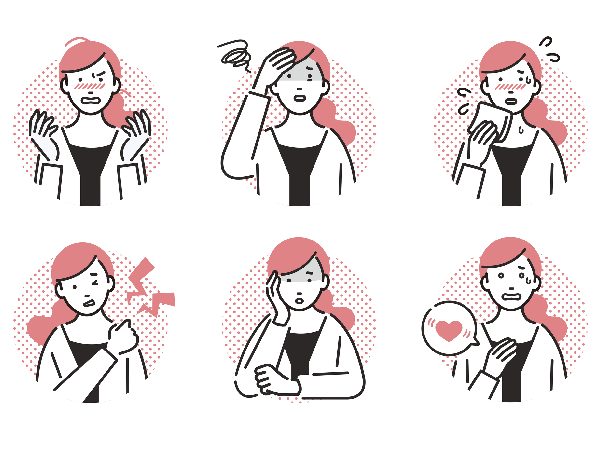食事・運動・睡眠の見直しで更年期を明るく乗り切る!
【医師監修】更年期障害の対策・セルフケア方法と付き合い方のコツ
【医師監修】更年期障害の対策・セルフケア方法と付き合い方のコツ
更新日:2025年08月09日
公開日:2022年10月18日

監修者プロフィール:横倉恒雄さん(横倉クリニック)

よこくら・つねお 医学博士。医師。横倉クリニック・健康外来サロン(港区芝)院長。東京都済生会中央病院に日本初の「健康外来」を開設。故・日野原重明先生に師事。婦人科、心療内科、内科などが専門。病名がないものの不調を訴える患者さんにも常に寄り添った診療を心がけている。著書『病気が治る脳の健康法』『脳疲労に克つ』他。日本産婦人科学会認定医 /日本医師会健康スポーツ医/日本女性医学学会 /更年期と加齢のヘルスケア学会ほか。
更年期障害、具体的にはどんな症状?
更年期とは、一般的に閉経を迎える45〜55歳くらいの10年間を指し、この時期には女性ホルモンが急激に減少することで、心身にさまざまな不調が現れます。
この不調を「更年期症状」といい、更年期症状が重く、仕事や家事など日常生活に支障が出るほどの状態のことを「更年期障害」といいます。
ホットフラッシュ(ほてり、のぼせ)、発汗など「血管の拡張や放熱に関する症状」、動悸やめまい、疲れやすさ、肩こり、関節痛、腰・背中の痛み、肩こり、息苦しさ、胸がしめつけられる感じなどの「身体症状」、イライラや気分の落ち込み、不眠といった「精神症状」などが、更年期に見られる主な症状です。
更年期障害になったらどうすればいい?
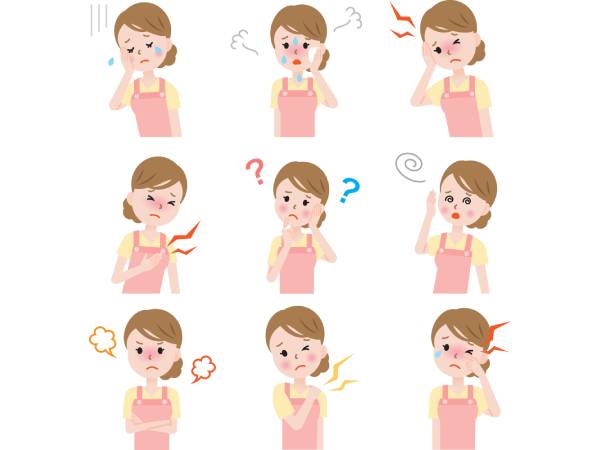
更年期障害は、女性であれば誰でもなる可能性があります。
「最近調子が悪い……もしかして更年期障害?」そう思ったら、セルフチェックや検査をし、自分の症状に合わせたケアを行っていきましょう。
病院で検査を受ける
更年期障害は簡単なセルフチェックも可能です。気になる症状を感じている場合は、まずはセルフチェックをしてみるといいでしょう。
病院での更年期障害の検査は「問診」と「血液検査による女性ホルモン検査」が主です。その他、「内診」「超音波検査」や「細胞診(子宮体がん、子宮頸がん検査)」「触診・超音波検査・マンモグラフィ(乳がん検査)」「骨量測定」なども、必要に応じて行います。
更年期は、これまで女性の体を守ってくれていたエストロゲンが減少することで、さまざまな病気にかかりやすくなる時期です。
バセドウ病など甲状腺の病気や高血圧、心臓病、耳鼻科系の病気、メニエール病、脳の病気、子宮体がんなどの病気が隠れているかもしれないため「更年期のせい」と決めつけず、定期的な検査を受けるといいでしょう。
セルフケアで対策
更年期の症状が軽い場合は、セルフケアによって症状が改善することもあります。
更年期を軽くする方法、楽にする方法は「食事・運動・睡眠」が基本なので、これらを意識したセルフケアを行っていくといいでしょう。詳しい方法については後述します。
病院でのケア・治療
セルフケアでは症状が改善しない場合や、更年期の症状が重く生活の質の低下が見られる場合などは、我慢せず早めに病院で治療を受けることが大切です。
- ホルモン補充療法(HRT)
- 漢方治療
- 向精神薬
- プラセンタ など
病院では、上記のような治療法から一人ひとりの症状や体質に合った治療を行います。
更年期の症状対策・セルフケアの方法
更年期の症状対策・セルフケアは「食事・運動・睡眠」が基本です。
病院で治療を受ける場合も、食事・運動・睡眠を改善していくことで症状の緩和や悪化の予防につながるでしょう。
- 食事でセルフケア
- 運動でセルフケア
- 睡眠でセルフケア
- その他のケア
- 漢方薬を使う
ここからは、それぞれの方法を詳しくご紹介します。
更年期障害対策1:食事でセルフケア

まずは、食事による更年期障害対策を見ていきましょう。
食生活の見直し
食生活の見直しは、更年期障害の予防にも有効です。「◯◯さえ食べていればいい」という食べ物は存在しないため、食事は栄養バランスよく摂取することを心掛けましょう。
厚生労働省が公表する「食事バランスガイド」は一般的な健康な人を対象としたものですが、更年期女性の食事指導にも使われているため、これを参考にして一日のメニューを見直すのもおすすめです。
また、食事を抜くと栄養バランスが崩れやすくなるため、毎日なるべく同じ時間に3食規則正しく食事を取ることを基本とするといいでしょう。
積極的に取りたい食材・栄養素
更年期女性が積極的に取りたいのが、大豆イソフラボンを含む大豆製品です。大豆イソフラボンは、女性ホルモンと似た働きをする成分として注目されており、納豆や厚揚げ、きなこ、豆腐、おからなどを積極的に摂取するのがおすすめです。
水を豆乳に変える、肉ではなく厚揚げや豆腐を使う、薄力粉の代わりにおからを使うなど、調理に工夫をして積極的に取り入れるといいでしょう。
また、ホルモンバランスを調整する働きなどを持つビタミンEも積極的に摂取しましょう。ビタミンEはかぼちゃ、アボカド、たらこ、アーモンド、抹茶などに豊富に含まれています。
ビタミンEは脂溶性なので、油と一緒に調理するといいでしょう。ビタミンCやビタミンAと一緒に摂取すると、さらに効果的です。
加えて、骨密度が低下しやすくなる更年期以降は、骨粗鬆症予防のためにカルシウムも積極的に取りましょう。
更年期におすすめのお茶
漢方では体の中を巡っている「気(き)」・「血(けつ)」・「水(すい)」のバランスが崩れると心身に不調が現れると考えられています。
気の流れをすっきりさせてくれるのが「ミントティー」です。のぼせや多汗などのホットフラッシュ、イライラへの効果が期待できます。
その他にも、女性にうれしい鉄分や葉酸を多く含むなつめやクコの実の薬膳茶、シナモンチャイ、スギナのお茶もおすすめ。更年期太りの対策には、ガレート型カテキンが含まれるお茶もおすすめです。
更年期障害対策2:運動でセルフケア

続いて、運動による更年期障害対策を見ていきましょう。
有酸素運動・筋トレ・ストレッチ
更年期は、筋力が大きく低下し始める時期でもあります。更年期に運動を習慣化することは将来の寝たきり予防にもつながるため、積極的に行っていきましょう。
以前から親しんでいるスポーツがあれば、それを続けるのがおすすめ。運動習慣がない人は、無理なく楽しみながら続けていける運動を行うといいでしょう。
おすすめなのがウォーキング、サイクリング、ランニング、ジョギング、水泳、ダンスなどの有酸素運動です。
体力の維持・向上、肥満防止にもなり、生活習慣病の予防効果も期待できるなどメリットがたくさんあります。有酸素運動と合わせて、ストレッチや筋トレを行うと、さらに効果的です。
運動の頻度・時間の目安
更年期女性のための運動メニューとしては、例えば以下のようなものがあります。
- ストレッチ……5分
- 有酸素運動……20〜40分
- 筋トレ……5〜10分
- クーリングダウン(ストレッチや軽い歩行、マッサージなど)……5分
運動習慣のない人は少ない時間から開始して、徐々に継続時間を増やしていきましょう。頻度は1週間に3〜4回を目標に、無理をせず体調に合わせて続けていきます。
運動をするタイミングは、食事をしてから2時間後がおすすめです。早朝の空腹時や食後すぐ、入浴後、飲酒後は避けましょう。
更年期障害対策3:睡眠でセルフケア

メンタルを安定させるためには、質のいい睡眠をとることが大切です。
規則正しい生活で生活リズムを整える、目覚めたら朝日を浴びる、夜は寝る前に明るい光を浴びないなどの対策を行いましょう。
また、憂うつな気分のときやイライラしてしまうとき、不安感のあるときは「寝る前によかったことを3つ書く」という方法もおすすめです。
「ランチがおいしかった」「スーパーですごくおいしそうな野菜が買えた」「庭の花がきれいに咲いた」などほんの小さなことでいいので、その日のよかったことを書くと、不安やイライラよりもポジティブな情報をキャッチしやすくなります。
更年期障害対策4:その他のケア

その他のケア方法もご紹介します。必要に応じて、食事・運動・睡眠の対策と合わせて行ってみましょう。
サプリメント
サプリメントにはさまざまな種類があり、更年期症状の緩和効果が期待されているものもいくつかあります。中でも注目されているのが、エクオールです。
エクオールは、ダイゼインという大豆イソフラボンに含まれる成分が腸内細菌によって代謝されてできる物質で、効果的な人とそうでない人がいますが、ホットフラッシュや肩こりなどの更年期症状を改善する効果が期待されています。
ただし、すべての人が腸内でエクオールを作れるわけではありません。日本人の場合は、エクオールを生み出せる人は5割程度だといわれています。
エクオールはサプリメントで摂取できるので、サプリメントを使って対策してみるのもいいでしょう。
アロマセラピー(アロマテラピー)
アロマセラピー(アロマテラピー)とは、植物から抽出した香り成分「精油(エッセンシャルオイル)」を使って、健康や美容に役立てていく自然療法のことです。良い香りが楽しめ、リラックス効果が期待できます。
クラリセージにはエストロゲン様作用があり、ホルモンバランスや更年期の症状、生理不順、月経前症候群(PMS)などへの効果が期待されています。
精油を使ったマッサージをする、下腹部へ塗布する、アロマバスに用いる、ティッシュペーパーなどに垂らして寝る前に香りを嗅ぐなど、さまざまな取り入れ方が可能です。
対症療法
更年期に見られる症状は多種多様で、日によって症状が変わったり、いくつもの症状が重なって起こることもあります。
冷えの症状がある場合は入浴や手袋などで手足を温める、頭痛がある場合は頭痛薬や鎮痛剤を服用するなど、現れている症状に対する対症療法も合わせて行うといいでしょう。
更年期障害対策5:漢方薬を使う
漢方薬は日本産婦人科学会も推奨する更年期障害の薬物治療のひとつです。漢方薬の一部は市販されており、セルフケアに活用することも可能です。
自然成分がやさしく働く漢方薬は、更年期の肉体的症状や精神的症状に同時にアプローチし、こころと体全体のバランスの乱れを改善します。そのため、いくつものお悩み症状を解決すると同時に、根本的な体質改善も目指すことができるのです。
ここでは、更年期の症状別におすすめの漢方薬を3つご紹介いたします。
・加味逍遙散(かみしょうようさん)
漢方薬の三大婦人薬のひとつ。他の2つ(桂枝茯苓丸、当帰芍薬散)も更年期の症状に用いられますが、加味逍遙散は血流やホルモンバランスを整えるだけでなく、不眠やイライラ、めまい、ホットフラッシュなど更年期にみられる、いわゆる不定愁訴によく用いられます。
・抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)
更年期や月経にまつわるイライラや怒りっぽさ、寝付きの悪さなどの症状によく用いられます。
・苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)
水分代謝を整え、動悸やめまい、ふらつきなどに用いられます。四物湯や当帰芍薬散などと合わせて、血流を促しながら水分代謝を整える目的で用いられることもあります。
漢方薬を選ぶ際は、ご自身の体質や状態に合っていることがとても大切です。うまく合っていないと、効果を感じられないだけでなく、場合によっては副作用が生じることもあります。
漢方薬を探すといっても、自分ではよく分からないという方には、自宅にいながら相談できて症状に合わせた漢方を購入できるオンラインサービスという選択肢もあります。
中でも、無料で体質や症状の相談ができ、合う漢方薬を提案してくれる「あんしん漢方」がおすすめ。お手頃価格で漢方薬をご自宅に届けてくれます。
更年期障害との付き合い方の3つのコツ

ここからは、更年期障害との付き合い方の3つのコツをご紹介します。
正しい情報を入手し、自分の体について知る
女性ホルモンや更年期に起こる変化について、正しい情報を入手して自分の体について知ることも、更年期障害の症状と付き合っていくためには大切です。
積極的に正しい情報を入手して、日々の体の変化を意識し、自分の体を労ってあげましょう。
我慢し過ぎない
更年期障害は目に見える病気ではなく、さまざまな不調が現れる不定愁訴です。そのため、「つらい症状があっても我慢して家事や仕事をしなくてはならない」と考えている女性は多いです。
しかし、我慢してもいいことは何もなく、むしろ我慢によるストレスで症状が悪化してしまう可能性もあります。
我慢し過ぎず、休めるときは休養を取る、鎮痛剤を飲む、病院を受診して治療を受けるなどの対処を行いましょう。
無理せず自分の体の状態に合わせて行動する
女性ホルモンは、女性の心身に大きく影響します。
更年期はこれまで分泌されていた女性ホルモンが急激に減少することで、心身に不調が現れやすくなる時期であるため、変化に無理に逆らおうとせず、自分の体の状態に合わせて行動することが大切です。
つらい更年期障害の症状はセルフケアで対策を
イライラやホットフラッシュ、動悸やめまい、気分の落ち込みなどの更年期症状が強く現れて生活に支障が出ている場合は「更年期障害」の可能性があります。症状が重い場合は病院で検査を受け、適切な治療を受けましょう。
症状が軽い場合や、病院での治療と並行して、自宅でできるセルフケアで対策を行うのもおすすめです。症状の違いはあれど、更年期は誰もが通る道。自分の体を労り、うまく付き合っていきましょう。
※この記事は2022年10月の記事を再編集をして掲載しています。
■もっと知りたい■