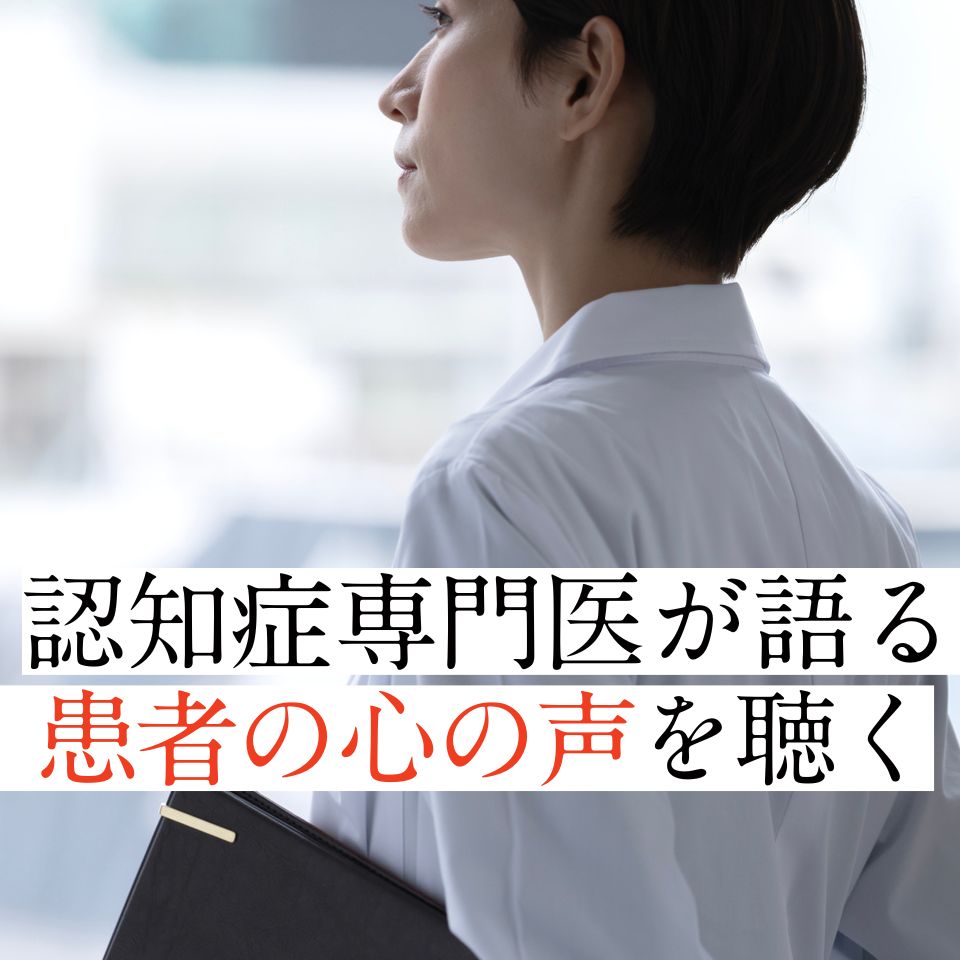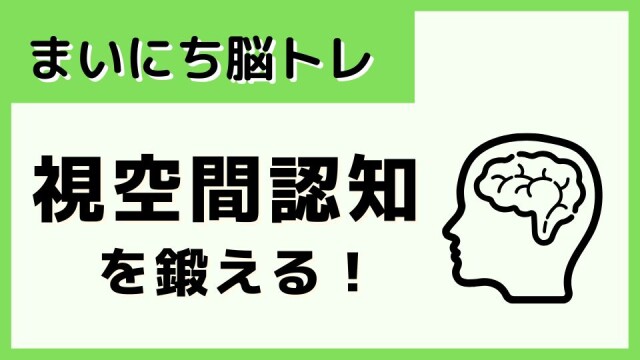認知症専門が語る「患者の心の声を聴く」#3
自分の最期を整えるには「今からでは遅過ぎる」?その気付きが心を楽にする
自分の最期を整えるには「今からでは遅過ぎる」?その気付きが心を楽にする
公開日:2025年10月25日

齋藤正彦(さいとう・まさひこ)さんのプロフィール
1952(昭和27)年、千葉県生まれ。精神科医、医学博士。都立松沢病院名誉院長。80年東京大学医学部卒業。専門は老年期認知症の医療、介護。82年より都立松沢病院精神科医員。東京大学医学部精神医学教室講師、認知症専門病院の和光病院院長などを経て2012年都立松沢病院院長。21年より同名誉院長。著書に『アルツハイマー病になった母がみた世界』(岩波書店刊)などがある。
認知症を完全に予防することは、老いを克服することと同義

「最期まで元気な体で、凛として過ごしていたい」というのは、多くの方が抱く願いです。その大きな妨げになり得る認知症は、何よりも怖い病気だと考える方も少なくありません。では今後、認知症は予防や根治ができる病気になるのでしょうか。
例えば認知症の7割近くを占めるアルツハイマー病について、65歳より下の世代に起こる若年性のものは、明らかな脳の異常であり、現在開発されている薬が効くのではと個人的には思います。
一方、80歳を超えて発症した患者の場合、認知症による脳の病変と、“自然な加齢現象”による脳の老化とが並行して進んでいて、高齢になるほどその境界線はあいまいで不可分です。実際、90歳以上の人口の約6割が認知症だという推計も出ています。
認知症を完全に予防し、根治することを目指すのは、老いそのものを克服しようとするような、途方もないことなのです。
「健康な自分」から「病気の自分」になると変わる意思

パズルなど脳を使う趣味に取り組む、適度な運動に励む、ということは、脳を活性化し「健康的に老いていく」ためには、確かに効果的です。ただどれだけ健康に配慮しても、「加齢」が最大の認知症リスクなのですから、年を重ねれば誰もがなり得ます。また遺伝的な要因など自分では制御できない理由から認知症になることも当然ある。
一方で、多くの人は「認知症には絶対になりたくない、予防したい」と思っていて、それに応えるような商品やサービスもあふれています。その風潮は認知症に対して前向きに対応しているようでいて、実は「認知症になるのは予防の努力を怠ったからだ」という“自己責任論”につながりかねない、と危惧しています。
「病気にならないようがんばり続け、いざとなったら家族の負担にならないよう意思決定する」ことが美徳……。今、そんな考えが社会全体に根付いているように思います。患者さんの中にも、「体が弱ったら潔く施設に入る」「認知症になってまで生きていたくない」などと話す方が少なくありません。
しかし、いざそのときになってみると、人はそう簡単に割り切れないものです。元気な頃「自分で食べられなくなったら、延命治療はしなくていい」と話していた患者さんが、嚥下(えんげ)力が落ちて口からの食事は危険だと言われたにもかかわらず、人目を忍んで盗食をしたケースもありました。
「肺炎の危険がある」と止められてもなお、食べる。なぜこのようなことが起こるか、理由は明白です。
「健康なときの自分」と「病気になった自分」とでは、ものの感じ方がまったく違うからです。いかに気丈な方でも、病気になり、今までになかった不安や心細さを感じたとき、「施設は嫌だ、自宅で過ごしたい」とか、「何とかして生き永らえたい」という執着に駆られることは、人間ならば当然あることです。
人の人生は決して「自己決定、自己責任」で完結しない
その意味で、終末期の医療についてあらかじめ自分の意思を「事前指示書」などの書類で残すことについて、私自身は賛成ではありません。健康なときに「延命治療を望まない」と意思表示していたとして、それが“今まさに病気に苦しんでいる自分”の意思と一致するでしょうか。健康な自分は、病気になった後の自分より、「正しい判断」ができるのでしょうか。そんなことは絶対にないと、私は思います。
もちろん、終末期にどのような医療を受けたいか、今の考えを家族に伝えることは無駄ではなく、いざというときに周囲の判断の後押しになるでしょう。しかしその意思表示があれば、本人や家族にとって「後悔のない看取り」ができるとは限らないのです。
認知症を患い、87歳で亡くなった母の看取りのときも、きょうだい3人でずいぶん話し合いました。微熱が続き、食事がとれなくなった母に対して、検査をして原因を突き止め、治療をするか否か。最終的には「積極的な治療はしない」と決め、静かに母を見送りました。
検査の身体的負担が、今の母には大きいだろうことや、母がその数年前に大きな手術をしたとき、「もう体を切るような治療は受けたくない」と話していたことなど、さまざまな状況を考え併せ、病院側とも相談の上で下した決断でしたが、それが母の意思に沿うものだったか、正解は知るすべがありません。
今思うのは、人の人生は決して「自己決定、自己責任」で完結しないということです。誰しも社会の中で協調し、支え合いながら生き、老いていくのですから、死だけ「書面で意思表示をして済ませる」のは無理があります。
家族や医療者もともに悩み、苦しみながらも結論を出す。それが人の死であり、見送る側の心に残った悲しみや後悔も含めて、その人との“つながり”だと、私は思います。
この先どうなろうとも「あとは運命に身を任せよう」

人生において、いつ何が起こるかは予測ができません。唯一、明確なのは、「老いと死は、誰にとっても必然」ということです。
わかっていても、それに備えるのは難しいものですね。人生を振り返って、「こんなはずでは」と物足りなさを感じたり、これからどう老いて、どう最期を迎えるかを不安に思い、「何をしたらよいのか」とくよくよ考えたりしてしまう方も多いのではないでしょうか。
そんな方は、少し考え方を変えてみませんか。自分の最期を整えるために今からできることは、実は「想像以上に限られている」のだと。
私が小学校の頃の話です。当時の私は、突発的に「母親が死んでしまったらどうしよう」という不安に襲われ、授業中に学校を飛び出して家に帰ってしまうことが何度もありました。母親はまだ若くて病気もなく、心配する理由もなかったはずです。
その後、精神科医になりずいぶんたってから、ふと気付きました。当時の私の不安は、幼い頃に両親を亡くした母自身の、「同じ悲しみを子どもに味わわせまい」という切迫感が無意識に私に影響し、引き起こされていたのではないかと。
これはほんの一例ですが、人の生き方は、母がそうであったように、親の存在や幼い頃からの環境で醸成されるマインドセット(無意識の思考や行動のクセ)により、知らず識(し)らずのうちに規定されています。
そしてそれは「文化的遺伝」とでも言うように、親から子へ、そのまた子へと受け継がれていきます。今の自分や、歩んできた人生は、その連綿と続いてきた流れの中にあり、“行き着くべくして行き着いた”ものと言えないでしょうか。敬虔なクリスチャンだった母ならば、きっと「神のお導き」と表現するでしょう。
こう考えると、どう老いて、どう最期を迎えるかをくよくよ考え不安に思っても、自分の力では「今さらどうしようもないこと」だと気付くはずです。それはあきらめではなく、歩んできた自分の人生を「あるがままに肯定する」ということに他なりません。
たまには「もう、このくらいでいいか」「今からでは遅過ぎる」と、肩の力を抜いてみませんか。自分の老いや死に対して、できる努力はしながらも、どこかで「あとは運命に身を任せよう」と思い切ることです。その鷹揚な構えが、心の平穏を保ちながら、最期まで自分らしく過ごすことへもつながっていくと、私は思います。
取材・文=新井理紗(ハルメク編集部)
※この記事は、雑誌「ハルメク」2025年2月号を再編集しています。