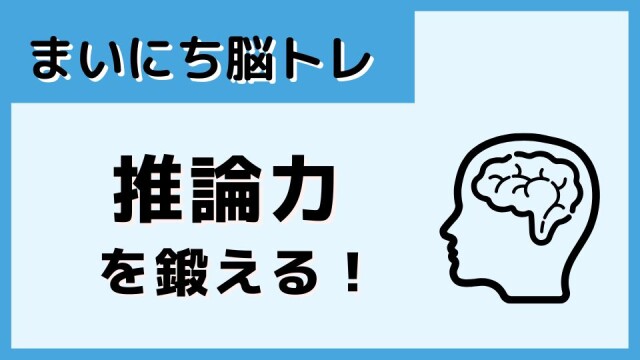認知症専門医が語る「患者の心の声を聴く」#1
認知症は「自我が揺らいでしまう病」不安に寄り添うためにできること
認知症は「自我が揺らいでしまう病」不安に寄り添うためにできること
公開日:2025年10月25日
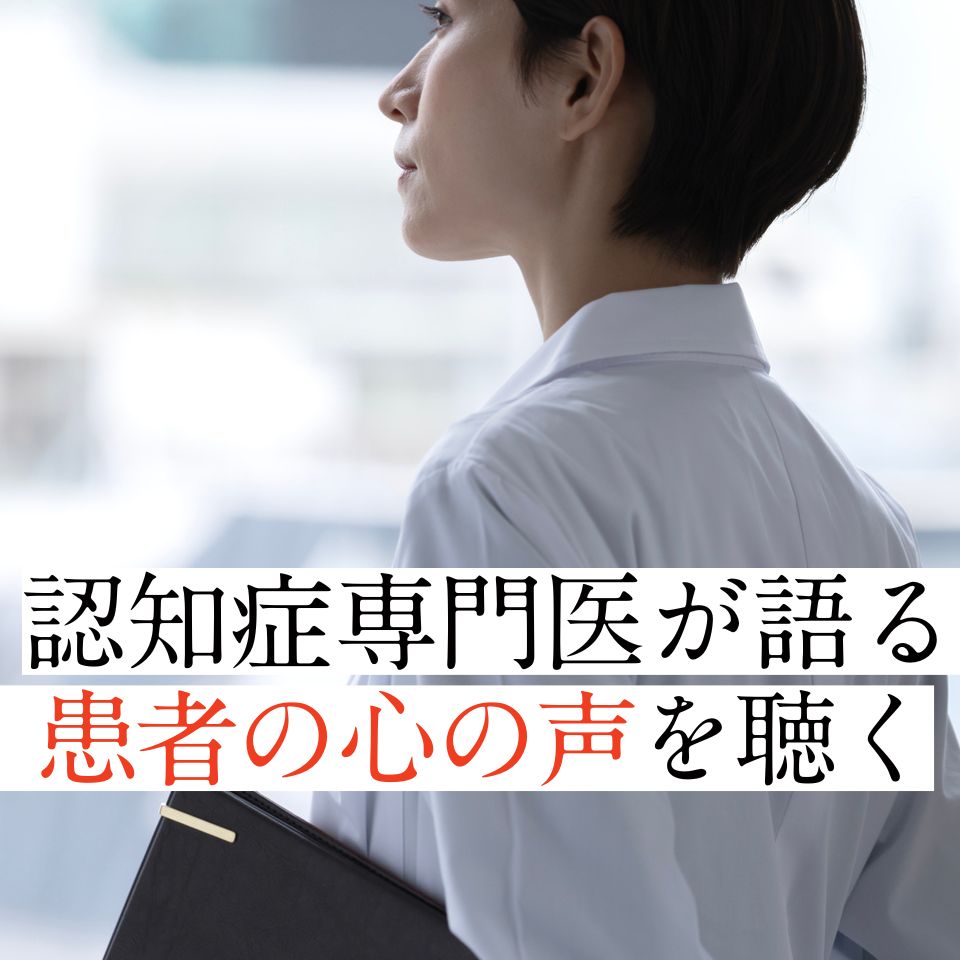
齋藤正彦(さいとう・まさひこ)さんのプロフィール
1952(昭和27)年、千葉県生まれ。精神科医、医学博士。都立松沢病院名誉院長。80年東京大学医学部卒業。専門は老年期認知症の医療、介護。82年より都立松沢病院精神科医員。東京大学医学部精神医学教室講師、認知症専門病院の和光病院院長などを経て2012年都立松沢病院院長。21年より同名誉院長。著書に『アルツハイマー病になった母がみた世界』(岩波書店刊)などがある。
「忘れてしまう」ではなく「記憶できていない」のです

1988年、私は日本で最も古い公立精神科病院・東京都立松沢病院の認知症病棟担当医になりました。以来、精神科医として認知症の方を専門的に治療・ケアしています。
認知症は「脳の病気」というイメージが強く、「精神科で何をするの」と思われる方もいるかもしれません。実は世界保健機関(WHO)の定義で、認知症は「精神疾患」に分類されており、精神科でCTやMRIなどを使った脳の検査や、投薬治療、作業療法などのリハビリが行われています。
認知症は多くが進行性で完治することはなく、生涯付き合い続ける病気です。そのため、患者やその家族が「いかに納得して、気持ちに折り合いをつけて病気と向き合えるか」をサポートすることが、検査や投薬といった医学的処置に劣らず、大変重要になります。
具体的には、今患者に起きている記憶障害や見当識障害(※)、徘徊などについて、「その原因(脳の萎縮状況など)」や、「患者は何ができなくなり、何はできるのか」「患者と家族は何ができるか」の説明に、言葉を尽くすことです。
例えば患者家族から特によく寄せられるのが、「何度同じことを説明しても忘れてしまう」という悩み。これは「忘れてしまう」のではなく、そもそも「記憶できていない」ことに起因します。
※見当識障害=時間や場所など、自分が置かれた状況を把握できなくなる障害
本人の失敗を防ぎフォローする工夫で、自信や尊厳を守る

脳の仕組みから、少し説明しましょう。五感から取り込んだ情報を「記憶」としてキャッチするのが、短期記憶を司る海馬です。加齢とともに海馬の働きは衰えますが、何度も繰り返し同じ情報に触れることで記憶することは可能です。
しかし、認知症の6~7割を占めるアルツハイマー型認知症では、情報をキャッチできないほど著しく海馬が衰え、今あったことを記憶として脳にとどめておけない症状が、発症後の早い段階で現れます。
一方、物事を把握する理解力は比較的残っているために、「言われたことにその場では納得するが、記憶としては残らず、何度も家族に聞き返す」という現象が起きるのです。このような患者に「さっき言ったでしょう。何度言ったらわかるの」と言っても、いたずらに本人を傷つけ自信を奪うだけです。
こうして、本人が置かれている状況を家族や周囲に理解してもらうことで初めて、相談し合いながら対策を講じることができます。
例えば「ヘルパーさんが9時半に来るから家にいてほしい」ことを本人に伝えるなら、口頭だけでなく、それを明記したメモを残すことです。さらに、メモを出掛けるときに必ず通る玄関のドアに貼っておけば、メモを見逃して外出してしまう事態も避けられます。
患者の失敗を未然に防ぎ、さりげなくフォローする工夫をしながら、今できることを続けてもらうこと。それが患者本人の尊厳や脳機能を守りつつ、自身の能力の低下と素直に向き合えることにもつながると、私は思います。
自身の異変に一番驚き不安を感じているのは、患者本人です
私が大学で精神医学を学んでいた約40年前、「認知症の患者本人には病識(自分が病気であるという自覚・意識)はない」と、教科書に書いてありました。物忘れをしても、「忘れている」こと自体を自覚できないのだと。
そのため患者本人の訴えは軽視され続け、現在もMRI検査や心理検査など検査所見に依存し、診断や治療を決めてしまう医師も少なくありません。しかし私は、長年の臨床医としての経験を経て、こうした見方が正しくないこと、そして自身の異変に一番驚き不安を感じているのは、他でもない患者本人だと考えるようになりました。
先ほどの「海馬」の説明で挙げたように、記憶障害で物事を「覚えられない」ために、物忘れ自体を認識できないことはあるでしょう。しかし、自分には心当たりがないのに周囲から「また忘れている」と言われ、以前はできていたことができなくなっていく現実に、「何かがおかしい」と不安に思わない人がいるでしょうか。
実際、家族に病院へ連れてこられて、はじめは「私はボケていない」と憮然としていても、よくよくお話を聞くうち「自分が崩れていく気がする」「馬鹿になったんだろうか」と、心の内の苦しみを打ち明けてくださる方がたくさんいらっしゃいます。
認知症患者の多くが直面する困難は、自分が制御できない、自分が何者かわからない、“自我が揺らぐ”ことへの恐れです。そこに少しでも光を当て得るとしたら、真摯な対話を通じて、その方が感じている主観的な症状や苦しみを理解し、寄り添おうと努めることではないかと思います。
どんな状態になろうと、人生を生きる主体は、その人自身に他ならないのですから。
「弱者とともにあれ」。しかし自分は、“強者”なのだろうか

私の「患者のそばにいなければ」という考えの根底には、2011年に87歳で亡くなった母の影響があるのかもしれません。母は敬虔なクリスチャンで、「弱者とともにありなさい、手を差し伸べなさい」という人でした。
母の考え方は尊重していましたが、他者を「弱者」とする考えには、自分が「強者」という前提があるようにも思います。では、患者を診る私は「強者」で、患者は「弱者」なのでしょうか。医師としての経験を重ねるほど、「そうではない」という思いが強くなっていきました。
私は2012年に松沢病院の院長に就任してから、統合失調症の患者も多数、診るようになりました。彼らの話を聞き、その挫折や人生のつまずきを知るうち、ふと「同じような経験が私自身にもたくさんある」ことに気付いたのです。
自分は今、心身ともに大きな問題なく過ごせているけれど、それは単に“運”でしかなく、何かのきっかけで立場が逆になっていたかもしれないーー。
繰り返し彼らと自分の人生を重ねる中で、私たちは医師も患者もなく、「神の前で等しく弱い存在」なのだと感じるようになりました。その実感が、「おごらず謙虚に、患者と目線を合わせることを忘れるな」という自戒となって、今も私を律してくれているように思います。
83歳でアルツハイマー型認知症と診断された母のこと
認知症は、72歳の私にとってはすでに身に迫っている病です。生きている限りは、脳も体も極力健康に保ちたいとは思います。一方で、いざそのときとなったら、できなくなったことは受け入れながら、仕事や趣味、住まいなどを適切にダウンサイジングし、いかに「今の生活を穏やかに、平和に過ごすか」を第一に暮らしを整えようと決めています。
そう考えるのは、83歳でアルツハイマー型認知症と診断された母を間近で見てきた経験からです。母はもともと学ぶ意欲にあふれた人で、古典文学や聖書の勉強会、短歌の会など、さまざまな集まりに参加していました。
認知症の症状が出てからも、「私はまだ大丈夫」「しっかりしなくちゃ」と必死だったのでしょう。懸命に参加を続けていましたが、以前のように歌が詠めない、集合時間を間違える、といった失敗の積み重ねにショックを受け、自信を失っていった様子が、当時の日記に綴られています。
実の息子として、認知症の専門家として、もっと母のためにできることがなかったか、何が正解だったのか。今も逡巡は絶えませんが、認知症の母と向き合う日々はまた、たくさんの気付きももたらしてくれました。それについては次回、お話しします。
取材・文=新井理紗(ハルメク編集部)
※この記事は、雑誌「ハルメク」2025年2月号を再編集しています。