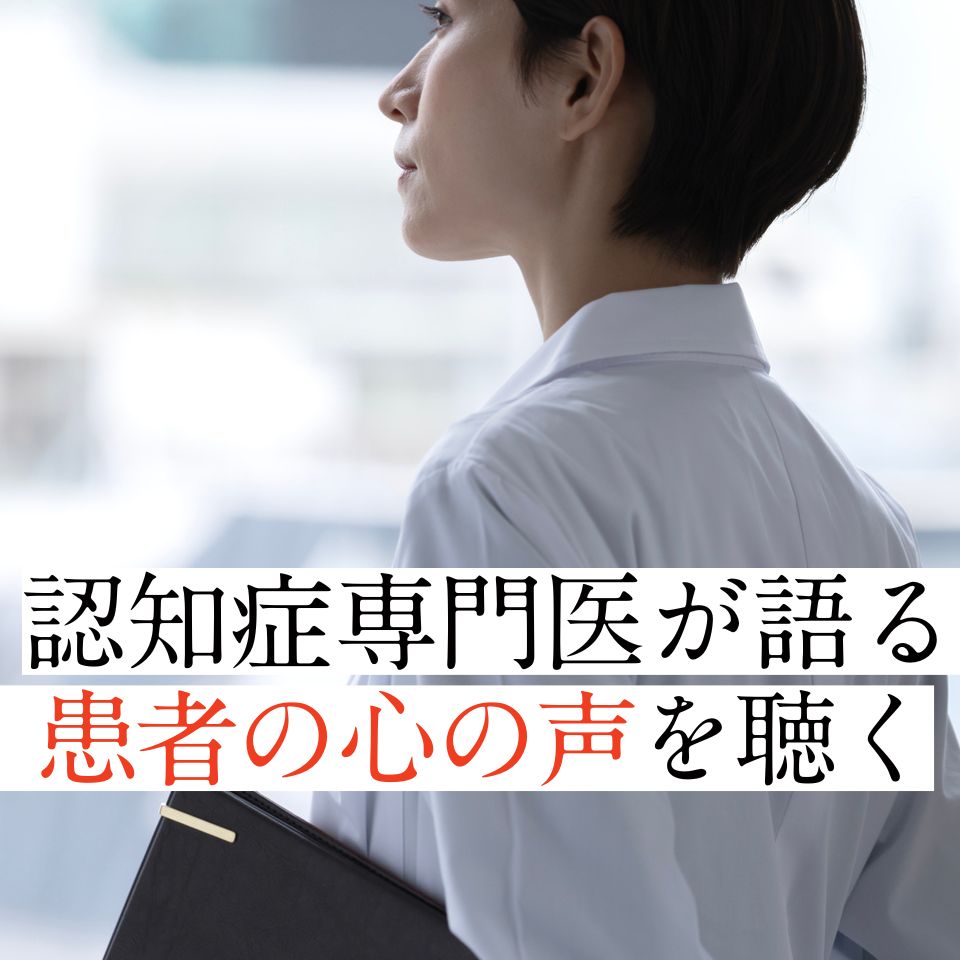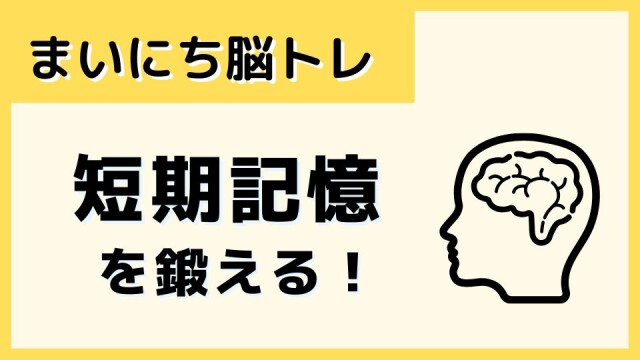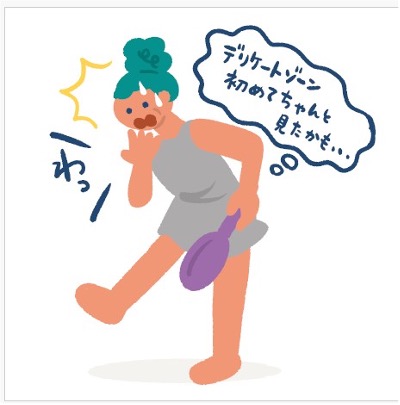認知症専門が語る「患者の心の声を聴く」#2
認知症になった母が書き続けた「日記」が教えてくれたこと
認知症になった母が書き続けた「日記」が教えてくれたこと
公開日:2025年10月25日

齋藤正彦(さいとう・まさひこ)さんのプロフィール
1952(昭和27)年、千葉県生まれ。精神科医、医学博士。都立松沢病院名誉院長。80年東京大学医学部卒業。専門は老年期認知症の医療、介護。82年より都立松沢病院精神科医員。東京大学医学部精神医学教室講師、認知症専門病院の和光病院院長などを経て2012年都立松沢病院院長。21年より同名誉院長。著書に『アルツハイマー病になった母がみた世界』(岩波書店刊)などがある。
64歳で父亡き後、失われた青春を取り戻すように活動的に

今、私の手元には、母が遺した18冊の日記帳があります。母の認知症が進行し、自宅から施設に引っ越す際、私から母にお願いして譲り受けたものです。認知症を専門的に診る精神科医として、当時の母が何を感じ、何を書き留めているかを知りたい気持ちからでした。
日記ですから、人に読まれることを前提にしておらず、息子である私に知られたくない思いも綴られていたかもしれません。それでも母は、「あなたの研究のためなら」と快く応じてくれたことを、今も覚えています。
1924年、大正の終わりに生まれた母は、終戦後すぐに結婚し、歯科医である父を支え、私と弟、妹の3人きょうだいの子育てに全力を注ぐ日々を過ごしました。大きな転機は、64歳のときに父を肺がんの術後の合併症で亡くしたこと。
その後しばらく落ち込んで過ごしましたが、もともと知的好奇心が旺盛で、社会貢献への思いも強かった母は、父の死から3年後には見違えるように活動範囲を広げていきました。若い頃から参加していた短歌の会に加えて、自宅で留学生に日本語を教える仕事を始め、古典や聖書の勉強会にも精を出し、習字や生け花、スペイン語、ピアノのレッスン……。
毎日のように予定を入れ、国内外の旅行へも頻繁に出掛ける奔放さは、家庭生活では叶えられなかった自己実現を一気に果たすかのごとくであり、戦争で失われた青春を取り戻しているようでもありました。
一方、母の日記では、認知症と診断される10年ほど前の70代半ばから、認知機能の低下を嘆く記述が目立ち始めます。歌会の約束の時間を間違える、電車に手荷物を忘れるなどのミスをはじめ、得意だった料理も、煮物を焦がす、味付けが決まらないなど、失敗を重ねていたようです。
「この頃めっきり(料理が)下手になって困る」「本当に嫌になってしまう」と不安の言葉が頻出しています。
70代後半、母が感じていた不自由さと不安に、鈍感だった私

認知機能が低下した際、本人にとって深刻なのは、脳の萎縮度合いなどの客観的データよりも、脳の変性によって「今までできていたことが、どれだけ不自由になってきたか」ということです。生活を支えてくれる家族がいて、穏やかに過ごしていれば、たとえ認知機能が低下していても、顕在化しにくいケースもあります。
しかし母は、仕事が多忙な妹と二人暮らしで日中は一人で家事をこなし、高度な記憶力、言語力を使う趣味や習い事を数多く抱えていたため、早い段階で“不自由”を感じることになったのでしょう。
当時の私はといえば、母の変化を察知していながら、その不安にはまったく鈍感だったと言わざるを得ません。母が77歳のとき、馴染みの悉皆(しっかい)屋さんから「仕立てた襦袢(じゅばん)代の3万円が未払い」だと指摘され、私が勝手に支払ったことがありました。
母自身は「確かに払った」と主張していたにもかかわらず、です。「話がこじれても面倒だ」と考えてフォローしたつもりでしたが、その後の母の日記には、「私をまったく信用していない」「年寄りはこうやって邪魔にされる」などという怒りが繰り返し書かれていました。
この出来事が母を深く傷つけていたことに、母の死後、日記を読んで初めて気付くという情けなさ。同時に、私の行動を看過できないほどに、母が自信を失っていたのだと思い返すのです。
母の苦しみも孤独も「母だけのもの」。家族にできることは…
80歳を超えて以降、胃がんや大動脈瘤の手術も重なり、何とか続けていた習い事や集まりへも参加が難しくなりました。日記には、「頑張れ!レイコ!」と自分を鼓舞しつつ、「このまま呆けてしまうのだろうか」と焦りを感じる様子が見てとれます。
そして2007年、83歳のときに母はアルツハイマー型認知症と診断され、翌年には私の自宅近くの有料老人ホームに入居することになりました。この頃母は「何かに失敗して困った」というより、一人でいることの不安に苛(さいな)まれていたように思います。
例えば私なら、家に一人でいても「何時には妻が帰ってくる」「電車でこれくらい行けば弟がいる」と認識できますが、母はすでに、日時や場所、人間関係の認識(見当識)が障害され、外界との「つながり」に確信が持てなくなっていました。そのため、一人にされると「何で私はここにいるの、なぜ一人ぼっちなの」と一気に落ち着かなくなります。
自分が自分でなくなるような、深く、本質的な不安です。一方で私たち家族の心配は、「母の生活をどう支えるか」という現実的なことばかりに向いていて、母の抱えていた不安に手を差し伸べることはできませんでした。
この“すれ違い”は、どの家族にも起こる普遍的な問題だと思います。結局、その人が感じる孤独や苦しみは、本人だけのものです。
周囲が完全に理解して寄り添い、まして「救い主になろう」などというのは不可能ですし、おこがましいことです。私たちにでき得たことは、母に顔を見せ、そばにいる時間をつくり、母の中で失われた「つながり」をひととき思い出してもらうことくらいでした。
自我を蝕まれ自律を失っても、最期までもがき続けた母

私自身、今は母の介護に後悔することはありません。ただ母にもう少しだけ肩の力を抜き、いい意味で現実に妥協し、老いを柔軟に受け入れる心構えがあったら、もっと安らかな晩年を過ごせたのではないかと思います。
母がそう生きられなかったのは、育った環境に一因があると、私は分析しています。4歳で母親を、12歳で父親を病で亡くした母は、年の離れたきょうだいを親代わりに育ち、普通なら両親を通じて学んだはずの現実世界のしがらみとは無縁のまま大人になりました。
そして夫亡き後、自由な時間を得た母は、理想や憧れのままに、年齢に比して過剰ともいえるほどに社会活動を広げていきました。認知症の進行でその理想が叶わなくなったことに、母は苦しんだはずです。
一方で日記に遺された文章には、徐々に自我を蝕まれ自律を失っても、すべてを人任せにして過ごすことを最期までよしとせず、「何とかしなくては」ともがき続けた母の意志がにじんでいます。
ことすべて叶うこととは思わねど
己が歩みをますぐにゆかむ
これは母の遺した短冊に書かれていた歌です。亡くなる前年のクリスマス、施設のツリーに飾るために書いた短冊のようですが、元の短い文章を何度も推敲して、短歌にまとめ上げた形跡がありました。
当時の母はすでに短期記憶が損なわれ、日記すら書けなくなっていた状況を考えると、奇跡のようです。恐らく母は、何のために書いた短冊かもわかっていなかったでしょう。それでも目の前の文章を、何とか一首の歌に仕上げようとしたその試みこそが、母の歩んだ道そのものであり、人生の総決算だったように私は思います。
これが私の知る限り、母が最期に詠んだ歌でした。
母を思い返すと、結局は「どう生きたかの先に、死がある」ということを実感します。
自分の最期を思うように整えることは、誰にとっても非常に難しいことです。それは理解しつつも、避けがたい老いや、認知症をはじめとする病を前に、できるだけ心穏やかに自分の生を全うするには何が必要なのか。私なりの考えを、次回お話ししたいと思います。
取材・文=新井理紗(ハルメク編集部)
※この記事は、雑誌「ハルメク」2025年2月号を再編集しています。