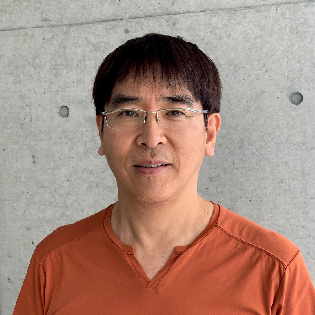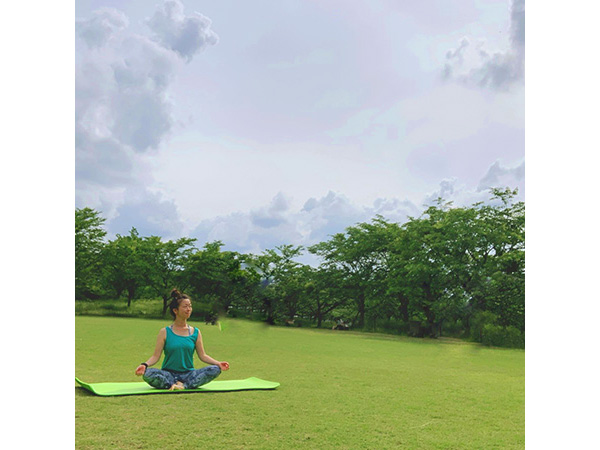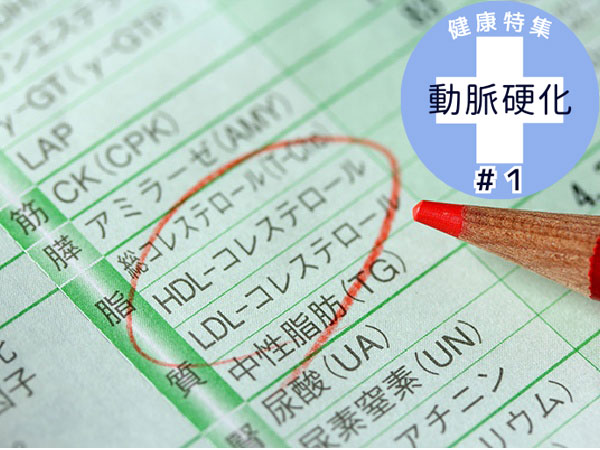意外と多い「多汗症」自力で治せる?病院に行くべき?
ちょっと動くと汗が出るのは多汗症?病気・原因・治療
ちょっと動くと汗が出るのは多汗症?病気・原因・治療
更新日:2025年07月23日
公開日:2023年11月14日

ちょっと動くと汗が出るのはなぜ?考えられる病気・原因

汗をかくのは自然なことですが「異常な発汗がある」「尋常じゃない汗をかく」「少しの運動で大量の汗をかく」といった場合は、何か病気が影響している可能性が考えられます。
ここからは、ちょっと動くと汗が出る場合に考えられる病気や原因について見ていきましょう。
基礎代謝の向上(冬など寒い季節の場合)
寒い冬は体温を維持するため、体内で熱の産生が活発になり、基礎代謝が高まります。これによって、普段なら汗をかかないような少しの動きでも汗が出ることがあります。
また、暖房の効いた室内で厚着をしていると、さらに汗をかきやすくなることも。このような基礎代謝の向上による発汗であれば、問題はないと考えられるでしょう。
ただし、服装を薄着しても発汗が続く場合は、ホルモンバランスや自律神経の乱れ、病気の影響も考えられるため一度病院を受診すると安心です。
暖房の効き過ぎた室内で「冬でも汗をかく」、冷房の効き過ぎた室内で「夏でも汗をかかない」といった状況が続くと、汗のコントロールがうまくできなくなり体の不調につながる可能性もあるため、季節に合わせて適切な服装や空調に調節しましょう。
更年期の影響
「若い頃は汗かきじゃなかったのに、50代になって汗をかくようになった」という場合、更年期の影響が考えられます。
更年期には、女性ホルモンの急激な減少が起こりますが、これによって「ホットフラッシュ」という更年期症状が見られることがあります。
ホットフラッシュは更年期に起こるのぼせやほてり、発汗といった症状のことで、汗が止まらなくなったり、急に顔が熱くなったりする症状が起こります。
ホットフラッシュは、時間帯や季節に関係なく、いきなり症状が起こることが特徴です。ストレスや緊張があるときには、症状が悪化することも少なくありません。
急に体が熱くなった後で急激に冷える「冷えのぼせ」となることもあります。
自律神経失調症
自律神経失調症とは、自律神経である交感神経と副交感神経のバランスが崩れることで起こる、さまざまな体の不調のことです。
ちょっと動いただけで汗をかくといった症状の他にも、以下のような症状が見られます。
- めまい、耳鳴り
- 立ちくらみ
- 息苦しさ、胸が締め付けられる感じがある
- 夏でも手足か冷えることがある
- 手足がだるい
- 気候の変化に問わくなる
- 寝ても寝ても眠い
- 手足や体がだるい
- 胃腸の調子が悪い など
高齢になると、自律神経の調整能力が低下することで発汗が起こることもありますが、他の病気が隠れていることもあるため、汗が気になる場合は放置せず病院を受診しましょう。
多汗症
「ちょっと動くと汗が出るようになった」「季節に関係なく大量の汗をかく」「手汗で紙が濡れてしまい困っている」といった症状が見られる場合、多汗症の可能性があります。
多汗症については、次からの項目で詳しく見ていきましょう。
多汗症とは

多汗症とは、汗をかく量が異常に多く、日常生活に支障を来たしている状態のことを指します。
多汗症は身近な病気で、厚生労働科学研究班の調査によれば、掌蹠多汗症(手のひらや足の裏に起こる多汗症)の重症者が80万人もいるといわれています。
多汗症は重症になると「顔からポタポタと汗が滴る」「紙が濡れてしまって記入できない」など、生活の質の低下につながる疾患ですが、病院に受診している人は少ないといいます。
つらい症状を我慢して悩み続けるよりも、早めに病院を受診して適切な治療を受けることが大切です。
多汗症の特徴
多汗症には、以下のような特徴があります。
- 多汗・無汗を繰り返す
- 体の左右で同時に発汗する
多汗症は、常に大量の汗をかいているわけではなく、多汗・無汗を交互に繰り返すことが多いです。運動や気温に加えて、緊張などによる体温上昇がきっかけになることもあります。
また、体の左右で同時に発汗することも特徴です。汗をかきやすい場所としては顔や頭部、手のひらや足の裏があり、複数の部位で多汗となることが多いです。
多汗症の症状レベル
「原発性局所多汗症診療ガイドライン 2023 年改訂版」によれば、多汗症は「汗の症状でどの程度、日常生活に支障が出ているか」で重症度が判定されます。
判定には「HDSSスコア」(Hyperhidrosis disease severity scale)が用いられます。HDSSスコア3、4が重症の指標です。
- HDSSスコア1……発汗は全く気にならず、日常生活に全く支障がない
- HDSSスコア2……発汗は我慢できるが、日常生活に時々支障がある
- HDSSスコア3……発汗はほとんど我慢できず、日常生活に頻繁に支障がある
- HDSSスコア4……発汗は我慢できず、日常生活に常に支障がある
この他、掌蹠多汗症の場合は、手のひらの汗の出る量の目安とした3段階のレベル評価で、症状を評価することもあります。
多汗症でよく見られる症状

以下は、多汗症でよく見られる症状です。
- 頭から過剰に汗が出る:頭部多汗症
- 顔から過剰に汗が出る:顔面多汗症
- 手の平や足の裏から過剰に汗が出る:掌蹠多汗症
- 脇から過剰に汗が出る:腋窩(えきか)多汗症
ここからは、それぞれの症状について解説します。
頭から過剰に汗が出る:頭部多汗症
頭部多汗症は、頭皮から汗をかく多汗症です。
ストレスの多い環境や、不規則な生活をしている人は自律神経が乱れやすく、頭部多汗症の症状が起こりやすいとされています。
遺伝的な要因もあるとの報告があります。
顔から過剰に汗が出る:顔面多汗症
ちょっと動いただけなのに顔から過剰なほどの汗が出る場合、顔面多汗症の可能性があります。
顔面多汗症は2〜10年など長期間症状が続くこと、額や鼻の周辺に大量の汗をかくことが特徴で、運動やストレスだけでなく、熱いものを食べたときにも症状が悪化することがあります。
頭部多汗症と同時に起こることも多く、この場合は頭部顔面多汗症と呼ばれます。
手の平や足の裏から過剰に汗が出る:掌蹠多汗症
掌蹠多汗症とは、手のひら(掌)や足の裏(蹠)に過剰な汗をかく症状のことです。手のひらだけに見られる場合は手掌多汗症、足の裏だけの場合は足蹠多汗症と呼ばれることもあります。
掌蹠多汗症は軽症〜重症までさまざまで、ストレスが高まったときだけに汗が出る程度という場合もあれば、汗が滴るほどになることも。
手に汗をかいていると、コミュニケーションの際に「相手に不快感を与えるのではないか」と不安になり、コンプレックスとなってしまうことも少なくありません。
10〜18時頃に多く見られ、睡眠中はあまり汗は見られないことが特徴です。季節も影響し、暑い時期になると汗の量が増えます。
脇から過剰に汗が出る:腋窩(えきか)多汗症
腋窩(えきか)多汗症は、脇に大量の汗をかく多汗症です。体温が上昇したときや緊張したときに症状が悪化する傾向にあります。
なお、腋窩多汗症とワキガは異なる病気で、脇汗が多いからといってワキガとは限りません。
しかし、腋窩多汗症はワキガを引き起こす原因となることがあり、臭いや汗が気になって仕事に集中できない、人前に出られないといった悩みにつながることもあります。
多汗症の分類と原因

多汗症は「汗の出方」と「原因」で分類できます。
多汗症の汗の出方
多汗症は汗の出方によって「全身性多汗症」と「局所性多汗症」に分類できます。
- 全身性多汗症……全身の発汗が増える多汗症。全体の約10%
- 局所性多汗症……特定の部位だけ発汗が増える多汗症。全体の約90%
全身性多汗症と局所性多汗症では、局所性多汗症の方が圧倒的に多く、多汗症の約90%を占めるといわれています。
全身性多汗症の一部は遺伝の影響が関与していると考えられており、家族や親戚に同じ症状が見られる場合は、全身性多汗症の可能性が考えられるでしょう。
多汗症の原因
多汗症の原因は以下の2つに分けられます。
- 続発性多汗症……他の病気に合併して起こる多汗症
- 原発性多汗症……原因が特定できない多汗症
続発性多汗症は、他の病気に合併して起こる多汗症です。以下のような病気が原因となって、多汗の症状が起こります。
- 更年期障害
- 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)
- 低血糖
- 糖尿病
- 褐色細胞腫
- 悪性リンパ腫
一方、原発性多汗症では、原因となる病気がないのに、日常生活に支障が出るほどの発汗が起こります。
原発性多汗症の原因ははっきりしていませんが、自律神経が乱れやすく交感神経の活動が亢進しやすい、家族に同じ症状の人がいる、脇の臭いが強い(通常より「アポクリン汗腺」が大きく分泌量が多い)といった要因の影響が示唆されています。
多汗症の治療法
多汗症の治療には、以下のようにさまざまなものがあります。
- 外用薬
- 内服薬
- 漢方薬
- ボツリヌス注射
- イオントフォレーシス(発汗の多い部位を水を貯めた容器に浸して10~20mAの電流を流す治療)
- 交感神経遮断術
- 精神療法
- ミラドライ(マイクロ波を用いて汗腺を破壊する治療) など
多汗症の部位によって適用される治療が異なり、またどこの皮膚科・形成外科でもされている治療でないものも多いため、受診される前にまずは問い合わせ、気になっている症状を伝え、その治療を行っているかどうかを確認するのが良いでしょう。
他の病気が原因になっている「続発性多汗症」の場合は、それぞれの疾患に対する治療を先ず行います。
このように一人ひとりの原因や症状によって適した治療は異なるため、異常を感じたらまずは医師に相談して、適切な治療法を見つけましょう。
もしかして多汗症?症状のセルフチェック
以下の項目のうち、2つ以上があてはまる場合、発汗量が増えた期間が6か月以上続く場合は多汗症の可能性があるため、病院を受診しましょう。
- 25歳より前から発汗の症状が始まった
- 親や兄弟など親族に多汗症の人がいる
- 体の両側でほとんど同じくらいの量の汗をかく
- 週に1回は汗によって困る出来事がある(握手を躊躇する、急な発汗で人前に出るのが恥ずかしいなど)
- 日常生活に支障をきたしている(制汗剤が手放せない、汗じみが気になって好きな服を着るのを躊躇うなど)
- 精神的に落ち着いているときや寝ているときには汗をかかない
ちょっと動くと汗が出る・多汗症は自分で治せる?

多汗症を自力で治したい場合、以下のような方法によって汗の量を抑える、多汗症を予防するといった対策ができます。
- 生活習慣の改善
- 食生活の改善
- ストレスの軽減
食事や生活習慣も発汗に影響しているため、生活習慣や食生活の改善によって、汗の量が減る可能性があるでしょう。例えば、中枢神経を刺激するカフェインは、過剰摂取すると汗が増える原因になります。アルコールも発汗を促すため、量を減らす、禁酒といった対策が有効です。
過度なストレスがあると交感神経が優位になり、多汗につながることがあるため、ストレスをためない工夫や定期的なストレス発散を行うといいでしょう。
ただし、多汗症の症状には個人差があり、自力で治すのが難しいケースもあります。治療が必要な場合もあるため、我慢せずに病院を受診することが大切です。
ちょっと動くと汗が出る場合は病院に行くべき?
多汗症状には、重篤な病気が隠れていることもあります。
- 発汗の症状が強く日常生活に支障をきたしている
- 突然症状が現れ、普段よりも強く発汗が出る
- 症状が急激に進行している
- 息切れ、動悸、悪寒、ほてりなど他の症状も見られる
- 心疾患、内分泌系の疾患など基礎疾患がある
上記のような場合は放置せず、すぐに病院を受診して詳しい検査を受けることが大切です。多汗のみが見られる場合は皮膚科、多汗以外にも症状がある場合は、内科を受診するといいでしょう。
気になる発汗がある場合は早めの受診を
多汗症に悩んでいる人は少なくありません。日常生活に支障が出ているとQOLにも関わるため、我慢せずに早めに病院を受診しましょう。
更年期や自律神経の影響による発汗の場合もありますが、なんらかの病気が原因となっているケースもあります。突然症状が現れて普段よりも強く発汗が出る場合や、症状が急激に悪化している場合などは、すぐに病院を受診しましょう。
監修者プロフィール:髙橋 謙さん
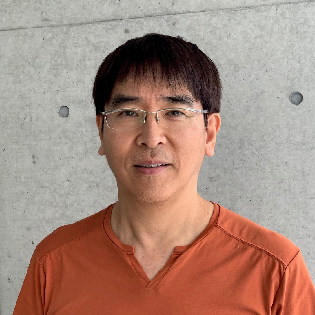
1999年大阪医科大学(現大阪医科薬科大学)卒業、東京女子医科大学循環器内科へ入局。その後、実家クリニック(元髙橋内科皮膚科クリニック、現在は閉院)の継承、京大病院総合診療科、関西電力病院総合内科、髙橋内科皮膚科クリニック、大阪市立総合医療センター皮膚科を経て、2015年12月にたかはし皮膚科クリニックを開業。これまでの豊富な経験を生かし、現在は1日当たり80~130人の患者さんの診療にあたる。
※HALMEK upの人気記事を再編集したものです
■もっと知りたい■