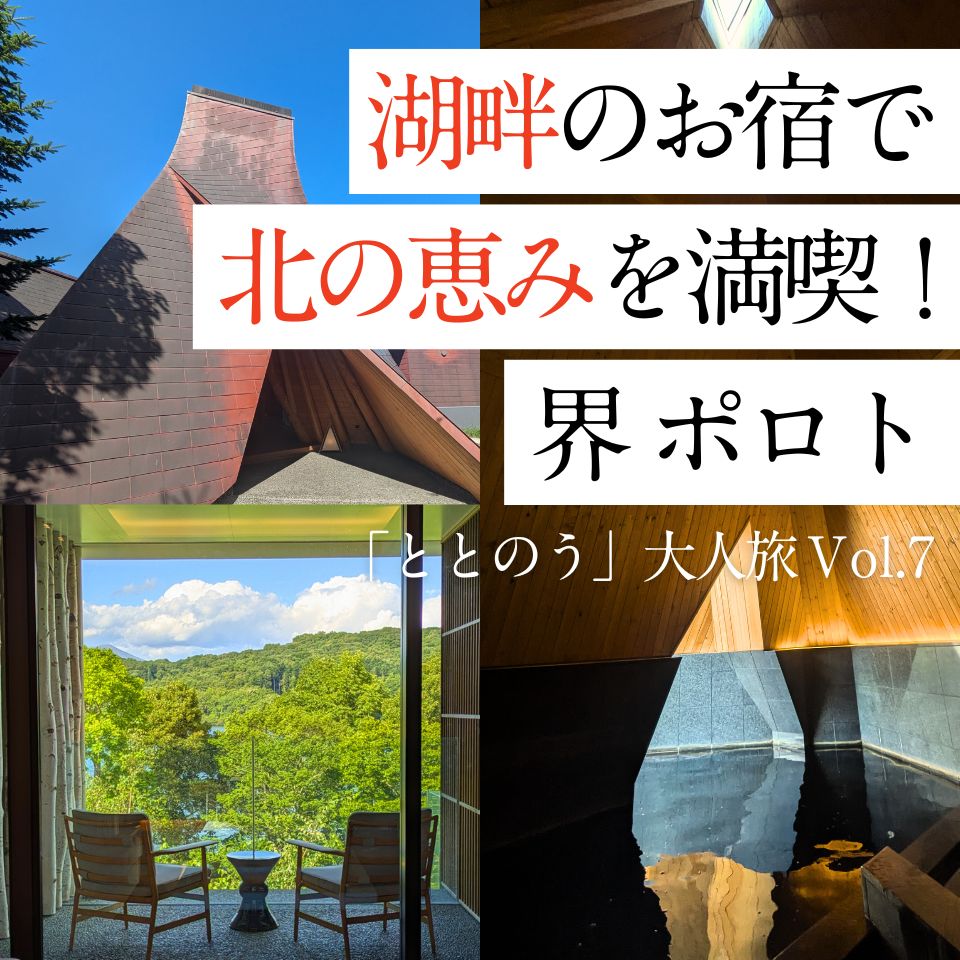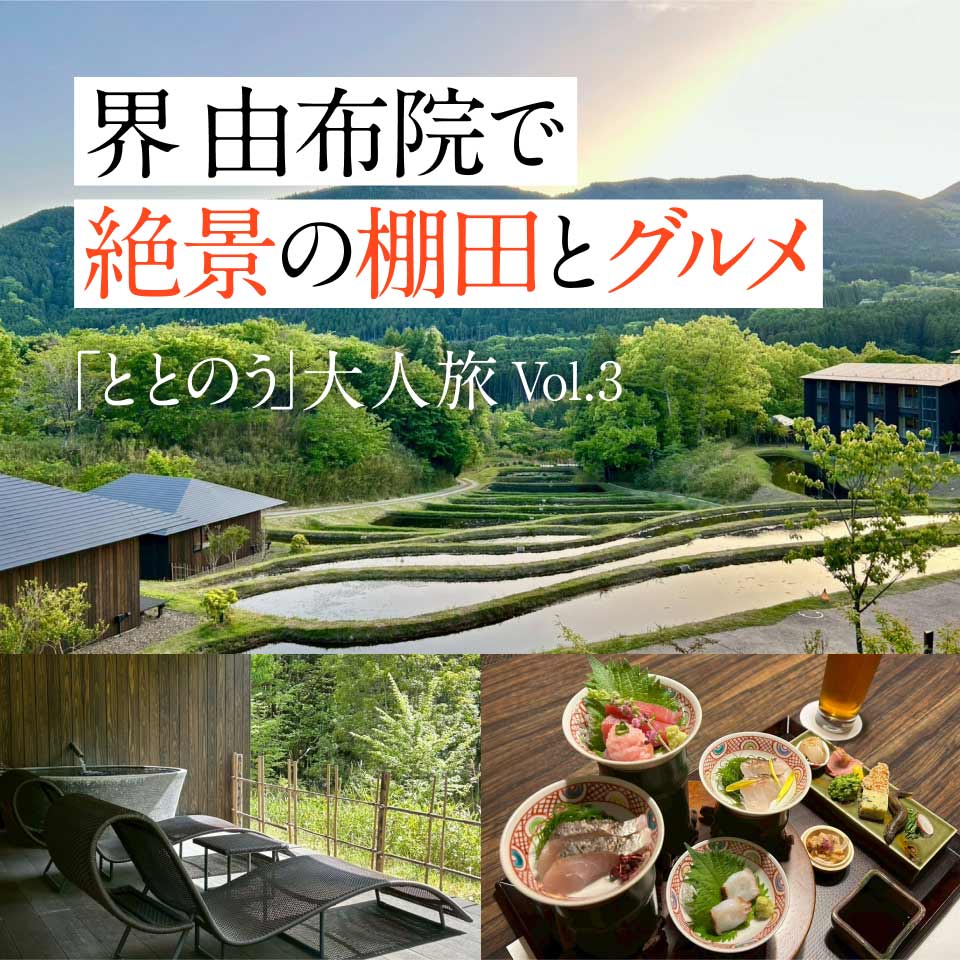縄文文化体験と津軽三味線
「三内丸山遺跡」で、センスオブワンダー全開
「三内丸山遺跡」で、センスオブワンダー全開
公開日:2023年01月08日

世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」
「三内丸山遺跡」(青森県)は、世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」を構成する史跡のひとつで、日本最大の縄文集落です。
約1万年続いた縄文時代の中期、今から約5900年~4200年前までの1700年の長期にわたり、縄文人が定住していたことが分かっています。
遺跡見学は、シニアガイドさんにおまかせ
広大な遺跡をボランティアガイドさんが案内してくれます。
シニアです。奈良もそうだけれど、観光ガイドとして活躍するシニアは、みんな生き生きしています。良いお仕事だ。勉強になるし、運動にもなる。喜んでもらえるからやりがいもある。
広くてなだらかな丘。メインストリートは当時のものを復元して12m~15m幅。
最盛期の人口は、500人とも800人とも。
竪穴式住居! 教科書で見たのと一緒!
腰を低くかがめてよっこらしょ。
中は、天井が高くて、意外とゆったり。違った、天井が高いのではなく、床を掘り下げているから、高く見える。
これは、「大型竪穴建物」の内部。約32mの長さ。柱は栗の木。もともとこの地に栗の木はなく、縄文人が自分たちで栗を植え、管理していたそうです。
何に使われたのかは不明だけれど、公民館や役所みたいな使われ方をしていたのでは? と、ガイドさんは遠い目。
なにせ、紀元前3900年~2200年のお話。
想像するしかない。むしろ自由に想像できるのがいい。
映えるこちら↓も、使途不明。見張り台? 祭事に使われた? 高さ15m、これも栗の木でできています。
「縄文の人は、重くて太い柱をどうやって立てたんでしょうね。これ? これは大林組さんが重機を使って立ててくれたんですけど」。
大林組って、ビルやマンションだけでなく、こういうのも建設するんですね。
「縄文時遊館」で、縄文の暮らしを自由(時遊)に想像
「縄文時遊館」には、土器や土偶のほかに、魚やウサギなどの動物の骨、貝殻も展示されています。
縄文人が食べていたのは、イカ、シャコ、ウニ、アワビ、カニ、サザエ、ドジョウやアユ、ヤツメウナギ、鴨にキジ、栗、クルミ。ひゃ~うらやましい。
ヒスイや黒曜石のアクセサリーや漆器、櫛、そして木の皮で編んだポシェット。中にクルミが入っていました。
ポシェットの持ち主は、子どもなのかな? その子はどうなったの?
そもそも集落がなぜなくなったのかも不明。
だから、やっぱり想像するしかない。
津軽三味線の生演奏を「津軽じょっぱり漁屋酒場」で
夜は、青森市内の「津軽じょっぱり漁屋酒場」へ。コロナ禍前に来て以来2度目の来訪。
津軽三味線の生演奏を聴くことができる数少ないお店のひとつです。
照明が落ちて、ねぷたの張り子に明かりが灯り、ライブがスタート。
私のキンキの塩焼きの1m先に、三味線を弾くお嬢。※演奏は写真掲載NGのためナシ。
耳に目に舌に、THE青森!
津軽三味線には、吉田兄弟などが有名な「叩き三味線」と「弾き三味線」があります(お嬢談)。
お嬢の演奏は「弾き三味線」。一音一音が独立していて、話しかけてくるよう。吉田兄弟がロックだとしたら、こちらは演歌な感じ。ポップな調子の曲でも、大人の情緒。
やんややんやの喝采とおひねりが飛びまくったからか、通常30分の演奏が50分ほどに延長。
今度行く時は、私もポチ袋を用意しておこう。
青森市内に宿泊の際はぜひ! 青森に来たぞ! って実感できて、大満足間違いなしです。
■もっと知りたい■