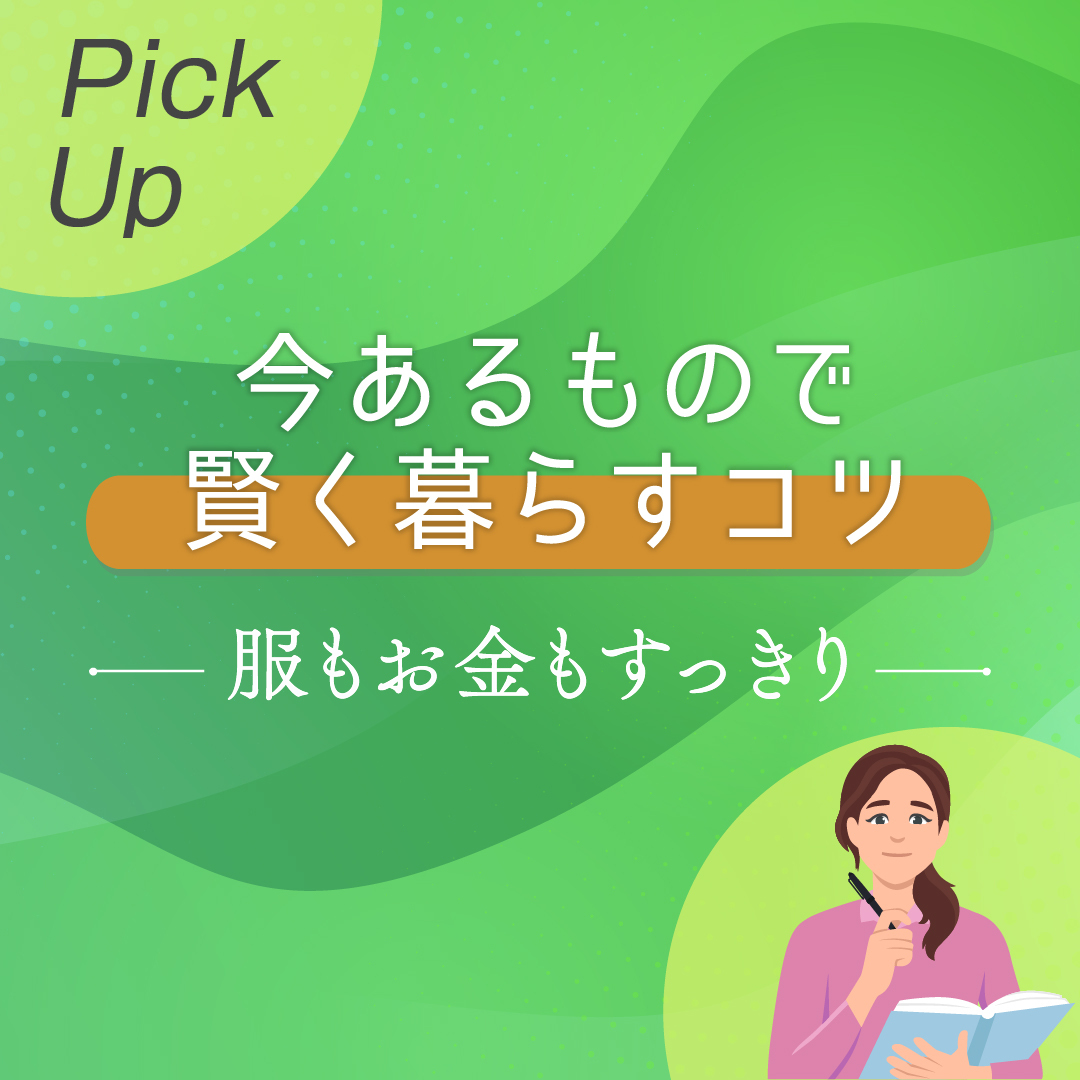50代からの片付けのコツ!
どこから始める?暮らしを豊かにする基本の片付け術
どこから始める?暮らしを豊かにする基本の片付け術
更新日:2022年03月28日
公開日:2021年08月20日

片付けを無理なく楽しむためのコツと事前準備

50~60代の片付けは、第2の人生を楽しむためのきっかけとしてとても有効です。家族を優先して生活してきた家の中を見直し、不要な物を整理してみましょう。
すっきりと片付いた空間に、お気に入りのインテリアを飾り、家具や雑貨を安心・安全で暮らしやすい配置に変えれば、毎日のおうち時間もさらに楽しくなります。
ここでは、片付けを前向きに無理なく楽しむためのコツをご紹介します。
時間や段取りを決めて、無理なく行う
長年暮らしてきた家の中は、物が溢れがち。一度片付け始めると、あちこちに目が行ってしまい、気が付いたら夢中で何時間も経っていたなんてこともあるのではないでしょうか。
スムーズにムダなく片付けるには、対象の場所や物、時間を事前にしっかり計画し、無理なく日数をかけて行いましょう。
1日の作業は1~2時間と決めて、片付けるエリアを細かく分けておくのもおすすめです。
リビングなどのよく使う生活スペース、大きな物置、小さな引き出しの中、どこから始めたら良いのかを明確にし、エリアごとに片付けの順番や段取りを組んでおけば、効率的に作業を進めることができ、片付け疲れを防げます。
ビフォーアフターを写真に収める
片付け開始前・片付け終了後に、部屋の写真を撮っておきましょう。写真で部屋の変化を実感できると、その後のモチベーションにも繋がります。
部屋が散らかってきた時は、アフター写真を見て、元の状態に戻すといった使い方もできます。
片付けが苦手な人や片付け後のイメージが想像できない時は、インテリア雑誌などを参考に、自分の理想とする部屋の写真を切り抜いておくのもおすすめです。最終的な仕上がりイメージを決めておくと、片付けに迷わず、自分のお気に入りの空間を作り出せます。
掃除用具を準備する
片付けに必要な用具は、事前に準備しておくと効率的に作業を進められます。処分する物が多そうなら、ゴミ袋・紐とハサミ・ダンボールなどを多めに準備しておきましょう。ダンボールは、今すぐ使わない物の一時保管にも使用できます。
長期間手を付けていなかった場所は、ホコリやダニなどが溜まっている可能性も。アレルギーなどに気をつけた対策もしておきたいですね。軍手・マスク・掃除機・はたき・雑巾・洗剤などがあると安心です。
キレイを実感しやすく、よく使う場所から片付ける
50~60代の片付けでは、老後も安心して暮らせる「清潔」で「安全」な部屋作りを目指しましょう。まずはリビングやキッチン、洗面台の収納、玄関クローゼットや靴箱など、よく使う物がある場所から取り組むのがおすすめです。
キレイを実感できる片付けの順番
- よく使う物がある場所(リビング・キッチン・洗面台の収納・玄関クローゼットや靴箱)
- 捨てる物が多い場所(物置・クローゼット・使わなくなった子ども部屋)
- 量が多い物(衣類・本)
- 引き出しの中や細かい物(文房具・薬箱)
無理をしない片付けのポイント
- 引き出しや戸棚、収納などは細かくエリア分けをして日程を分ける
- 粗大ごみやリサイクルに出すなら、回収日に合わせて作業計画を立てる
- よく使う物の定位置をあらかじめ決めておく
収納時に気をつけたいポイント
- 消耗品類は、一つ使ったら一つ補充をしてローリングストックで保管する
- 収納グッズは、物の位置を決めてからぴったりのサイズの物を購入する
- 足が引っ掛かり転倒するなどの危険を回避するため、床や廊下に物は置かない
- 生活空間をすっきりさせるため、物は部屋の1か所にまとめて、扉のある収納棚に整理する
出す・分ける・しまうの「片付け3ステップ」

片付けの段取りや準備が済んだら、いよいよ作業開始。「片付け3ステップ」を意識して効率的に作業を行いましょう。
ステップ1:片付けるエリアの物を一気に取り出す
キッチンの引き出しや洗面台の収納など、「今日はここ!」と決めたら、そのエリアの物は一度すべて取り出しましょう。取り出すことで持っている物の全体量が把握でき、仕分けもしやすくなります。
物置などの大きな物を取り出すときは、天気の良い日に広い場所にシートを広げてから取り出していきましょう。
取り出した物は、1か所に集めて並べておきます。この時、同じ種類の物が複数ずつある場合、種類別に分けて並べておくと、収納の際に効率よく作業を進めることができます。
ステップ2:処分する物・取っておく物を見極める
取り出した物の全体量が把握できたら、収納スペースと相談しながら処分する物・取っておく物に仕分けていきます。
ステップ2では、物を減らすことを意識して、以下の3つを基準に仕分けを行います。
- 現在使っている
- 使っていないから処分する
- 使っていないけど取っておきたい
「使える・使えない」で判断してしまうと、不要な物が溜まってしまいます。処分する物の判断に迷った時は、「使う・使わない」で判断しましょう。まだ使えるけれど実際にはもう使わないといった物は、できるだけ処分するように心掛けましょう。
また、春夏秋冬、すべての季節を経過し1年以上使っていない物は、この先も出番がない可能性が高く捨てても良いと判断します。
他にも、溜まってしまいがちな空き箱や紙袋・包装紙は、お気に入りの物など一定数を残し処分します。物がダブっていたり、失くしていた物が出てきたりと、必要量以上の物がある場合も、思い切って処分しましょう。
子どもが使っていた部屋やクローゼットなど、それぞれのエリアで子どもが置いていった不要品は、今後「使う・使わない」で仕分けてみましょう。いつも使う物ではないけれど、残しておきたい物は、使用用途や使用時期別に分け、1か所にまとめて保管しておくと便利です。
ステップ3:使用頻度が高い物から収納する
いつも使う物はすぐ取り出せるよう、腰の高さを目安に収納します。筆記用具などの細かい物や食器などの種類の多い物はカテゴリーごとに仕分けて、物の位置を決めると散らかりにくくなります。
同じカテゴリーでもいつも使う物、たまに使う物を一緒にしておくと、散らかって見えたり、取り出しにくかったりといったデメリットも。頻度別にまとめて収納しましょう。
下駄箱やクローゼットなど夫婦が同じ空間の収納を共有する場合は、段を分ける、エリアを仕切るなどして使う人別に収納をすると、分わかりやすくて便利です。
年に1回、決まった季節だけに登場するという物も意外と多いはず。普段必要でない物は、袋や段ボールなどに仕分けしてラベリングしておきましょう。
フリマアプリや古本募金、寄付などを活用する
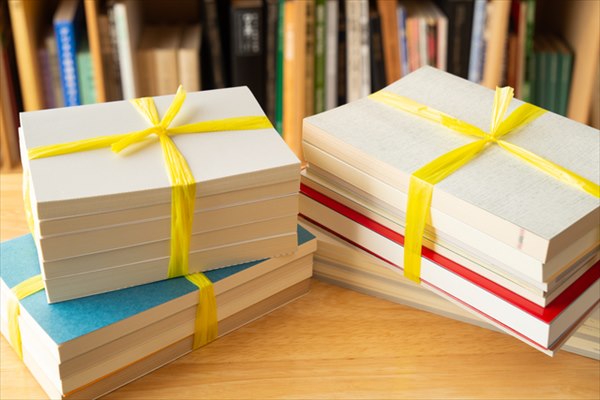
古い本が並ぶ本棚や子どもが使っていた部屋のクローゼットなど、処分する不要品も多く出てきます。不要品に仕分けた物の中でも、思い入れがあって手放しにくいものもあるでしょう。
そんな時は、ただ物を処分するのではなく、不要品を社会貢献やSDGsの取り組みに活用してみてはいかがでしょうか。
※SDGs(エスディージーズ)とは……2030年までにより良い世界を目指すために、制定された持続可能な開発目標。17のゴール・169のターゲットから構成され、貧困やエネルギー、平和や資源、気候変動などの持続可能な国際目標で「誰一人取り残さない」社会の実現を目指している。
具体的にはスマホを使ったフリマアプリに出品すれば、必要な人の元で新たに活用して貰え、自然とSDGsの取り組みに参加できます。出品した商品の売り上げは家計の足しにすることができるのも、「フリマアプリ」の魅力の一つです。
スマホでの手続きが苦手なら、「古本募金」・「寄付」などに活用するのもおすすめです。地域の古本回収ボックスの利用や、郵送などで寄付ができるので、自宅周辺の古本募金回収ボックスや貢献してみたい寄付プロジェクトを調べておくといいですね。
<古本募金>
<寄付>
大切な物や思い出の品の整理整頓

普段あまり使用していない物置やクローゼットの片付けでは、使わないけれど処分もできない「大切な思い出の品」がたくさん出てくるかもしれません。
いつも使う物・年に数回使う物などは、使用目的がはっきりしていて片付けがしやすいですが、そのどちらにも分類されない「大切な物」や「思い出の品」の片付けはどうしたら良いのでしょうか。
ここでは、いつも使う物ではないけれど、処分しない物のおすすめの片付け方法についてご紹介します。
なお、ついつい当時を思い出して作業が進まず時間がかかってしまうので、思い出の品の整理は、家の片付けの最後にやるのが鉄則です。家の中がすっきり片付いた後に、のんびりと整理するのがいいでしょう。
大切な物はしまい込まずにインテリアにする
独身時代から大切にしてきた物、新婚旅行の思い出の品、子育て時代の思い出の品、プレゼントで頂いた大切な物など、使ってはいないけれど捨てられないという物も多いのではないでしょうか。
せっかくお気に入りの物なのに、奥にしまっておくのは、もったいないですね。これまで大切にしまってきた宝物を取り出し、リビングや床の間などの見えるところに飾ってみましょう。
長年しまい込んでいたお気に入りの装飾品をインテリアとして飾れば、当時の思い出が蘇って夫婦の会話もさらに弾むかもしれません。
使っていない高級食器などは、来客時やとっておきの記念日に料理やスイーツを乗せて使用するのおすすめです。大切だからこそ毎日眺めたり使ったりできる場所に収納・配置し、暮らしを豊かにするアイテムとして利用しましょう。
写真や手紙の片付けは生前整理にもなる
なかなか処分できない、写真や手紙などの思い出の品物。自分にしかわからない思い出の手紙や写真などは、片付けをきっかけに生前整理をしておくのもおすすめです。
手紙や年賀状などは、取っておきたい物だけをきれいな箱や収納棚などにしまい、家族が見てもわかるようにラベリングしておきましょう。
アルバムの写真は、あえてすぐに見られるところに収納して、思い出を振り返る時間を楽しむのも良いですね。
子どもたちが独立して静かになった家の中。思い出の詰まった我が家はどこから片付けて良いのかわからないもの。
これから第2の人生を豊かに暮らすため、片付けの基本3ステップを意識して、必要な物・不要な物を見極め、好きな物に囲まれた理想の空間を目指しましょう。
■もっと知りたい■