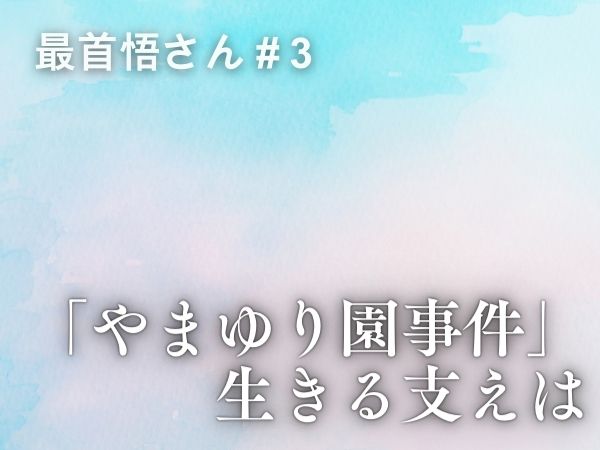「やまゆり園事件」犯人との交流を続けて#1
生物学者・最首悟さん「人は頼り、頼られる存在」
生物学者・最首悟さん「人は頼り、頼られる存在」
更新日:2023年07月24日
公開日:2022年12月30日
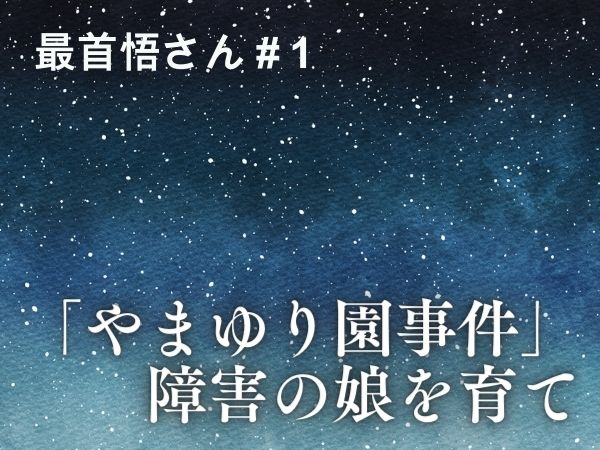
ダウン症、8歳で失明した娘を育てて思うこと

※インタビューは2021年7月に行いました。
私は78歳(取材当時)の妻と44歳(取材当時)の娘、星子(せいこ)と暮らしています。星子はダウン症で知的障害があり、一人では水も食べ物もとれません。盲目で、言葉を話すことも物をつかむこともなく、排せつはオムツでしています。自由に歩けません。作業所に通い、行って寝そべっています。
今でこそ私は障害に関する講演などを行っていますが、私はもともと障害にも子育てにも深い関心があったわけではありません。
学生の延長で助手になりたての頃は東大全共闘運動に参加していました。その後は大学で生物学の助手の仕事を27年間続け、途中からは予備校の講師もしていました。
周囲には重度障害の子がある大学の同僚もおり、筋ジストロフィーの少年の家庭教師をしていたこともあり、自分は障害に向き合うことができていると思っていましたが、まさか自分がその当事者になるとは思っていなかったです。
星子の上には3人の子どもがいますが、子育てにも積極的には関わっていませんでした。
星子が生まれたのは私が40歳のときでした。担当の女性医師に「ダウン症です。ショックを受けるかもしれないから、奥さんには2週間伏せておいた方がいい」とアドバイスされました。
ところが、2週間後に妻に娘がダウン症だと告げたら、それはそれは怒られました。
「母親を何だと思ってるの!能力なんか関係ない。とにかく育てるしかないでしょ!」って。慌てることなく、でんと構えているんですよね。
それで僕も目が覚めて、妻には頭が上がらなくなりました(笑)。生物の世界でも、精子は卵子に引かれていきますが、卵膜のところで侵入を拒否される場合があります。卵が精子を受け入れるかどうかは卵の都合によるものです。
男は女に尽くすしかないと、つくづく思います。
そうして星子との日常が始まりましたが、状況が大きく変わったのは星子が失明したときです。それまで星子は言葉の発達が遅いものの、一人で遊ぶこともできました。私もこれから言葉が出てきて話すようになるだろう、いずれ歩くようになるだろうとどこかで期待していました。
しかし8歳で白内障の手術に失敗して失明すると、星子は一切言葉を発しなくなりました。
娘がダウン症であることが贈り物のように思えた

子育てをしていると「将来が楽しみですね」といったあいさつがよく使われますが、星子が失明して言葉を発しなくなった頃から、私は星子の将来を考えられなくなりました。
将来のためにトイレに行けるようにしては、話せるようにしてはどうか、と人から言われたこともあります。それが親の責任ではないかと言われたこともあります。
でも、排せつ訓練も言語訓練も星子のストレスになるだけのように思い、しませんでした。
振り返ってみると、星子の子育てで大変なことはありませんでした。今強いて言うならば爪を切ることです。
放っておくと鉤爪(かぎづめ)になるので私が切ろうとすると嫌がって血が出る。大変なことと言えばそのくらいです。星子に何かができるように要求することがなかったからでしょう。

思い返せば、最初に産院でダウン症だと言われたときも、強いショックを受けたり打ちひしがれたりといったこともなく、どちらかというと「これで大丈夫」というような不思議な安堵の気持ちが強かった。ダウン症が贈り物のように思えたのです。
私は喘息持ちで、小学校5年生から3年連続で学校を休み、6年生で復帰してからは弟と同じ学級になりました。弟もいやだったろうと思いますが、私も学校では異分子として扱われて友達が一人もおらず、その頃から「人恋しさ」のようなものを抱えていました。
星子が生まれたときはちょうど自分の進路に迷っていた時期でした。
生物学の助手として研究をしていたものの、これでは東大闘争で学生たちが批判していた教授たちと同罪なのではないかと自問自答していました。そこで星子が生まれたことで、デラシネ(根なし草)のように漂っていた自分の人生がつなぎとめられた気がしたのです。
この子の世話をしていれば後ろ指をさされることはない、と。
娘との関係で「人恋しさ」が満たされました

もちろん、楽ではありません。これまで妻とは一度ずつ、「星子がいなきゃね」と口に出したことがあります。星子がいなかったらあちこち旅行にも行けるのに、そんなことを考えながら話したのですが、口にした直後に恥ずかしくなり、お互い言わなくなりました。
「人間」という言葉は元来「じんかん」と読み、人の住む場所を意味しました。2人の人の間、関係のことなのです。つまり人間は、少なくとも2人以上いて、相手がいてこそ自分がいる。「あなた」が先にいて、そこでようやく「私」がいるんです。
星子もそうです。星子は何もできません。「働かざる者食うべからず」で言われるような「働き」はできません。
でも私という人間がいるのは、星子がいるからです。相手がいて、私がいる。何もできない人を支える、そのことが私のレーゾンデートル(存在価値)であり、生きていることへの許可のように感じます。
私は子どもの頃から抱えていた人恋しさが満たされました。子どもはいつか離れていくものですが、星子はずっといます。
もっとも、妻がよく「私が死ねば星子は死ぬわよ」と言います。逆は言いません。
つまり自分が生きていれば星子は大丈夫なんだし、自分が死んだら自分との関係の中の星子は死ぬが、誰かが星子の世話をしてくれると思いこんでいるようです。具体的な将来について考えるのを拒否しているのです。
人は頼り、頼られる存在。甘えてもいい

先述のように子育てでは「将来が楽しみですね」というあいさつがありますが、星子に関しては、例えば暑さが続いて何も食べなくなると将来どころか明日が見えなくなります。
でも、将来がぼやけていくと、相対的に今日が浮上してきます。
今日が穏やかであるようにと願ううちに今日につなぎとめられ、将来のために無理をしたり星子に何かを強制したりしなくていいと感じるのです。星子は音楽を好み、よく笑います。明日もまた、今日のように穏やかであってほしい。
その「明日もまた、今日のごとく」の感覚が、家族に安堵と落ち着きをもたらしてくれます。無理に何かできるようにならなくていい。甘えてもいい。人間は頼り、頼られる存在なんです。
近代社会は、知力と体力があるものを人間と認めて、その上で個人の尊厳を認めてきました。そこで問題になるのは、その知力、体力がない者です。
キリスト教のプロテスタントの「清く貧しく美しく」も、社会のために働く人を基本としています。そもそも働けない人はどのように神のご加護を受ければよいのか。そこが福祉の領域の問題になります。
私は星子という「無用の用」の存在により、人間は自立していなければいけないという呪縛から解放されました。しかし、人間は社会にとって役立つ存在でなければいけないという考え方は根強くあります。
近年の最たる例が、2016年7月、相模原市の神奈川県立障害者施設「津久井やまゆり園」で45人が殺傷された事件でしょう。犯人の植松聖(うえまつ・さとし)青年は「重度・重複障害者を養うには莫大なお金と時間が奪われる」などの自説を述べ、それは私に衝撃を与えました。
事件後、私は植松青年から手紙を受け取り、交流を始めました。次回はそのお話をしましょう。
最首悟(さいしゅ・さとる)さんのプロフィール
1936(昭和11)年、福島県生まれ、千葉県にて育つ。東京大学理学系大学院博士課程中退。同大教養学部助手を経て、予備校教師、和光大学教授を歴任。現在、和光大学名誉教授。『新・明日もまた今日のごとく』(くんぷる刊)など著書多数。
取材・文=大矢詠美(ハルメク編集部)
※この記事は「ハルメク」2021年9~11月号に掲載された「こころのはなし」を再編集しています。
「やまゆり園事件」犯人と交流を続けた生物学者・最首悟さん《全3回》
- 障害のある娘を育てて悟った、頼ること頼られること
- 「自己責任」という言葉にとらわれ過ぎずに生きる
- 「共に居る」愛…「雑然に生きる」という意味