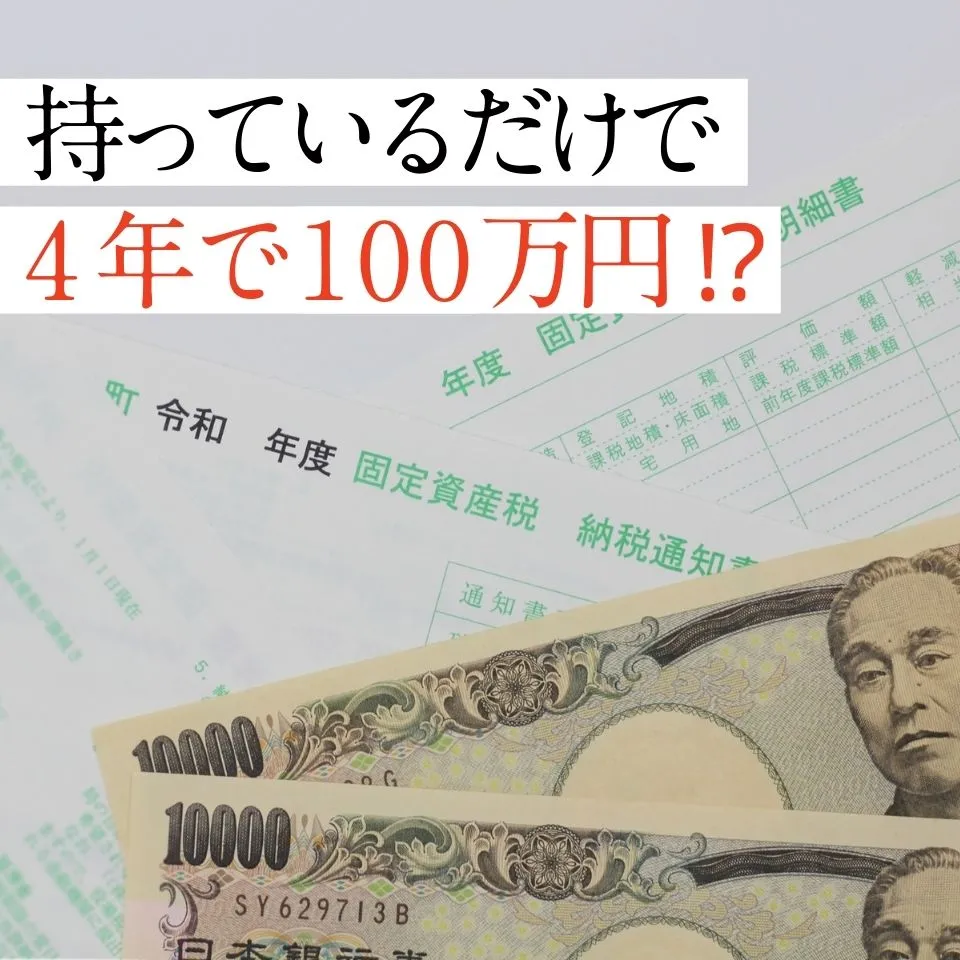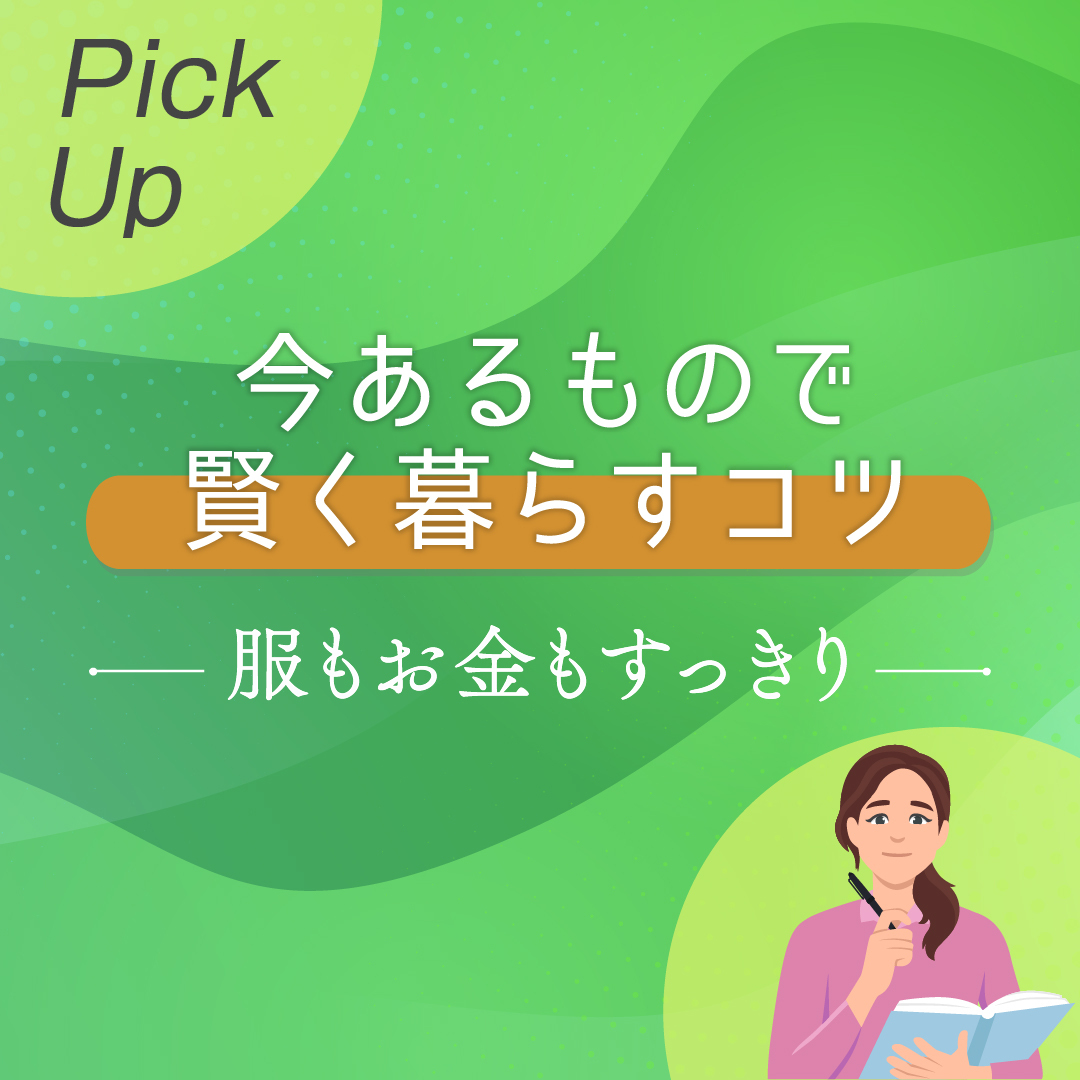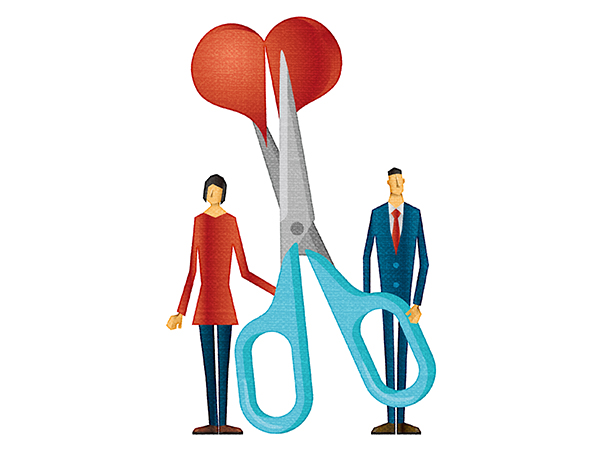コロナ不安による微熱の症状、自律神経失調症に注意
医師に聞くコロナ禍のメンタルヘルス、うつ対策は
医師に聞くコロナ禍のメンタルヘルス、うつ対策は
公開日:2021年02月25日

コロナ禍で自律神経に不調をきたす人が増加
新型コロナウイルスの感染拡大と行動制限などの影響で、私たちの生活は大きく様変わりしました。急激な社会の変化が、メンタルヘルスに与える影響は深刻です。
厚生労働省が2020年9月に15歳以上の10981人(男女)に実施した調査「新型コロナウイルス感染症に係るメンタルヘルスに関する調査」によると、半数程度の人が「神経過敏」「そわそわ、落ち着かない」「気分が落ち込んで、何が起こっても気が晴れない」など何らかの不安を感じ、緊急事態宣言中の2020年4~5月に不安を感じた人は63.9%に達していました。
全体で最も多い不安は「自分や家族の感染」でしたが、20~49歳女性では、「自分や家族の仕事や収入に関する不安」が6割以上と最も目立ち、宿泊・飲食サービス業などコロナの打撃を受けた業種に携わる人は「仕事や収入」に関する不安の割合が高いという特徴がありました。
心療内科医の川村則行さんは、「コロナの影響で、自律神経に不調をきたし不安や気分の落ち込みを訴える“うつ病手前の人“からの相談が増えています。経済的な影響などもあり自殺者が増えていることも見逃せません」と指摘します。
コロナ禍で人間関係や自分の人生に悩む女性たち
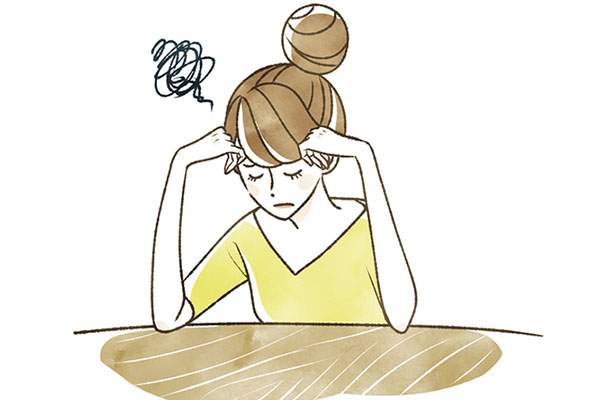
ハルメクWEB編集部にも、不安感や焦燥感、無力感や孤独感を抱える女性たちの声が多く寄せられていますので、少し紹介したいと思います。
54歳の真理子さん(仮名)は、新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、子どもや夫、友人など身近な人たちとの関係について悩むようになったと言います。
「彼らとそつなく付き合っている自分は演技をしている偽りの自分。不安で、時々すべてを投げ出したくなる衝動を覚える」と、心の揺れを明かします。
57歳の和美さん(同)は、「子どもも大きくなり、心の奥の奥にあるやりたいことを少しずつ実現していきたいと思っていた矢先、コロナで人とのつながりが薄くなってしまった。何を求めどの方向に進めばいいか、わからなくなった」と、将来への無力感を語ります。
コロナ禍によって孤立感に苛(さいな)まれているという声も届いています。
3年前に離職し高齢の親を介護中の56歳の由美さん(同)は「いつも自分が社会的に孤立しているような感じがしている。自分は取り残されている」。
自宅でリモートワークを続ける50歳の恵理さん(同)は、「声を出さない、誰とも話をしない日もあり、メンタルが疲れ切っている。心がついていかない」と、コロナ禍の孤独を感じる胸の内を明かします。
コロナ禍で心身の不調を感じたときのチェックリスト

こうしたネガティブな感情について川村さんは、「大半の方が、外出制限や人との関係性が狭くなる中で、考え過ぎの状態、頭を使い過ぎて不安障害に陥っている。息苦しさやめまいや頭痛などが現れる場合は、『自律神経が過敏になっている』と考えてほしい」と話します。
自身の自律神経が過敏になっているかどうかは、パニック発作とパニック障害の2つの診断基準(下記表を参照)でチェックすることができると言います。パニック障害とは突然、「心臓発作ではないか」「気が狂うのではないか」「死んでしまうのではないか」などと思ってしまうほど不安に襲われ苦しくなる疾患のことです。
この病気を取り上げる理由は、診断基準に書かれているさまざまな身体化された症状は、不安によるものであり、その実例を示すために、この診断基準はうってつけだからです。
「明らかにパニック障害と診断できないケースでも、動悸や息苦しさなどがあれば自律神経が乱れているので、自身の健康度を知る指標としてチェックしてみてください。不安が身体化したときの症状がリストアップされています」と川村さんはアドバイスします。
パニック発作の診断基準・チェックリスト
突然激しい恐怖または強烈な不快感が高まり、以下の症状のうち4つ(またはそれ以上)が突然に発現し10分以内にその頂点に達する場合は、パニック発作が起きていると考えられます。
- 動悸、心悸亢進(しんきこうしん)、または心拍数の増加
- 発汗
- 身震い、または震え
- 息切れ感、または息苦しさ
- 窒息感
- 胸痛、または胸部不快感
- 嘔気、または腹部の不快感
- めまい感、ふらつく感じ、頭が軽くなる感じ、または気が遠くなる感じ
- 現実感消失(現実でない感じ)、または離人症状(自分が自分でない感じ)
- コントロールを失うのではないか、または気が狂うのではないかという恐怖
- 死ぬのではないかという恐怖
- 異常感覚(感覚まひ、またはうずき感)
- 冷感、または熱感
高橋三郎、大野裕、染矢俊幸(訳):DSM-Ⅳ-TR精神疾患の分類と診断の手引き.pp171-174、医学書院、東京、2002より引用・一部改変
パニック障害の診断基準・チェックリスト
下記の【パニック障害の診断基準】のAからDの条件をすべて満たしたときには、「自律神経が過敏になっている」以上の状態であり、パニック障害と診断されます。気になる場合は、心療内科や精神科への受診を考えましょう。
A:1 と2 の両方を満たす
- 予期しないパニック発作が繰り返し起こる
- 少なくとも1回の発作の後、1か月以上、以下のうち1つ以上が続いていたこと
- a)もっと発作が起こるのではないかという心配の継続
- b)発作またはその結果がもつ意味(例:コントロールを失う、心臓発作を起こす、"気が狂う")についての心配や恐怖心がある
- c)発作と関連した行動の大きな変化(例:仕事をやめる、運動を避けるなど)
B:自分が制御できない症状や状況が起きてしまった時に、逃げることができない状況や場所で、強く不安や恐怖が生じてしまう広場恐怖症が存在している(広場恐怖を伴うパニック障害の場合)
C:パニック発作は、物質(たとえば乱用薬物、投薬)または一般身体疾患(例えば甲状腺機能亢進症)の直接的な生理学的作用によるものではない
D:パニック発作は、以下のような他の精神疾患ではうまく説明されない。例えば社会恐怖、特定の恐怖症、強迫性障害、外傷後ストレス障害、分離不安障害
セロトニンの減少によって微熱が続く、気分が落ち込む症状が現れる

パニック障害をはじめとする不安障害は、加齢や生活習慣の乱れによってセロトニンと呼ばれる脳の神経伝達物質が減少していることが関係しています。川村さんによれば、セロトニンには気分を安定させたり、不安や恐怖を軽くしたり、食欲をコントロールしたりする働きがあります。そのためセロトニンが減少すると、抑うつや不安、緊張、恐怖やイライラ、悲しい気持ちなどが生じます。
セロトニンが減ることに伴う症状としてよく知られているのは、月経前症候群(PMS)です。PMSは自律神経が高ぶりイライラしますが、アメリカではうつ病の一つと考えられています。セロトニンには食欲をコントロールしたりする働きがありますので、減ると食欲過多が続き体も重く感じ、心身の悪化につながります。
セロトニン不足が、微熱を引き起こすこともあります。「37.5度にいかないまでも夕方や夜に微熱が続く場合は、セロトニンが減ってしまっている可能性があります。セロトニンには発熱中枢を抑える力がありますので、セロトニンが減れば熱が出てくるのです。2020年の5~8月は微熱の症状がある患者さんの来院が多かったです」と川村さんは指摘します。
コロナ禍のメンタルヘルスケアは、セロトニンを増やす生活を

このように脳内のセロトニンを維持していくことは、心身の健康を保つ上で欠かせません。そもそも冬~春先は体内のセロトニンが少なくなり、不安や気分の落ち込みなどの症状も出やすくなるといいます。
川村さんによれば、前述の「パニック発作の診断基準」のチェックのうち、2~3個当てはまった場合は、セロトニンを増やす生活を心がけた方がいいそうです。
【川村流 セロトニンを増やすための暮らし方】
- 外に出て歩く
1日に1回は外に出るように心掛け、歩くことをおすすめします。太陽の光に当たると、脳でセロトニンが作られます。また歩くことや運動は、睡眠リズムを整えるだけでなく、体力をつけ、気分をよくします。外出できない場合は日光が入る明るい部屋で過ごすようにしましょう。情報によっては朝に太陽の光を浴びることが推奨されていますが、日中に太陽光を浴びれば問題ありません。
- 掃除、片付けをする
掃除や片付けを少しするだけでも運動になります。トイレに立ったときがチャンス。いすや布団に戻らないで、10分から20分くらい掃除や片付けの習慣をつけるとよいでしょう。その間、頭を使わず体だけ使うように心掛ければ、心身がすっきりします。
- 眠る前に自分のことを考えず、「お花畑」を描く
睡眠は毎日7~8時間はとるようにします。6時間以上は眠らないと治りが遅くなります。一方で10時間以上眠ると頭痛や体調不良の原因になります。眠る前に自分のことは考えず、頭をからっぽにするか、きれいな景色やお花畑、おいしい料理など、頭の中を「幸せな状態」にして眠るよう努めます。
- 答えが出ないような悩みを捨てる
悩みは、1週間に30分程度考えれば十分です。自分のこれまでの人生を否定したり、将来の人生などの悩みは、意識的に「考えない」ことが重要です。仏教に「諦観」という言葉があるように、現状をあるがままに受け止めつつ「ないものはしょうがない」「自分はこれで十分だ」と考えることが重要です。
- オンラインや電話で友人とおしゃべりをする
一人で悩んでいると視野が狭い自分の考えが、堂々巡りしてしまいます。自分とは違う別の人の視点から普段は考えないような話題を与えられると、強制的に思考がリセットされ脳を刺激し、セロトニンを増やします。他人としゃべると、長引くコロナ禍で自分が衰えていることもわかり、背筋が伸びます。
- お酒は飲まない
ネガティブ思考に陥っているときは、お酒は百害あって一利なし。飲酒はやめるようにしましょう。せっかく生活習慣をよくしても、お酒を飲めば効果が薄れてしまいます。
- 心療内科や精神科を受診する
6までの生活習慣の改善を心掛けても解消しない場合は、心療内科や精神科の受診を考えましょう。向精神薬には、セロトニンを増やす薬もあり1錠飲むだけでも、ぐっすり眠れるようになることがあります。
3~4月、春の心身の不調“木の芽どき”に注意

川村さんは「コロナの感染自体は、ワクチン接種が広まることや、季節が暖かくなっていくにしたがって収まりやすくなります。苦しいのは4月くらいまでかと思います。その時期が来るまで、悩み事を解決しようとするのは先延ばしにしてしまうのがいいかもしれません」と話します。
ただし暖かくなりかけた3~4月頃は、要注意な時期だそうです。この時期は三寒四温という言葉があるように寒い日と温かい日が交互に訪れることで、自律神経が乱れがちになるそうです。
「春は温かくなって冬よりセロトニンは増えますが、一方で昔から“木の芽どき”という時期があるように、季節的に完全に安心することはできません。生活習慣により配慮を重ねつつ、動き出す夏に向けてリズムをつくっていくことが大切です」(川村さん)
コロナ禍での悩みがあるときの相談先

日常的におしゃべりや相談する相手がいなかったり、身近な人に悩みを話しにくかったりする場合には、さまざまなメンタルサポートのある相談窓口があります。つらいときは専門家に話を聞いてもらいましょう。
雇用や家族からのDVなどの問題が悪化しているときは、決して一人で悩まず、下記の相談先に今すぐ相談してください。あなたの状況を理解し、解決策につながるはずです。
新型コロナウイルスの影響による心の悩みについて相談したい
- 新型コロナウイルス関連 SNS心の相談
受付時間:月・火・木・金・日 17時~22時30分(22時まで受付)水 11時~16時30分(16時まで受付)
運営:特定非営利活動法人自殺対策支援センターライフリンク - こころのほっとチャット
受付時間:12時~16時(15時まで受付)
運営:特定非営利活動法人東京メンタルヘルス・スクエア
心の健康について相談したい
- 精神保健福祉センター【電話は、最寄りのセンターにおかけください】
保健師・精神保健福祉士等の専門職が、面接や電話等により、コロナのことが不安で眠れない、子どもの世話でストレスがたまるといったお悩みの相談を受け付けています。
運営:都道府県などの自治体
- 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
職場のメンタルヘルスに関する情報を提供しています。産業カウンセラー等がメール・電話・SNSにより、メンタルヘルス不調、過重労働により体調を崩したと等の相談を受け付けています。
運営:一般社団法人日本産業カウンセラー協会
生きづらさやDVなどを相談したい
- よりそいホットライン
【電話:0120-279-338】【電話:0120-279-226】(岩手・宮城・福島県からの方)
暮らしの悩みごと、悩みを聞いて欲しい、DV・性暴力などの相談をしたい、外国語による相談をしたいときなど。電話、FAX、チャットやSNSに対応しています。
運営:一般社団法人 社会的包摂サポートセンター
- 公益社団法人 日本駆け込み寺
【電話: 03-5291-5720】受付時間 11時-17時
性別、年齢、国、宗教や、被害者、加害者を問わず、DV家庭内暴力、ひきこもり、虐待、多重債務、ストーカー、自殺など、さまざまな問題を抱えたときの相談を受けています。
運営:公益社団法人 日本駆け込み寺
経済的な苦しさを相談したい
- 福祉事務所【電話は、最寄りの事務所におかけください】
- 生活保護制度
「死にたい」「消えてしまいたい」と思ってしまう
- 自殺予防いのちの電話
ナビダイヤル受付センター【電話:0570‐783‐556】受付時間:10時から22時
フリーダイヤル相談【電話:0120‐783‐556】(毎月10日に開設)8時から翌日8時まで
- 全国のいのちの電話
受付時間:HPを確認ください
インターネット相談
運営:一般社団法人日本いのちの電話連盟
- 生きづらびっと
相談時間:月・火・木・金・日 17時〜22時30分(22時まで受付)水 11時〜16時30分(16時まで受付)
生きるのがむなしい、どうしようもない、生活していくのがつらい、しんどい、誰からも必要とされていない、友人がいない、孤独などの気持ちをLINEなどで相談できます。
運営:NPO法人自殺対策支援センターライフリンク - 参考:厚生労働省 心の悩みにおける相談窓口一覧
取材先:川村則行さんのプロフィール

川村則行さん
かわむら・のりゆき。川村総合診療院院長。1961(昭和36)年生まれ。東京大学医学部医学科卒業。同大学院博士課程(細菌学)修了。国立精神・神経センター心身症研究室長などを経て、2011年開業。臨床分子精神医学研究所所長。近著に『うつ病は「田んぼ理論」で治る』(PHP研究所刊)
■もっと知りたい■
- 【医師が解説】50代女性のうつの症状と認知症リスク
- うつを寄せ付けない!考え過ぎないための7つの習慣
- 人生相談:コロナ禍の孤独「心がついていけません」
- 自律神経失調症のセルフチェック&今すぐできる対策
- 自律神経失調症の不調が気になったら運動を始めよう
- 自律神経を整えるアイデア12と自己診断で不調改善
- 精神科医伝授!心の不調を抱えないためのセルフケア
- 疲労感、不調…自律神経を整える方法で快適な生活に
■参考資料
厚生労働省