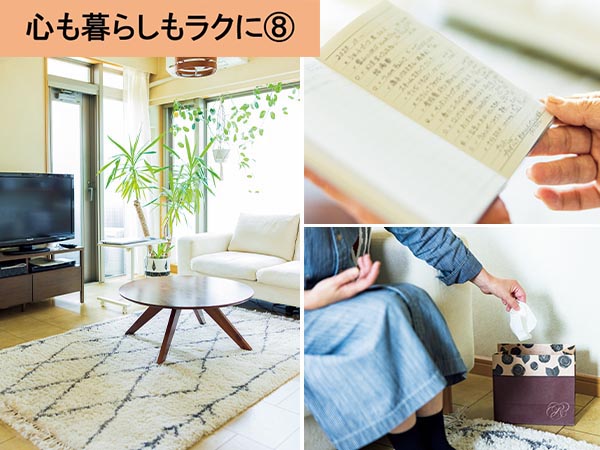公開日:2023年10月15日
素朴な疑問
ちゃぶ台の「ちゃぶ」とは何?語源・由来は?

こんにちは! 好奇心も食欲も旺盛な50代主婦、ハルメク子です。
息子と一緒にテレビでお笑い番組を見ていると、コントでちゃぶ台返しをしていました。
「なんだか懐かしいわー! ちゃぶ台をひっくり返すなんて」と言うと、息子が「あの小さいテーブル、ちゃぶ台っていうの? なんで? 」と不思議そうな顔をしています。
そう言われてみると、当たり前のように呼んでいたけれど、なぜちゃぶ台と呼ばれるようになったのかしら? 早速調べてみましょう!
ちゃぶ台の「ちゃぶ」とは?語源・由来

ちゃぶ台の語源には諸説ありますが、代表的なのは以下の3つの説です。
- 中国で食事の際に使うテーブルを「卓袱(しっぽく・チャフ)」と呼んでいたため
- 中国語で食事をすることを「チャフン」や「ジャブン」と言っていたため
- 大衆西洋料理屋を「チャブ屋」と呼んでいたため
ちゃぶ台の由来には、中国の卓袱料理に使う卓袱台や、中国語で食事を意味する言葉、開国後の大衆西洋料理店で使われていた食卓など、さまざまな説があります。
ちゃぶ台が使われるようになったのは明治時代の中頃のこと。
それまでは家族一人ひとりが専用のお膳を使って食事をしていましたが、明治維新以降、家族全員が向き合って食事をとることが大切だとされるようになったことで、ちゃぶ台が使われるようになっていきました。
つまり、ちゃぶ台はひとつの食卓を家族みんなで囲む西洋の文化と、畳に座って食べる日本の文化が合わさったものなのです。
ちゃぶ台の登場で生まれた食卓の変化

ちゃぶ台の登場によって、食卓には以下のような変化が生まれました。
- 大皿でおかずを出せるようになった
- 食事中に会話ができるようになった
- 食事以外にも利用されるようになった
ちゃぶ台登場以前は、食事の際におかずを家族ひとり分ずつ盛り分けるのが一般的でした。しかしちゃぶ台の上に大皿でおかずを出せるようになったため、主婦は盛り分ける手間が省けるようになりました。
また、昔は許されなかった食事中の会話も、ちゃぶ台の普及によって「食事中はなごやかに楽しい話をする」というマナーに変わっています。
食事や家族団らん以外にも、ちゃぶ台は子どもが勉強する際やお母さんの内職、家計簿をつける際など、さまざまなシーンで利用されるようになりました。
■人気記事はこちら!
参照:三島市郷土資料館

イラスト:飛田冬子