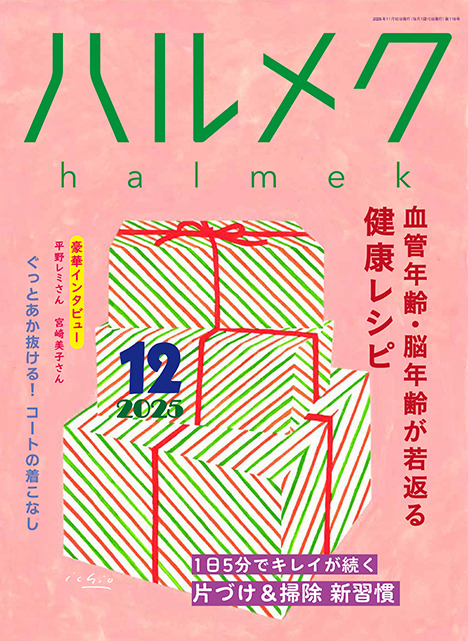更新日:2025年07月06日 公開日:2022年07月05日
素朴な疑問
七夕の食べ物(行事食)や起源・由来って?

こんにちは!好奇心も食欲も旺盛な50代主婦、ハルメク子です。
7月になると気になるのが「七夕」のイベント。今年の7月7日は晴れるでしょうか?過去の記憶では雨の日が多かった印象なので、今年こそ晴れてほしいですね。
ところで、「七夕の行事食」って何を食べるか知っていますか?お正月はおせち、節分は恵方巻、ひな祭りはちらし寿司といったように、四季折々で食べるものがありますが、七夕の食べ物は意外と知られていないかもしれません。そこで、七夕の行事食やその由来について調べてみました!
【七夕とは?】起源や由来を簡単に解説

七夕といえば、短冊に願いを込めて笹に吊るす風習や、彦星と織姫のロマンティックなお話が有名ですよね。このイベントのルーツについて知ると、意外にも奥深い文化が見えてきます。
七夕の起源・歴史
七夕は、中国・韓国から伝わった習わしが日本の風習と融合して形成されたもの。日本では宮中行事として貴族の間で広まり、江戸時代に伝統的な四季の行事「五節句(五節供)」として定められ、庶民の間にも普及していきました。
五節句と行事食
「五節句」とは、日本の四季を彩る重要な日で、それぞれに行事食が定められています。七夕もそのうちの一つです。
- 1月7日(七草の節句):七草粥
- 3月3日(桃の節句):ひなあられ
- 5月5日(端午の節句):ちまき
- 7月7日(七夕の節句):そうめん
- 9月9日(重陽の節句):桃、梨、栗
現在の七夕の日付は新暦の7月7日ですが、昔は旧暦に基づき、現在の暦では8月中旬頃のお盆の時期に行われていました。つまり、七夕はもともとお盆の行事としての側面も持っているのです。
【七夕の食べ物】そうめんの由来とは?

七夕の食べ物としてもっとも有名なのが「そうめん」です。その由来には以下のような説があります。
1.白い糸に見立てて機織りの上達を願った説
織姫が機織りの神様であることから、そうめんを白い糸に見立てて芸事の上達を願ったと言われています。
2.天の川に見立てて願いを込めた説
七夕の夜空に現れる美しい天の川をそうめんに例え、家族の健康や幸せを祈ったという説。
3.赤い糸に見立てて出会いを願う説
赤い糸は運命の結びつきを象徴しています。そうめんをこの糸に見立て、恋愛成就を祈ったと言われています。
昔はそうめんではなく?「索餅」の歴史

実は、七夕の行事食はもともと「そうめん」ではなく、索餅(さくべい/さくへい)というお菓子でした。
索餅はかりんとうに似た形状の甘いお菓子で、「索麺(さくめん)」とも呼ばれていました。この索麺が時代とともに変化し、現代の「そうめん」の形になったと言われています。
日本で索餅が食べられるようになった背景には、中国の伝承が関係しています。昔、中国の7月7日にある子どもが亡くなったことで熱病が流行。その子どもが好きだった索餅をお供えしたことで、病気が収まったとされ、それ以降索餅を食べる風習が広まったそうです。
「そうめんの日」も七夕に制定
ちなみに7月7日は「そうめんの日」でもあります。これは全国乾麺協同組合連合会が1982年(昭和57年)に制定しました。七夕のそうめんの文化は現代にも受け継がれており、家庭でも簡単に楽しめる行事食として人気です。
七夕は中国から伝わった風習が日本の文化と融合し、今の形になった行事です。行事食の「そうめん」は、家庭でも手軽に取り入れられる季節の味覚。
今年の七夕は願いを込めた短冊を吊るしつつ、そうめんを味わい、季節の行事を楽しんでみてはいかがでしょうか?
■人気記事はこちら!
参照:地主神社

イラスト:飛田冬子