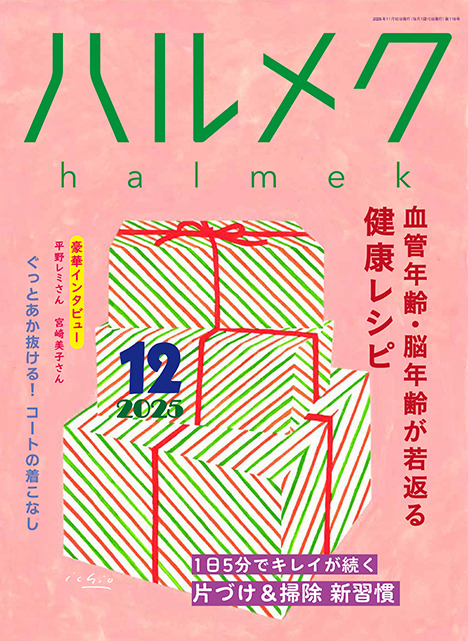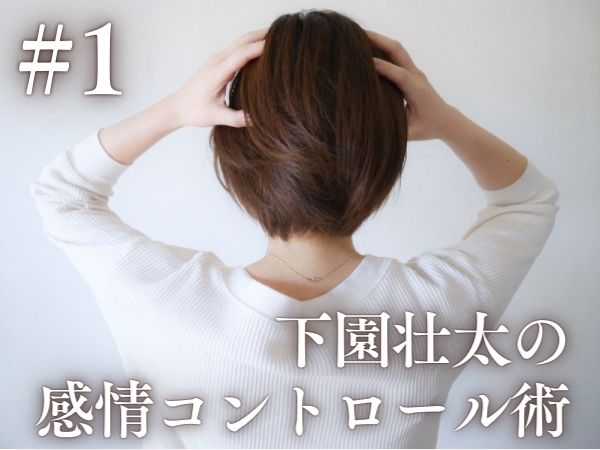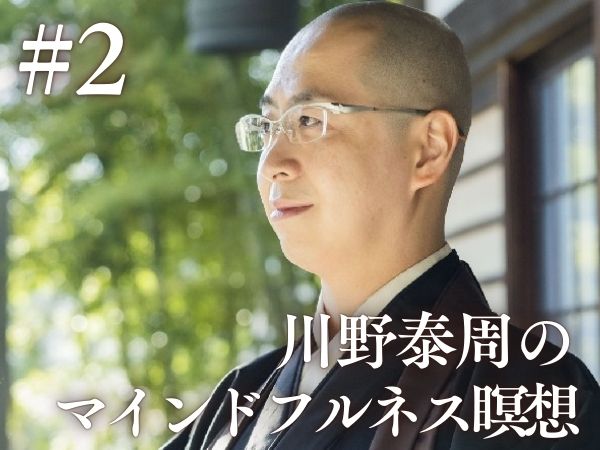怒りや不安…苦しい感情をコントロールする方法#2
下園壮太|負の感情に飲まれない距離の取り方、鎮め方
下園壮太|負の感情に飲まれない距離の取り方、鎮め方
更新日:2023年01月19日
公開日:2020年08月16日

感情は、勢いが強いと理性を乗っ取ってしまう

心は「感情」と「理性」という2つの要素から成り立ち、いずれもあなたを守るために存在していますが、年齢とともに感情をコントロールする力は徐々に落ちてきてしまう、ということを、このシリーズの第1回でお話ししました。
感情は、その勢いが強いときには最も“取り扱い注意”の状態となります。なぜなら、感情は「思考を乗っ取る力」を持っているからです。
感情は、原始時代からずっと、人間が自らを守るために存在してきました。自らの生命が危機を感じたときや、種の存続が危ない、と本能的に感じたときに、感情は事態に素早く対処するために、「体と思考を一体化させる」という働きを発揮します。
もちろん、現代に暮らす私たちは、原始時代とはまったく違う環境の中に生きているのですが、感情は太古の昔のままで反応してしまいます。このために、...