日本科学未来館館長が「今」を語る理由 #1
全盲の館長・浅川智恵子さん「情報から孤立しない社会を、テクノロジーで」
全盲の館長・浅川智恵子さん「情報から孤立しない社会を、テクノロジーで」
公開日:2026年02月06日

浅川智恵子(あさかわ・ちえこ)さんのプロフィール

1958(昭和33)年大阪府生まれ。IBMフェロー(最高位の技術職)、日本科学未来館館長。82年、追手門学院大学英文科卒業。85年、日本IBM東京基礎研究所入社。2004年、東京大学大学院工学系研究科先端学際工学専攻博士課程修了、博士(工学)。
日本語デジタル点字システムや、視覚障害者向けの音声ブラウザ「IBMホームページ・リーダー」など、視覚障害者を支援するアクセシビリティ技術を開発し、19年には日本人女性として初めて全米発明家殿堂入りを果たす。現在は「AIスーツケース」と呼ばれる、視覚障害者のためのナビゲーションロボットの研究開発に取り組んでいる。
ケガが原因で14歳で全盲に。見えない世界が始まった

みなさん初めまして。日本科学未来館館長の浅川智恵子です。
コンピューター科学の研究者として視覚障害者支援のための技術開発を手掛けて、もう40年がたちました。
私自身も、視覚障害者です。実は小さい頃からスポーツが大好きで、特に水泳と陸上が大の得意。小学生の頃の夢は「体育大学に入って、オリンピック選手になること」でした。
しかし11歳のとき、夏の水泳授業の最中にプールの壁に右目の下を強打し、けがを負いました。以降、徐々に右目が見えにくくなり、その手術後に、左目の視力も悪化。14歳のとき、両目の視力を完全に失いました。
大好きだった体育の授業はもちろん見学。黒板も教科書も読めず、授業の内容がわからない。板書の音、同級生の笑い声、誰かが息せき切って走る風の音――それらがただ耳に流れ込んでくる時間を、じっとやり過ごすしかありませんでした。
子どもながらに、「この先の人生を、目が見えない状態でどうやって生きていけばいいんだろう」という焦りと閉塞感に苛(さいな)まれていたように思います。
盲学校に通い「普通に生きたい」と願い続けながら

それでも中学校卒業後に盲学校(視覚特別支援学校)に進学してからは、点字を学び、白杖を持って一人で歩く訓練を重ねて、「視覚障害者として生きていく」という覚悟と術(すべ)を身につけていきました。
盲学校では、視覚障害者でも短距離などの陸上競技が楽しめることを知って、さっそく陸上部に入部。他にも、水泳やスキー、スケートなど、チャレンジできそうなことは何でもやりました。
この頃、私がずっと持ち続けていたのは、「“普通”に生きたい」という願いです。目が見えなくても、好きなスポーツがしたいし、友達と買い物にも行きたい。自分の進路や将来の夢だって、普通はまず「自分がしたいこと」を探しますよね。
同じように、ハンディキャップがあっても「自分がしたいこと」を探して選ぶ自由を諦めたくなかったのです。そんな思いもあって、「自分だからできる仕事を見つけ、自立して生きる」ということが、私の大きな目標になりました。
大学進学。障害ではなく「選んだ道」での試練に直面して
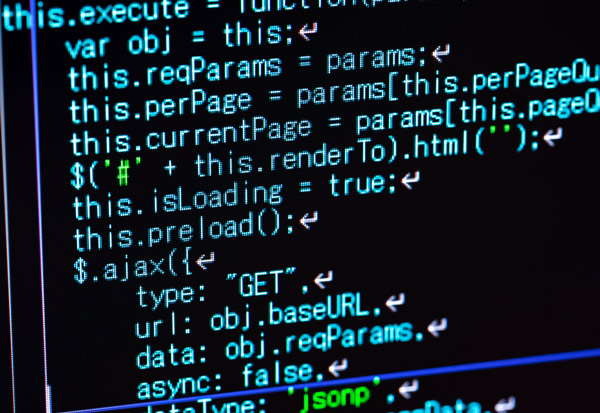
盲学校卒業後は、得意だった英語が生かせればと大学の英文科へ進学。在学中も、翻訳家や通訳、カウンセラーなどさまざまな職種について調べましたが、それぞれに壁があり、将来の進路を決めきれずに過ごしました。
そしていよいよ卒業が迫った頃、ふとテレビで「コンピューターのプログラマーとして働く視覚障害者がいる」という情報を耳にしました。1980年代当時、コンピューターはまだ今のように身近ではない時代です。
「プログラマー」という先進的な響きに惹かれて調べてみると、大阪の社会福祉法人日本ライトハウスで、視覚障害者がプログラミングを学べる情報処理学科があることを知りました。私にとってまったく未知の学問。でもきっと今後伸びていく分野で、今から勉強さえすれば、私でも仕事に就ける。
「これしかない」と確信めいたものを感じ、2年間の職業訓練コースの履修を決めました。このときがコンピューター科学との出合いであり、新たな試練の始まりでもありました。
ビット、バイト、二進法といったコンピューターの基本から、プログラミングの手順など、知識ゼロの状態から身につけるのには非常に苦労しました。中途失明者である私は、点字を素早く読めなかったこともネックになりました。
特に苦しんだのは「オプタコン」という機器の操作です。先端についたカメラで文字を読み込み、それを針の振動に変換する装置で、使用者はその振動を指で感知して文字の形を認識することができます。
出力したプログラムの文字列に誤りがないかを確認するために使うのですが、特に「a」や「c」といった丸まった文字を指先で判別するのが難しく、毎日深夜まで訓練に明け暮れました。
何度「辞めよう」と思ったか知れません。でもこれは、視力を失うという「受けざるを得なかった」試練とは違い、「自ら選んだ道で突き当たった」初めての試練。それなら最後までやり通そう、やるしかない。自分を奮い立たせて毎日を過ごしました。
自動点訳システムの研究員に。人生が拓けてきた

成績はごく普通でしたが、ここから人生が拓けていきました。コースの修了が近づいた頃、たまたま日本IBMで「英語の自動点訳システム」の開発プロジェクトが立ち上がり、英語と点字のプログラミングができる客員研究員の募集がかかったのです。まるで私のために用意されたようなポジションでした。
任期はたった1年で、採用されれば東京で初めての一人暮らし。不安ばかりでしたが、それ以上に「この仕事がしたい」という気持ちが強かったのを覚えています。思い切って応募し採用が決まったときは、自立の一歩を踏み出せた高揚感がありました。
IBMで研究員として働く中では、画期的な最新技術の数々に触れる機会もありました。例えば、ちょうど私が客員研究員として働き始めた年に導入された、音声出力装置。
それまでは、オプタコンで一字一字読み込んで確認する必要があったプログラム内容も、端末が合成音声で読み上げてくれるので、間違いも音ですぐに気付けます。同僚とのメールやチャットも、音声出力を使うことでタイムラグなくスムーズにやり取りをすることができました。
ハンデじゃない、自分にこそできる強みと気付かされた

視覚障害のある当事者として、「テクノロジーがいかに障害を補う力になるか」を実感する日々でした。
その思いをある会議で語ったとき、先輩の一人がかけてくれた言葉があります。
「目の見えないあなただからこそ、ユーザーの気持ちがわかるのですね」
思えば視力を失ってから、「自立しなくては」とがむしゃらにがんばってきたものの、結局はさまざまな場面で周囲の助けを借りなければいけないことに、どこかでずっと「引け目」を感じていました。けれど先輩の言葉は、ハンディキャップとしか考えていなかった障害がむしろ「自分の強みになる」と気付かせてくれました。
たとえ自信がなくても、「自分にこそできること」は誰にでも必ずあって、それを見つけ、どう生かすかを考え抜くことで、道は拓ける――。そう信じられたことが、後々も私の支えになってくれました。
“情報から切り離される孤独”を味わわなくていい世界へ

客員研究員として働いた1年で英語自動点訳システムを形にした私は、成果を認められ、IBMの研究員に正式採用されました。研究者として掲げた目標の一つが、「視覚障害者の情報へのアクセシビリティ(接しやすさ)の向上」です。
かつて私も体験したように、視力を失ったことで周囲の情報から切り離され、途方に暮れることのない社会を、テクノロジーの力で実現したいと考えたのです。
情報のアクセシビリティの向上を目指す上では、1990年代のインターネットの登場は非常に大きなインパクトがありました。
誰もが家にいながら、膨大な情報にアクセスできる点が革新的である一方で、視覚障害者がパソコンを操作して情報を得るには高い壁があり、かえって晴眼(せいがん)者※との情報格差が広がってしまう懸念もありました。
インターネットという新たな情報源の恩恵を、すべての視覚障害者に届けたい――。そのために、私はさまざまなプロジェクトに取り組むことになります。
※視覚障害者の対義語で「視覚に障害のない者」を指す
取材・文=新井理紗(ハルメク編集部)
※この記事は、雑誌「ハルメク」2025年6月号を再編集しています。































































