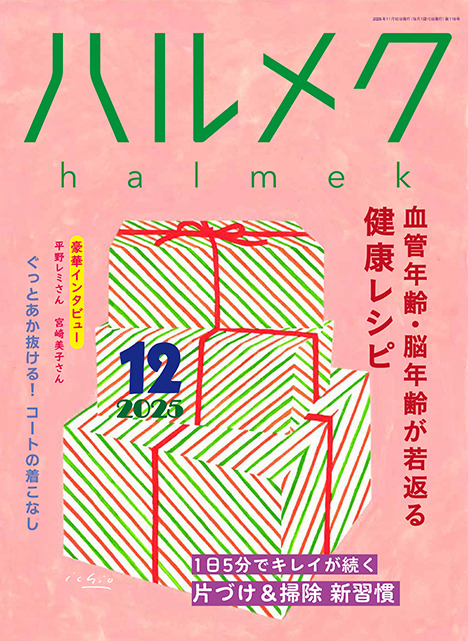公開日:2019年02月11日
素朴な疑問
落語が関東と関西で違うって本当?

この人うまいこと言うなあ、と感心すると、つい「座布団1枚!」と心の中でつぶやいてしまうワタシです。もちろん、ルーツは長寿番組「笑点」の山田君。そういえば笑点に出てくる落語家さんには、どうして関西弁の人がいないのでしょう?
調べてみると、笑点に出演しているメンバーは関東の団体(落語協会、落語芸術協会、円楽一門会)に所属していて、関西の落語家さんは、上方落語協会に所属しているそうです。所属団体が違うから、共演が難しいのかしら。また、関東には、前座見習いから前座、二つ目、真打という昇進制度がありますが、関西は香盤制度によるランク分けです。関東と関西の落語って、もしかして内容も違うのでしょうか。
関東の落語は江戸落語、関西の落語は上方落語と呼ばれています。江戸時代の上方では、お寺や神社の境内、盛り場などで、面白い話や謎かけ話をしてお金を稼ぐ「辻噺(つじばなし)」という大道芸能がありました。(もとになっているのは、お坊さんの説法なんですって!)辻噺には、見物人を集める必要があったため、拍子木や楽器といった小道具(鳴り物など)を使うにぎやかなものだったそうです。落語のルーツはどうやら上方のようです。
やがて、上方から江戸に出てきた塗装職人の鹿野武左衛門(しかのぶざえもん)という人が、江戸でも辻噺をはじめます。しかし、それは屋外ではなく、座敷で披露するという新しいスタイルでした。このスタイルは、「座敷噺(ざしきばなし)」と呼ばれます。富裕層の屋敷に呼ばれるお座敷芸ですから、小道具は使わず、せいぜい扇子や手ぬぐいを活用するくらい。これが、江戸落語の起源だと考えられています。
現在でも、上方落語では見台という小さな机を使います。見台の役目は、拍子木でカンカン! と叩いて音を出すことです。屋外で音を鳴らし、通行人を呼び止めた辻噺の名残と考えられています。
上方落語と江戸落語は、同じ演目でもタイトルや表現が変わることがめずらしくありません。例えば、関東の「酢豆腐」という演目は、関西では「ちりとてちん」、「時そば」は「刻うどん」になるのです。
江戸落語には、笑いの中にも時折ホロリとさせる人情話が含まれています。一方、上方落語には、機転をきかせてトラブルを笑いにするという特徴があります。江戸っ子は、粋でいなせだけれど情にもろい。関西人の商人魂は、腰は低いがシビア。こんな対比が思い浮かぶような気がしませんか?
■人気記事はこちら!
- 耳掃除はしない方がいいって本当?
- 食後30分は、歯を磨かない方がいいって本当?
- 近視の人は老眼になりにくいって本当?
- 魚を食べると頭が良くなるって本当?
- ヒジキは食べ過ぎると体に良くないの?
- 知ってるようで実は知らない?素朴な疑問ランキング ベスト100
参照:文化デジタルライブラリー

イラスト:飛田冬子