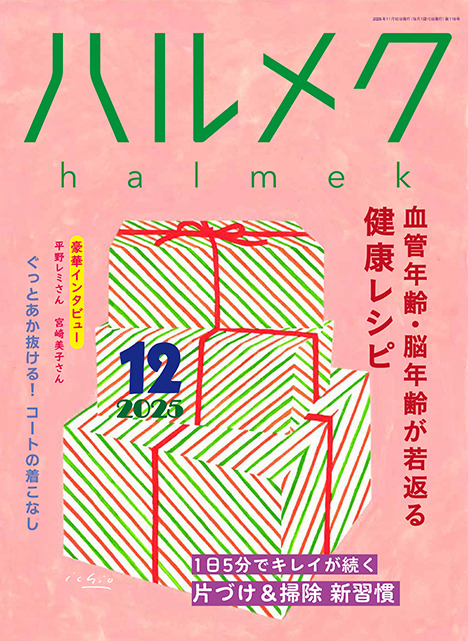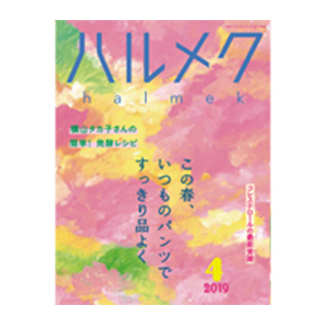人には最後に死ぬという大仕事が残っている
がん患者と向き合い「限りある時間の生き方」を伝える
がん患者と向き合い「限りある時間の生き方」を伝える
更新日:2023年02月10日
公開日:2022年10月27日

樋野興夫(ひの・おきお)さんプロフィール

1954(昭和29)年、島根県生まれ。順天堂大学名誉名誉教授。新渡戸記念中野総合病院、新渡戸稲造記念センター長、恵泉女学園理事長。米国アインシュタイン医科大学、米国フォックスチェイスがんセンター、がん研実験病理部長を経て現職。2008年「がん哲学外来」を設立。『いい覚悟で生きる』(小学館刊)、『がん哲学外来へようこそ』(新潮社刊)他多数。
「がん哲学外来」は約1時間、1回限りの真剣勝負

※インタビューは2009年6月に行いました。
「がん哲学外来」と聞いて、みなさんは何をするところだと思われるでしょうか。
「がん哲学外来」では、治療や診断はしません。僕は白衣を着ないし、カルテも書かない。もちろん必要なら治療に関するアドバイスもしますが、基本的には医者と患者が同じ目線に立ち、患者さんの不安や悩みを聞き、人生について語り合います。
だから「がん哲学外来」は、治療法を提案するセカンドオピニオンでもなければ、心のケアを行うカウンセリングでもない。一人の患者さんと約1時間、1回限りの真剣勝負です。
僕は、普段は顕微鏡をのぞいてがんを研究している病理学者です。もともと島根県の鵜峠(うど)村という日本海に面した小さな無医村に育ち、幼い頃から医者になろうと思っていました。でも、若い頃は出雲(いずも)弁を気にして他人とコミュニケーションをとるのが苦手で、患者を診る臨床ではなく、細胞を相手にする病理の道へ進んだのです。
そして25歳からの10年間、病理解剖でご遺体と向き合う日々を送るうちに「必ず人は死ぬもの」という思いを強く抱くようになりました。

それが2005年、アスベスト(石綿)が原因のがん「中皮腫(ちゅうひしゅ)」の患者が多発して問題になったとき、たまたま中皮腫の検査方法を開発していたことから大学で「アスベスト・中皮腫外来」を立ち上げ、僕も外来に出ることになりました。
中皮腫は非常に治りにくいがんで、治療法も少なく、診断された半年後に亡くなってしまうことも珍しくありません。それでも、多くの患者さんは死ぬまでの毎日を必死で生き、生きる意味や心の安息を求めていました。
そんな患者さんたちと接し、自分にできることは何かと考えたとき、僕の中で浮かんだのが、患者さん自らが人生や死について考えるための支援の場、「がん哲学外来」だったのです。
「これからの時間をどう生きるか」という悩みに寄り添う

再発や転移を繰り返したり、末期のがんで「もう治療法はない」と言われた患者さんは「がん難民」と呼ばれ、社会問題となった2007年、僕は病院から思者さん向けの「がん相談」のあり方についてアドバイスを求められました。...