がん哲学外来・樋野興夫「がんとともに生きる」#1
樋野興夫さん|自分が、家族が「がん」と診断されたら
樋野興夫さん|自分が、家族が「がん」と診断されたら
更新日:2024年09月16日
公開日:2023年08月29日

樋野興夫さんのプロフィール

ひの・おきお 1954(昭和29)年、島根県生まれ。順天堂大学名誉教授。新渡戸記念中野総合病院 新渡戸稲造記念センター長、恵泉女学園理事長。米国アインシュタイン医科大学、米国フォックスチェイスがんセンター、がん研実験病理部部長を経て現職。2008年「がん哲学外来」を設立。著書に『いい覚悟で生きる』(小学館刊)、『がん哲学外来へようこそ』(新潮社刊)他。
病気は個性の一つ。病気であっても病人ではない
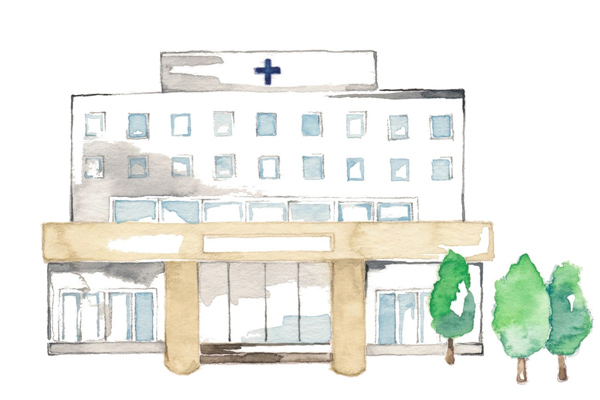
「がん哲学外来」と聞いて、何をイメージされるでしょうか。「がん」と「哲学」、さらには「外来」が結びつく――、正直、訳がわからないですよね(笑)。私は、そういう訳がわからないことをやるのが自分の役割だと思っています。訳がわからないことを本気でやる、それが私の信条です。
私が順天堂大学医学部附属順天堂医院に「がん哲学外来」を開設したのは、2008年1月のこと。54歳のときでした。外来といっても、料金は無料。30分から1時間ほど時間をたっぷりとって患者さんと面談をし、病気そのものではなく、病気にまつわる悩みを解消することを目的としています。
これまでがんで悩む患者や家族、3000人以上の方とお会いして、治療の不安から人間関係の悩みまでさまざまな相談を受けてきました。医師と患者がじっくり「対話する場」をつくるというこの活動は、私の予想をはるかに超えたスピードで全国に広がり、今では活動の場を病院の外にまで広げています。
問題は解決できなくても、悩みや不安は解消できる

まだ、ここがどんな場所か想像できない方もいるでしょう。そこで、ある日の私と女性の患者さんとの対話の様子をご紹介します。
女性「先日、病気を告知されたのですが、田舎の両親にはまだ伝えないようにしようと思っているんです」
――あなた以外に病気だと知っている人はいるんですか?
「いえ。友人にも職場にも言っていません。幸い、まだ体調はそこまで悪くないし、まわりに『病人』として見られるのはなんとなくいやなんです。それに、黙っておいた方が心配かけずに済みますから」
――でも、あなただって不安でしょう。
「はい。でも……正直口に出すのも怖いし、人に話すと一気に気持ちが弱くなってもっと具合が悪くなりそうで」
――あのね、病気になっていても、病人ではないんですよ。
「え? 病人ではない?」
――ええ。病気はあなたの個性の一つ。「自分は病気なのだ。病人なのだ」とあなた自身が思い込んでしまっているんじゃないですか?
「病気は個性……。そう思うと少し気が軽くなります。実は最近、友人といると孤独を感じてつらかったんです。私だけ病気で大変で、これからどうなるんだろう、そう考えると気がふさいで何も楽しめなくて」
――病気であっても今せっかく生きているのに、楽しまなかったらもったいないじゃない。“人生いばらの道、にもかかわらず宴会”ですよ。悩む人は毎日がつらく大変なものだろうけど、心に楽しみを持てる人にはどんな状況でも毎日が宴会になるんだから。
「はい……。まわりが、ではなく私自身が自分を病人として見過ぎて、いろいろ悩んでしまっていたのかもしれません」
こんなふうにお茶を飲みながら何げない雰囲気で話をする、それだけです。でも、最初は思い詰めた暗い顔をしていた患者さんが、話し終わる頃にはみんな表情が明るくなったり、笑顔になって帰って行かれます。
このように、病気そのものや悩みの根本を解決することはできなくても、その人の持っている不安や悩みを気にならないようにする。それが「がん哲学外来」の特徴であり、目的です。
がん哲学外来は「がんと生きる覚悟」を気付かせる場

病理・腫瘍学者として長く顕微鏡の中でがん細胞と向き合ってきた私が、どうして、人間、それもがん患者と向き合う活動を始めたのか。それには大きく二つのきっかけがありました。
一つは、診療とは別の「対話の必要性」を感じたこと。事の発端は05年、アスベスト(石綿)による中皮腫や肺がんなどの健康被害が社会問題になったとき、中皮腫の早期診断法を開発したのがきっかけで、3か月ほど外来に出ることになったのです。
もっとも診療は病理学者にはできないので、私が行ったのは主に時間待ちをしている患者さんへの問診でした。
当時の患者さんの多くは、建築現場や解体現場などで作業していて発病してしまったのですから、不安と同時に怒りも抱えていました。体だけでなく心も蝕まれていたのです。しかも、普段、患者さんは何時間も待たされた後、医師と3分ほど会話して終了です。
それではどうしたって心は満たされないでしょう。そんな医療現場の状況を見て、患者さんの不安やどうしようもない気持ちを何とか受け止めるためには、じっくり対話する必要があるのではないか……そう考えるようになりました。
もう一つは「病気と共存する時代」に入ったということです。高齢化が進み、今は2人に1人ががんになる時代です。がんと聞くと死に直結する病と思いがちでしたが、近年の医療の発達により、そうとはいえなくなりました。
がんを患う人が増える一方で、がんと闘いながら何年も生きる人も少なくはありません。がん患者として生きるのが当たり前の時代。だからこそ、患者と従来の医療とのすき間を埋める医師が必要なのです。
というのも、がん宣告を受けた直後のショックは大変なものです。健康でいることが当たり前と思っていた人ほど、なかなか気持ちの整理がつかないでしょう。そして、治療や手術、再発の心配と、その後も悩みや不安は尽きません。
ですが、がんをきっかけに大いに悩み、考えることは、実は人生を豊かにすることにもつながります。今の自分自身としっかり対話して「患者としての覚悟」をすることが必要なんだ、という気付きを与える存在、それが「がん哲学外来」というわけです。
それに、治療法などとは別に、病気と共存しながらどう生きるかの「心構え」さえできれば、日常生活における「がんの優先位置」を少しずつ下げていくことができるようになります。
病気に悩みはつきもの。でも悩むのは1日1時間で十分

これを読んでいる方の中に、がんを患う方がいたら、こう考えてください。
家にひきこもって病気のことを思い悩む時間は1時間あれば十分です。
さらにはその時間を短くして、歯磨きや皿洗いと同じくらいの感覚にしてしまうといい。日常生活の一部にしていくと、気にならなくなっていきます。がんより魅力を感じるもの、打ち込める新しい対象を見つけるのも手です。
人間は自分のことだけ考えて満足する生き物ではありません。ですから、誰かのために役に立つことができないか、いい縁や人を自分から探しに出掛けていきましょう。そうすると「自分の役割」というものが見えてきます。
自分にはこれができる、という役割を持って人と関わることで、「病気の自分」以外の新たな生きる軸が見えてくるはずです。
次回は、「がん哲学外来」の活動と、他者との対話から生きるヒントを見出す方法についてお話しします。
取材・文/長倉志乃(ハルメク編集部)
この記事は雑誌「ハルメク」2022年9月号「こころのはなし」を再編集しています。
■樋野興夫さんの「がんとともに生きる」をもっと読む■
・#2|がん患者と家族の本当の支え合いとは
・#3|がんになっても後悔を残さないために
「女性のがん」特集アンケート
ハルメクでは、50代から急増する女性のがんについての特集のためアンケートを実施中です。ぜひ、下記応募フォームより「女性のがん」特集のアンケートにご協力ください。






















































