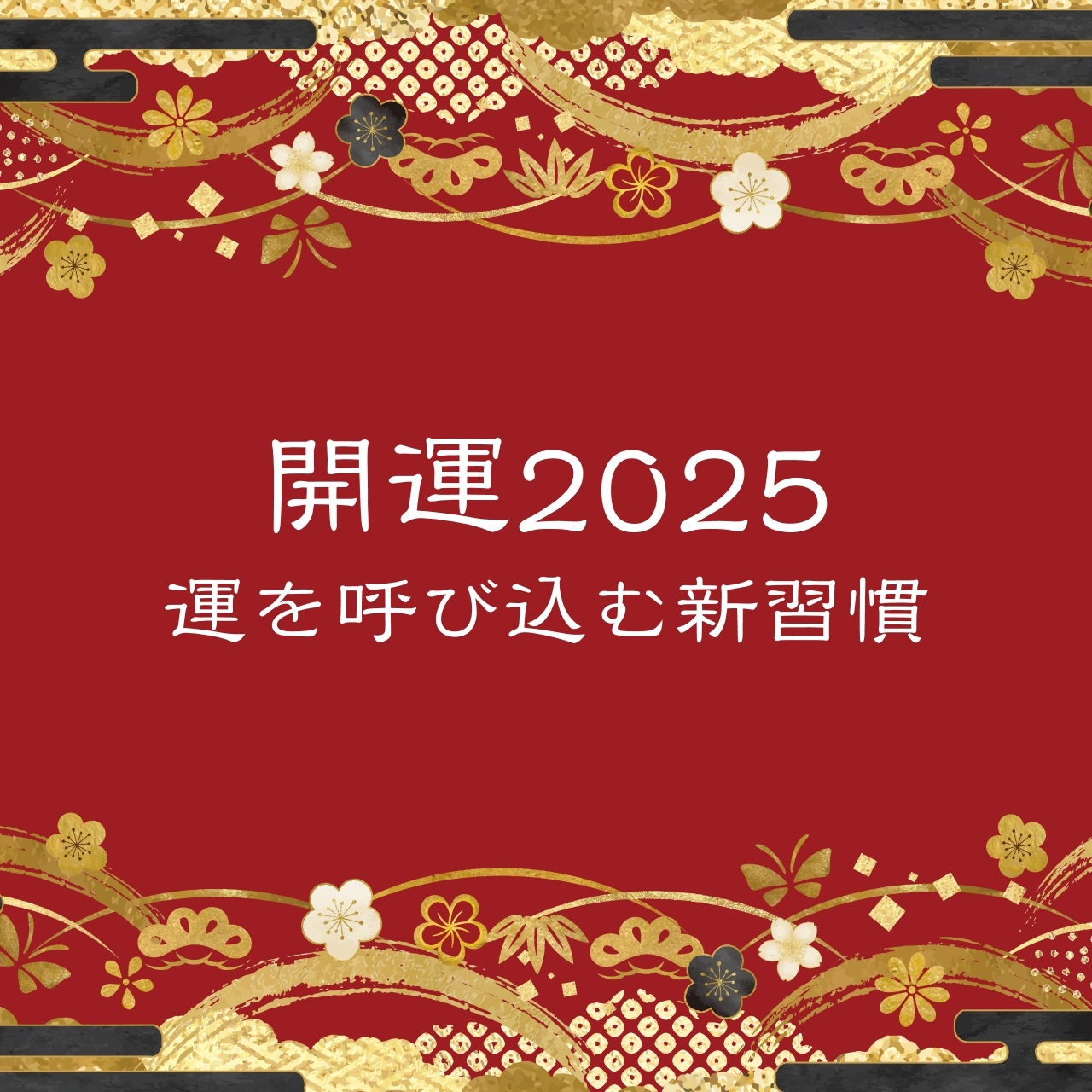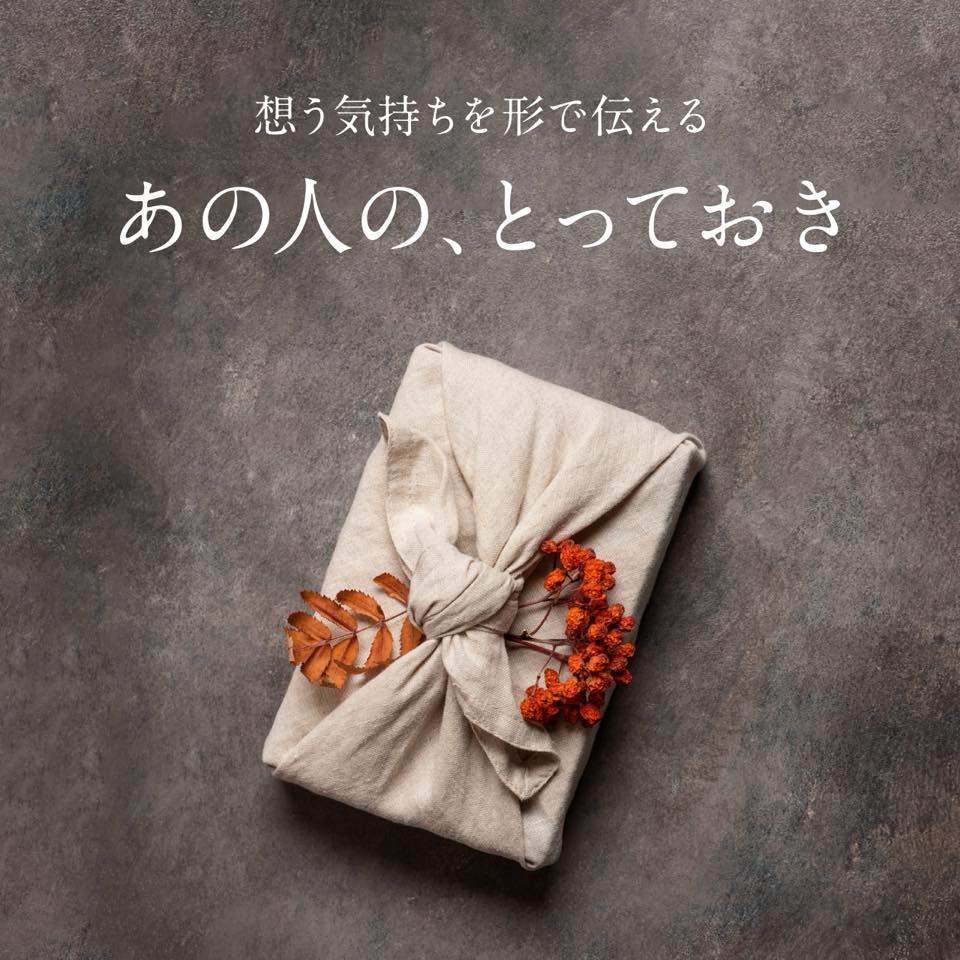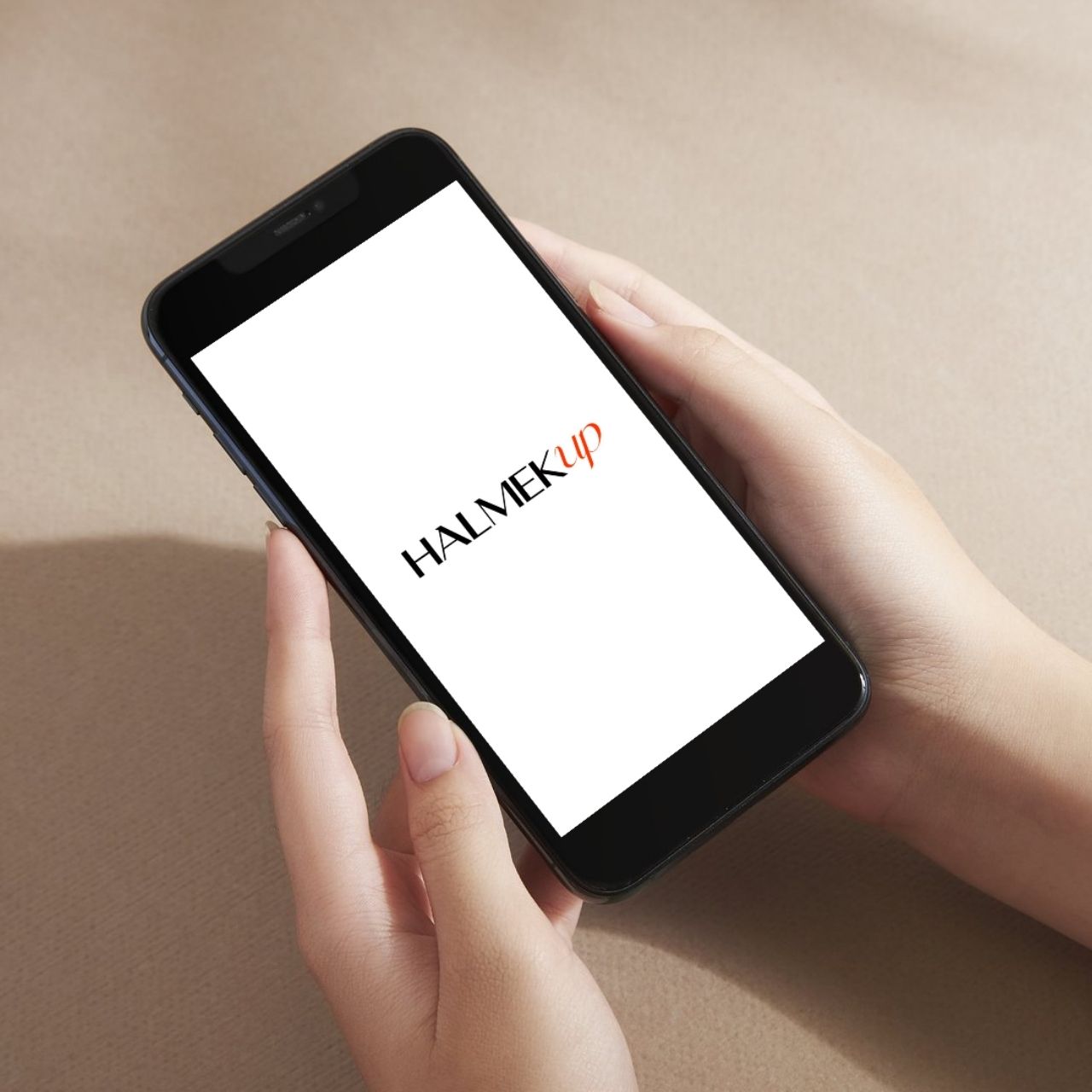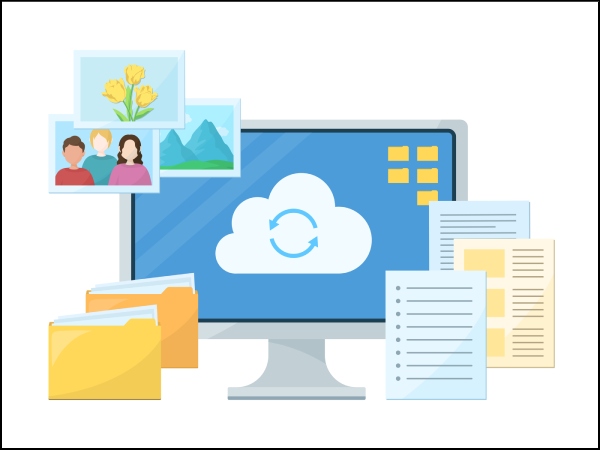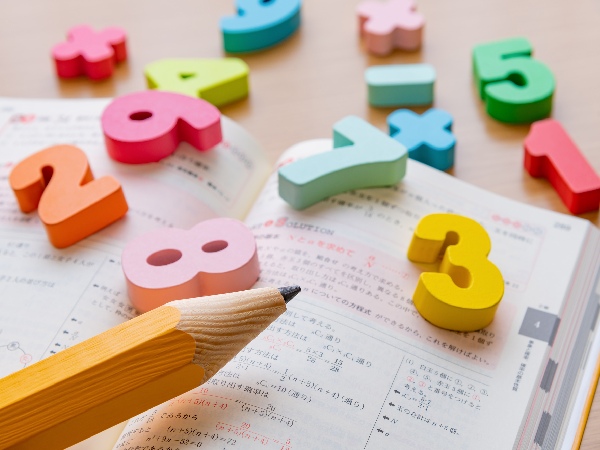今月のおすすめエッセー「庭づくり」富山芳子さん
2024.12.31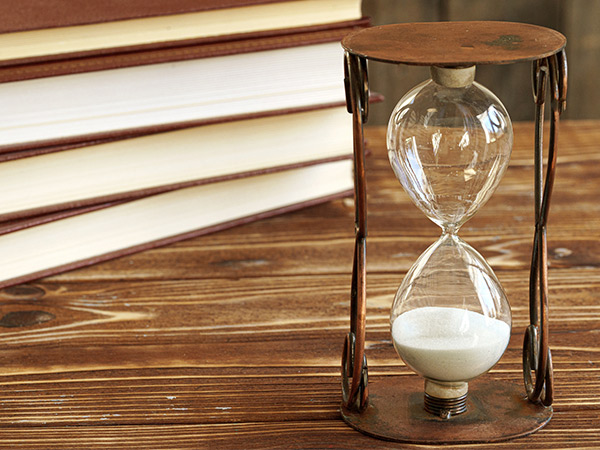
2021年07月12日
通信制 青木奈緖さんのエッセー講座第2期第2回
エッセー作品「時の道筋」宇野百合子さん
「家族」をテーマにしたエッセーの書き方を、エッセイストの青木奈緖さんに教わるハルメクの通信制エッセー講座。参加者の作品から青木さんが選んだエッセーをご紹介します。宇野百合子さんの作品「時の道筋」と青木さんの講評です。
時の道筋
NHKにファミリーヒストリーというテレビ番組がある。
毎回ゲストが、自分のルーツを知り涙ぐむ。母方の生家、父方の生家の土地を訪ね、生業をさぐり、人となりを浮き彫りにする。
ついつい観てしまうのだが、私はそこに何を期待しているのだろう。
そして、自分のルーツを知って、人は何をその心に溢れさせるのだろうか?
そもそも私は何故、家族のエッセイを書きたいなどと思ったのか。
子供の頃の私は、医師をしていた祖父の診察室で、いつも試合に負けては怪我の治療に来るボクサーのアカギさんの話を、疲れきったサラリーマンの話を、うんうんと聴いていた祖父の姿を見ていた。祖母が治療用の蛭を納めに来ていたヘビ屋のおじさんや、大衆酒場のおばさんの人生相談にのっていたことも知っていた。
自分が医師になって患者さんと向き合うようになってからは、夫々の患者さんの人生のドラマの重さに圧倒されそうになりながら、患者さんひとり一人が転ばないように、少しでも役立つ杖になれたら、つっかえ棒になれたらと願ってきたが、気づけば沢山の話を聴いてきた私自身が、人生の晩年へと向かう年齢に達してしまっていた。
私たちは祖父母の代から、ずっと人を支える側で、言わば黒子の役回り。自分のことなど口にすべきではないと思ってきた。けれど今になって黒子の側の物語を、祖父母の姿を、父母の姿を、それに連なる自分の想いを表しておきたくなった。自分が年を取ったということもあるのだろうけれど、自分に至る人々が生きてきたという記憶を刻んでおきたくなったのだ。
人として生きる「いのち」が限られたものであると、ようやくに身に染みて感じられるようになったといえるのかもしれない。頭でわかっていたことでも、腑に落ちてはいなかったということか。
年寄りの感傷と言われてしまえば、それまでだが、年を経なければわからないことは、確かにあるのだ。
とても後悔していることが2つある。
1つは父が晩年、父方の系図を調査依頼して作った時、そんなこと意味があるのかと、軽んじたこと。
もう1つは、成人式を終えた私に、祖母が、その半生を記したノートを見せてくれたのに、読むのが辛くて初めの数ページで返してしまったこと。
私はまだ若すぎてその想いを受け取れなかった。家族の人生は、自分がまだその只中に居る時には、心を開いて受容することが困難だった。今なら、それが出来るだろうと思うし、今、しなければ、永遠に失われてしまうことになるのだろう。
私は多分、祖母や父が試みたように、自分が今ここにいること、自分が生まれてきた「時の道筋」を辿ってみたいのだと思う。日常の風景、出来事の記録だけでない、織り合わされた人の営みに光を当ててみたいのだと思う。
そこから私は自分を知りたいのだ。
青木奈緖さんからひとこと
他の多くの作品が家族の誰かについて書いている中で、この作品は「なぜ自分は家族のエッセーを書くか」という普遍的なテーマを扱っています。
このような根本的な問題と向き合うと、考えているうちにややこしくなって、胸の内に去来するモヤモヤを伝えきれず、諦めてしまうものです。
作品としてはすらすら読めますが、これをまとめるのは容易ではなかったはずです。
「なぜ自分は書きたいと思うのか」、これはみなさんに共通するテーマです。
ぜひ一度お考えになってみてください。
ハルメクの通信制エッセー講座とは?
全国どこでも、自宅でエッセーの書き方を学べる通信制エッセー講座。参加者は毎月1回家族の思い出をエッセーに書き、講師で随筆家の青木奈緖さんから添削やアドバイスを受けます。書いていて疑問に思ったことやお便りを作品と一緒に送り、選ばれると、青木さんが動画で回答してくれるという仕掛け。講座の受講期間は半年間。
現在、第3期の参加者を募集中です(締切は2021年7月26日)。詳しくはこちらをご覧ください。
■エッセー作品一覧■
- 青木奈緖さんが選んだ2つのエッセー#6
- 青木奈緖さんが選んだ3つのエッセー第2期#1
- 青木奈緖さんが選んだ4つのエッセー第2期#2
- エッセー作品「息子に囲碁を教える」岩田實さん
- エッセー作品「時の道筋」宇野百合子さん
- エッセー作品「幸せを運ぶ〈てがみ〉」岡島みさこさん
- エッセー作品「遠回りしたけれど」加藤菜穂子さん