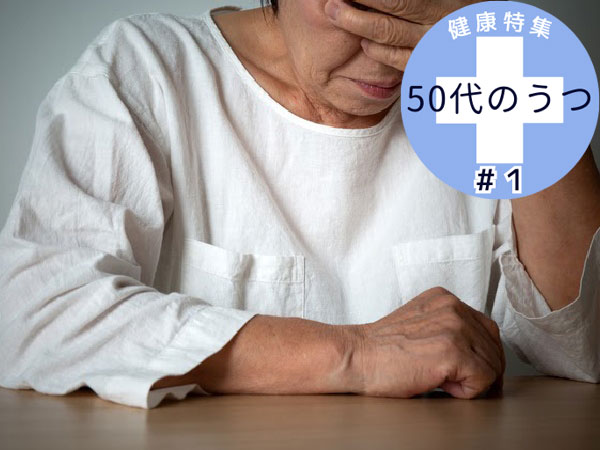もしかしてストレス?限界に達する前に医療機関へ
ストレスが原因で起こる心や体の症状・病気まとめ
ストレスが原因で起こる心や体の症状・病気まとめ
更新日:2023年04月18日
公開日:2022年07月05日

取材先:川村則行さんのプロフィール

かわむら・のりゆき。川村総合診療院院長。1961(昭和36)年生まれ。東京大学医学部医学科卒業。同大学院博士課程(細菌学)修了。国立精神・神経センター心身症研究室長などを経て、2011年開業。臨床分子精神医学研究所所長。近著に『うつ病は「田んぼ理論」で治る』(PHP研究所刊)
そもそもストレスって?

日常的に使っている「ストレス」という言葉ですが、ストレスとは、負荷がかかって歪みが生じた状態のことで、もともとは物理学の分野で使われていた言葉です。
肉体的な負荷や精神的な負荷を「ストレッサー」といい、ストレッサーによる刺激を受けると、人はそれに適応しようとして、心や体にさまざまな反応が起こります。これを「ストレス反応」といいます。
ストレスは適度であれば有益とされていますが、過度なストレスがかかると、心が緊張した状態が続き、心や体に負担や悪影響を与えます。
ストレスの5つの種類
現代はストレス社会と呼ばれ、さまざまなストレスがありますが、大きく5種類に分けられます。
- 職場でのストレス
- 女性特有のストレス
- 老年性ストレス
- 人間関係のストレス
- 受験ストレス
女性の場合、女性ホルモンの分泌量の変動により、ライフステージごとに心にも体にも大きな変化があります。これに伴い、体調が悪くなったり、イライラ、不安感など精神的な不調が現れることも。
また、年を重ねると、健康面での不安、感覚の変化や喪失、定年退職や介護、家族の病気、親や配偶者や兄弟との死別など、心身の負担になるライフイベントによって慢性的なストレスがかかることがあります。
50代以降の女性はストレスがかかりやすい環境にあるため、心や体の変化に気をつけておきましょう。
ストレスを感じると、体にどんな変化が起こる?

ストレスを受けると、自分を守るため、人の体にはさまざまな変化が起こります。
- 情動変化……不安や恐怖、失望、怒りなどの感情が起こる
- 身体変化……息苦しさ、冷や汗、動悸、震えなど体に変化が起こる
- 行動変化……1と2の変化を解消するための行動が現れる(お酒を飲む、タバコを吸う、急いで行動するなど)
ここからは、それぞれの変化について詳しく見ていきましょう。
心理面での変化
ストレスによって起こる心理面での変化や症状には、以下のようなものがあります。
- やる気が出ない
- 気持ちが沈み、憂鬱
- 何をするのも億劫で、何事にも興味が湧かず、楽しめない
- 寂しさや悲しさを感じる
- イライラする、落ち着かない
- 絶望感があり、いなくなりたいと感じる
- 悪い結果ばかり想像してしまう
- 集中できない
- 大事なことを考えるのを避ける
- 自分を責めてしまう など
身体面での変化
ストレスによって起こる身体面での変化や症状には、以下のようなものがあります。
- 体がだるい
- 元気が出ない
- 強い疲労感がある
- 頭が重い感じがする
- 食欲がない、もしくは、食べ過ぎる
- 夜なかなか寝付けない、熟睡した感じがしない、寝過ぎてしまう
- 動悸や息苦しさがある
- 胃腸の調子がよくない
- 冷えやのぼせ
- 肩こり、腰痛 など
行動面での変化
ストレスによって起こる行動面での変化や症状には、以下のようなものがあります。
- アルコールを飲む量やタバコを吸う本数が増える
- 家に閉じこもる
- ずっと寝ている
- 生活リズムや睡眠リズムが乱れる
- 過度に集中する
- 浪費が増える
- ギャンブルにのめり込む
- 何気ないことで怒ったり、運転が乱暴になる など
ストレスが限界に達した時の症状や変化
ストレスは全て悪いのではなく、適度なストレスであれば有益だとされています。しかし、ストレスによる影響を長期間受け続けると、さまざまな問題が生じることも。
ここからは、ストレスが限界に達した時の症状や変化をご紹介します。
自分で気づく変化
「好きなことなのに楽しめない」「疲れているのに眠れない」という症状がほとんど毎日起こり、1週間以上続く場合は、医療機関に早めに相談しましょう。
周囲が気づく変化
ストレスが限界に達していても、自分では変化や症状に気づけないこともあります。周囲が気づく変化には、以下のようなものがあります
- 些細なことで激しく怒る、乱暴になる
- 「自分のことを悪く言っている」と周囲を気にする
- 表情が乏しくなり、口数が減る
- 家に引きこもりがちになる
- 身だしなみなどがだらしなくなる、不潔になる
- 好きなことをしなくなる
- ケガが多くなる
- 仕事の遅刻や早退が多くなる、突然休む、付き合いを避ける など
どのような変化が起こるかは人によって異なりますが、家族や職場の同僚、知人・友人でこのような変化が見られた場合は、ストレスの影響が考えられるでしょう。
ストレスの影響で起こる病気・症状

ここからは、ストレスの影響で起こる病気や具体的な症状をご紹介します。
息苦しさ、喉がつかえる感じ、閉塞感(ストレスボール)
ストレスの影響によって、「息苦しい」「胸がつかえるような感じがある」「閉塞感がある」など、喉から前胸部にかけて違和感が生じることがあります。
胸や喉がつかえるような症状は、ストレスによって起こる症状でよく見られるもので、「ストレスボール」や「ストレス球」などと呼ばれます。痰が絡むような感じがしたり、咳がみられることもあるようです。
ストレスボールは、さまざまなストレス性疾患に見られる症状ですが、症状への不安や不快感が強い場合は「咽喉頭食道異常感症」「咽喉頭神経症」「食道神経症」と診断されることもあります。
めまい
めまいには、体がふわふわしたように感じる「浮動性めまい」と、目が回るようなめまい「回転性めまい」があり、浮動性めまいはストレスが影響していることが多いとされています。
回転性めまいの場合は、メニエール病や良性発作性頭位めまい症の可能性が考えられます。
頭痛
頭痛は、ストレスによって体に現れる代表的な症状の一つです。急に強く痛む「片頭痛」、重たい痛みがだらだら続く「緊張型頭痛」のいずれも、ストレスが関係しています。
アレルギー・免疫異常
ストレスは免疫の異常につながり、免疫力の低下を引き起こすことがあります。また、アトピー性皮膚炎や気管支喘息など、アレルギーの疾患が起こりやすくなったり、悪化につながったりすることもあります。
蕁麻疹
蕁麻疹はアレルギーによって起こるイメージがあるかもしれませんが、ストレスも大きく影響しています。ストレスによってホルモンや自律神経が乱れることで、蕁麻疹として体に現れます。
ストレスが原因で起こる蕁麻疹は繰り返し現れることが多いとされ、総合的な治療を行う場合は皮膚科だけではなく、心療内科や精神科を受診した方がいい場合もあります。
胃の痛み・下痢・便秘
ストレスがかかり続けることで強い緊張状態になると、胃腸に異常が起こり、胃の痛み、逆流性食道炎、下痢、便秘の原因になります。
胃酸の過剰分泌が起こると、急性胃腸炎などにつながることもあるようです。ウイルスに感染しやすくなるため、胃腸炎の症状が見られる場合は早めに病院に足を運ぶことが大切です。
腰痛・背中の痛み
ストレスは腰痛や背中の痛みの原因になります。椎間板ヘルニアやぎっくり腰などの問題がないのに腰や背中の痛みが続く場合は、ストレスが原因の可能性も考えられるでしょう。
燃えつき症候群
燃え尽き症候群はバーンアウトシンドローム(burnout syndrome)とも呼ばれ、それまで何かに没頭していた人が、過剰なストレスや疲労によって燃え尽きたように意欲を失ってしまうことを指します。
仕事が手につかなくなる、対人関係を避ける、朝起きられない、職場に行きたくない、イライラが蓄積する、お酒の量が増えるなどの症状が見られます。
突発性難聴
突発性難聴が起こる原因ははっきりとはわかっていないものの、ストレスを感じているときに起こりやすいといわれています。
不眠症
不眠症とは、入眠障害・中途覚醒・早朝覚醒・熟眠障害など、睡眠にかかわる問題が1か月以上続き、意欲・食欲・集中力が低下する、倦怠感があるなどの不調が起こる症状を指します。
不眠症になると、眠れないことがストレスになることも多く、悪循環につながりやすいです。
心身症
心身症とは、ストレスの影響によって起こる体の病気のこと。一つの病気の名前ではなく、全身の至るところに症状が現れることが特徴です。
人それぞれ、心身症の症状が現れる器官は異なりますが、有力な説としては「本人の一番弱い部分に症状が現れる」といわれています。
不安障害(神経症)
不安障害は、かつては神経症と呼ばれていた病気で、ストレスの影響で心身にさまざまな症状が起こる疾患です。不安障害は悩みや葛藤などの原因があることが特徴で、原因が解消されれば症状がよくなることが多いとされています。
気分障害(うつ病、躁うつ病)
気分障害といわれるうつ病や躁うつ病は、ストレスでなる病気の中でも代表的なものです。
悲観的、憂鬱、物悲しいなど抑うつ気分、意欲低下などの精神症状が現れます。また、食欲不振や睡眠障害なども多くの人に見られます。
更年期障害
更年期は一般的に40代半ば~50代半ばの10年間を指し、女性ホルモンであるエストロゲンの激減によって、女性の体や心に大きな変化が起こります。
これによって起こるさまざまな症状を更年期症状といいますが、日常生活に支障が出るほど症状が強く出ている場合は「更年期障害」と呼ばれます。
ストレスの影響を受けると、更年期障害が見られやすくなります。
高血圧、心臓病
ストレスを受けると、自律神経である交感神経が高まり、脈が速くなって高血圧になります。このとき、心臓に負担がかかるため、心不全発症の危険性が上昇するなど心臓病のリスクが高まります。
その他、多くの病気に影響を与える
この他にも、ストレスが関連していると考えられている疾患はいくつもあります。
- 過喚起症候群
- 胃・十二指腸潰瘍
- 心因性嘔吐
- 潰瘍性大腸炎
- 過敏性腸症候群
- 糖尿病
- 単純性肥満症
- 円形脱毛症
- 慢性関節リウマチ
- 夜尿症
- 心因性インポテンス
- メニエール病
- 眼精疲労
- 本態性眼瞼痙攣
- 顎関節症 など
おすすめのストレス解消法

ストレスをため込まないためにも、積極的にストレス解消を行っていきましょう。
- 無理なく続けられる運動を行う
- しっかり休養する
- 睡眠の質を高める
- 食事のバランスを整える など
上記のような方法の他にも、自分の好きな趣味を行うなどもおすすめです。
気になるストレス症状は早めの対処を
ストレスを受け続けると、心や体にさまざまな症状や変化が現れます。
自分で自覚できるほどストレスの影響で心身に症状が現れている場合、無理をすれば体を壊してしまう可能性も。ストレスを感じている場合は気分転換をする、休息を取るなど、セルフケアを行い、自分を労ってあげましょう。
ストレスは慢性化すると病気につながる可能性もあるため、つらい症状が続く場合は早めに病院に行って医師に相談することが大切です。
■もっと知りたい■