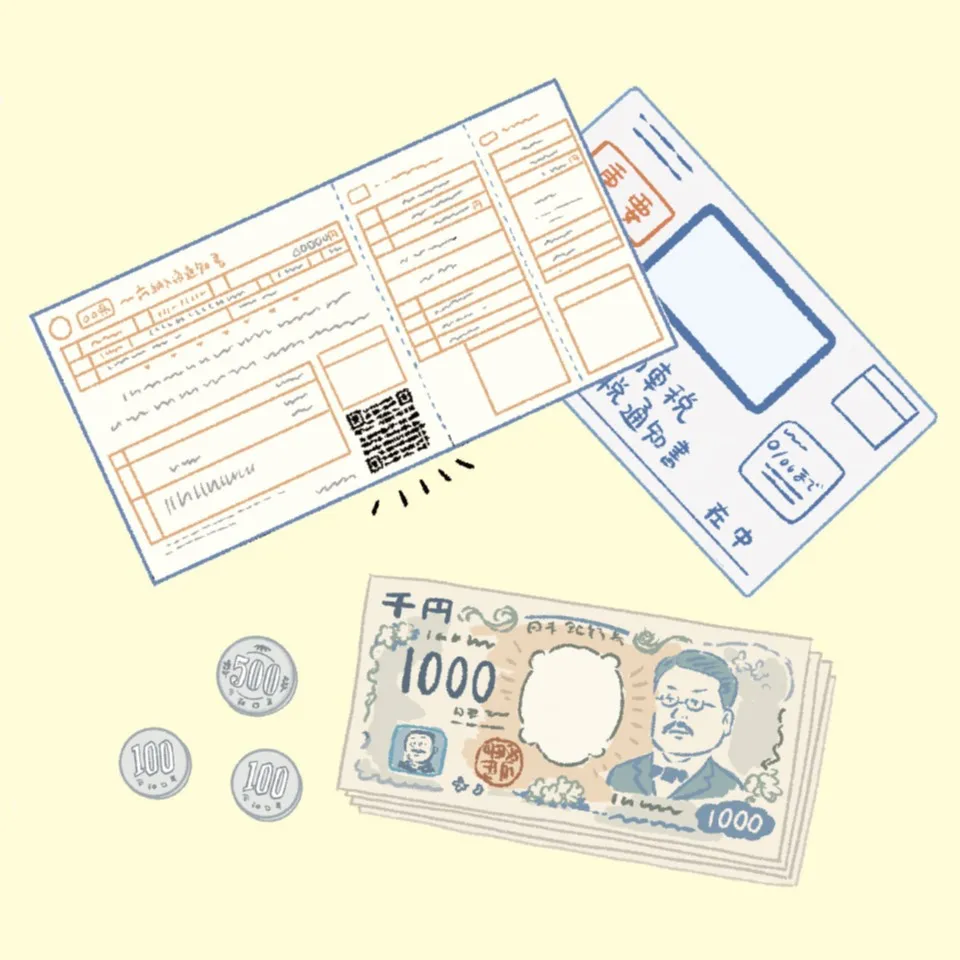
税公金をスマホで払うと…
税公金の支払いはスマホからが圧倒的にラク&お得!「ゆうちょ銀行」では抽選で毎月1万名様に1,000円が当たるキャンペーン実施中!

公開日:2022年02月21日
頼れる人がいない!みなさんどうしているの?
子どものいない夫婦は、自分たちの死後事務手続きについて生前に託す人を決め、希望を伝えておくことが大事です。また、のこされた配偶者のために、遺言書も慎重に作成する必要があります。その際のポイントを押さえておきましょう。

終活に関する記事などを見ると、子どもがいることを前提に書かれたものが少なくありません。そのため、子どもがいない夫婦やおひとりさまは、終活の進め方でいろいろと悩んでしまうようです。ハルメク読者からもこのような声が。
「自分の死後のことを考えます。私たちのように子どもがいない方々は誰に相談しているのでしょうか。お葬式も簡素にしたいと思っていますが、お付き合いもあり、周りからあれこれ言われそうで悩んでいます」(夫と二人暮らしで子どもがいない坂口さん<仮名・69歳>)。
「終活の記事は参考になるのですが、一人暮らし(子どもなし、兄妹なし、話せる人なし)の人の情報が少ないです。もう少し細やかな情報が載っていたらいいのに」(おひとりさまの井上さん<仮名・65歳>)。
また、「夫婦仲は良好だけれど、夫も私も兄弟や甥姪とは疎遠」という子どもがいない夫婦の橋本さん<仮名・57歳>からは、「終活や死後の手続きで、兄弟や甥姪に頼らないためにはどうすればいいのでしょう」という質問が届きました。
このように、子どもがいない夫婦やおひとりさまの終活に関するお悩みは深いようです。今回はそういった方々にスポットを当てた終活の考え方を見ていきましょう。

子どもがいない夫婦やおひとりさまがやるべき終活には、大きく分けて「相続対策」と「死後事務の相談先を決めておくこと」の二つがあります。それぞれ気を付けるべきポイントはなんでしょうか。
子どもがいない夫婦で、例えば夫に先立たれた場合、相続人は誰になるのでしょう。実は、妻がすべて相続するわけではないのです。
夫の両親が生きている場合には、配偶者である妻と、夫の両親(祖父母)が相続人になります。法定相続分(民法で定められた相続割合)は、妻が2/3、夫の両親(祖父母)が1/3です。
夫の両親(祖父母)が他界している場合は、妻と、夫の兄弟姉妹が相続人です。夫の兄弟姉妹に死亡している人がいる場合には、その子ども(甥姪)が代襲相続することになります。この場合の法定相続分は、妻が3/4、夫の兄弟姉妹(甥姪)が1/4です。
妻だけが相続人となるのは、夫の両親(祖父母)が他界し、夫の兄弟姉妹や甥姪がいない場合のみになります。
上記を踏まえた上で、相続対策をしないまま夫に先立たれてしまうと、のこされた妻に起こる不都合やトラブルとして、預貯金・不動産など財産の名義問題があります。
相続人全員による遺産分割協議を経なければ、夫名義の預貯金を解約することや、住まいを妻名義に変更することができなくなります。原則として相続人全員の同意を得て初めて解約や名義変更ができるのです。
2018年7月の民法等の改正により、遺産分割の終了前であっても、自分の法定相続の範囲内で1金融機関につき150万円を上限に預貯金の引き出しができるようになりましたが、やはり夫の資産を妻の意思だけで自由に動かせないのは、不便なこともあるかもしれません。
そこで生前に準備したいのが遺言書です。有効な遺言書がある場合には、基本的に遺言に沿って手続きが行われます。夫の亡き後に妻が財産をスムーズに引き継ぐためには、生前に遺言書を作成することが必須だといえるでしょう。

遺言書を作成する際には、以下の点に気を付けることが大切です。
■夫婦それぞれで遺言書は用意する必要がある
まず、同じ書面で二人の遺言書を作成しないこと。二人の遺言書は無効になります。夫婦がそれぞれ遺言書を作成する必要があるのです。
■遺留分を侵害しないように財産を分ける
また、夫の遺言書に「財産はすべて妻に相続させる」と書かれていても、夫の両親が存命の場合には、遺留分(法律で最低限保障されている遺産の取得分)を侵害しているなどの理由で本人(夫)の希望が叶えられない場合があります。
円満な相続のためには、遺言書を作成する際に、夫と妻の双方の家族と話し合いをすることが大切です。妻(夫の場合も同様)に確実に全財産を残したい場合には、相続開始前に妻以外の相続人に遺留分放棄をしてもらうという手段もあります。
遺留分の放棄は口頭ではなく、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
■遺言書が無効にならないように正しく作成する
一方、遺言書の作成には、満たすべき要件が厳格に定められています。相続発生後のトラブルを回避するためには、遺言書の作成は専門家に相談することが最善策といえるでしょう。さらに、遺言の内容を実現するには、遺言執行者を指定することも必要です。
「どうやって専門家を探せばいいのかわからない」という場合は、信託銀行の「遺言信託」などを利用する方法もあります。「遺言信託」なら、遺言書の作成から執行の手続きまで、すべて任せることができます。

子どものいない夫婦やおひとりさまは、相続だけでなく、煩雑な死後の事務手続きを誰に依頼するのかも生前に決めておくことが大切です。その際には、どのような手続きを、どのように行ってほしいのか、希望を伝えておく必要もあります。
とはいえ、これは簡単に決められることではないでしょう。日頃、かなり親しくしていない限り、親戚や友人に依頼するのは憚(はばか)られます。もし、近くに頼れる人がいないのならば、第三者に委託するという方法もあります。
三井住友信託銀行の「おひとりさま信託」なら、死後事務を代行する一般社団法人を紹介してもらえます。訃報連絡から葬儀やお墓の手配、家財整理、公共サービスやクレジットカードの解約、ペットの引き渡しなど、煩雑な死後事務手続きをまとめて任せることができます。
子なし夫婦やおひとりさまが漫然と感じている終活の不安も、こういったサービスを利用することで解消されるかもしれません。終活の一つの選択肢として検討してはいかがでしょうか。
■記事監修:勝猛一さん
かつ たけひと 司法書士 「勝司法書士法人」代表。相続・遺言サポートオフィス「ゆずりは」運営他。遺言、相続など終活のプロフェッショナル。YouTubeチャンネル「勝 司法書士法人勝猛一」で終活情報を発信しています。著書に、『事例でわかる 任意後見の実務』(日本加除出版)
■もっと知りたい■
■記事協力=三井住友信託銀行
驚きの軽さ&使いやすさ!
1本で7つの効果ハルメクが厳選した選りすぐりの商品