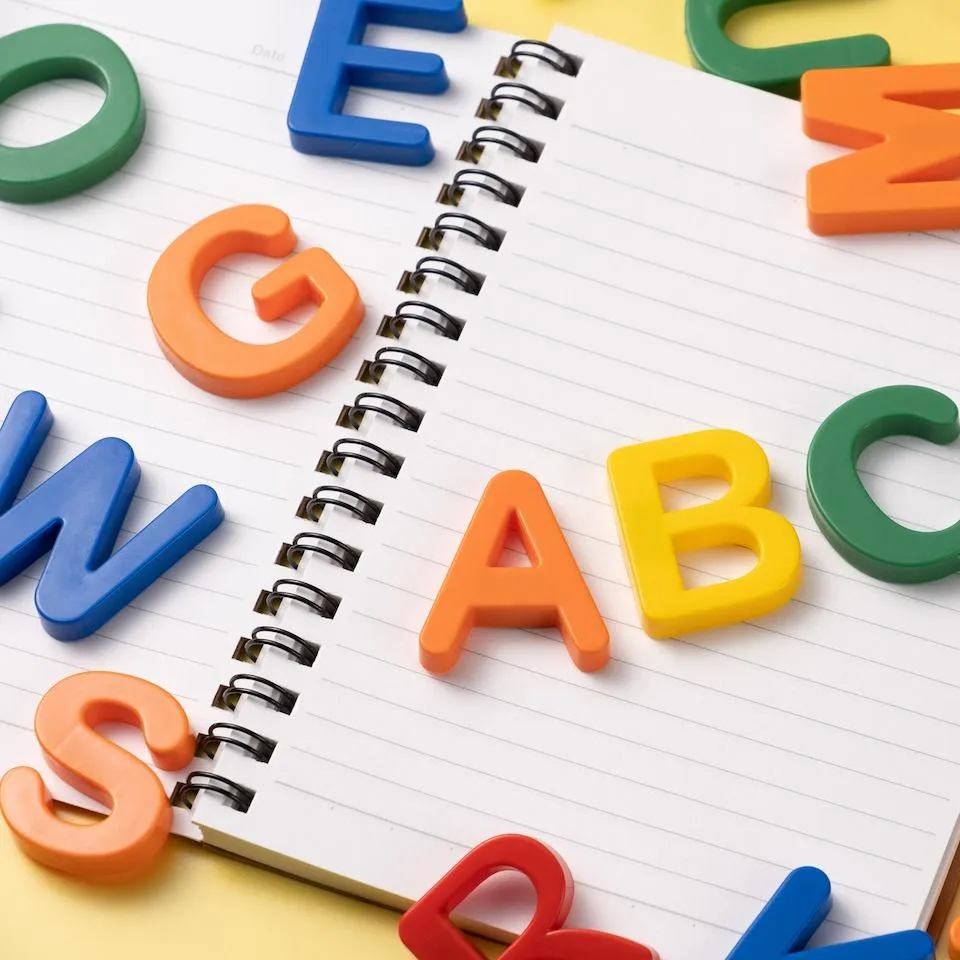
毎日5分で英語力アップ!
忙しい人・飽き性なひとも大丈夫!毎日5分、英語学習を習慣化させる簡単な方法をご紹介♪
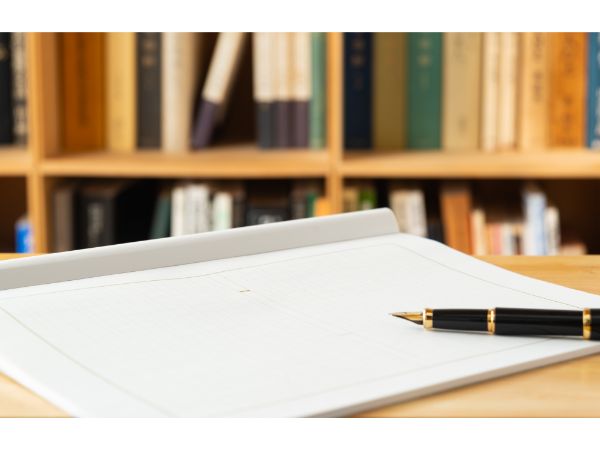
更新日:2025年02月27日 公開日:2021年12月29日
初心者の方必見!面白くて読みたくなる文章を作る方法
エッセイの書き方や書くときのポイント、面白い文章を書くコツなどについて初心者の方にもわかりやすく解説します。自分の体験・考えを言葉で表現したい、面白い話が書きたいという人も、そもそもエッセイって何?という人もぜひチェックしてみてください。

エッセイとは、自分の体験や考えを自由な形式で文章にしたもののことです。文体や長さ、語り口などに特別な指定はなく、自分の思ったように書くことができます。
こう聞くと簡単に書けそうに感じるかもしれませんが、実際にペンを握ってみると、思ったように進まないということもよくあります。まずはエッセイがどんなものなのか、見ていきましょう。
自分の体験や考えを書くという点では、エッセイは日記に似た部分もありますが、両者には大きな違いがあります。日記は自分だけが読むことを前提にしているのに対し、エッセイは人に読んでもらうことを前提とした文章です。
エッセイは書いてそこで終わりではなく、読者を楽しませる工夫が必要になります。
なお、エッセイという言葉は、アメリカやヨーロッパでは「小論文」のような意味合いが強いようですが、日本で現在定着しているのは「随筆(書き手の体験を元に事実や状況をまとめた文章)」の意味合いです。
エッセイは自分の体験や知り合いから聞いた話、読書から得た知識などを元にして書かれることが多いです。
自分の子どもの頃の話やユニークな子育てエピソード、知り合いから聞いた面白い話、最近あった奇妙な出来事など、自分の身に起こった体験について書き、それについてどう思ったのか、自分の感情や考えを文章にしたものがエッセイです。
内容が面白かったとしても、話の内容が事実ではなく創作である場合は、エッセイではありません。
エッセイは自分の体験を元にして書く文章ですが、単に出来事に関する感想を「楽しかった」「うれしかった」などと書くだけではエッセイとはいえません。
その感情を感じるまでの心の動きや、そこに思い至った背景など、自分の心の動きを深く掘り下げて文章で表現したものがエッセイです。
自分の心の動きを文章にするのは大変な作業です。初めて書くときは、おしゃべりをするような感覚ですらすら書くのは難しいかもしれません。まずはたくさん書いてみて、コツを掴んでいきましょう。

ここからはエッセイの書き方の基本的な流れをご紹介します。
まずは、エッセイの「テーマ」決めです。単に面白いだけではなく、読者の心に残る内容や、役立つ知識などを盛り込むことで、読み応えのある文章になります。
エッセイのテーマは無数に存在します。エッセイでは自分の考えや心について深く掘り下げて必要があるため、自分が興味のある内容にすると書きやすいでしょう。
自由に好きなことを書くのがエッセイですが、書いた文章は「人に読まれる」ということを忘れないことが大切です。どんな人が、どんなときに、どんな心境で自分のエッセイを読むのかじっくり考えて構成を作りましょう。
1つの文章だけではなく、1冊の本を作るつもりで書くなら、話の構成だけではなく目次(全体の構成)を考える必要があります。文章の雰囲気やテーマに合った構成で、ユニークな流れを心掛けるといいでしょう。
テーマを決め、構成を考えたら、いよいよ本文を書いていきます。
たとえば、ハイキングでの経験をエッセイにするなら、どんな交通手段を使い、いつ、誰と、どこに行ったのか。どんな経験をして、何を感じて、何を考えたのか。
苦労して山に登り、やっと頂上の絶景を見られたのであれば、達成感を味わったことでしょう。しかし、そこに到達するまでは楽なことばかりではなかったはず。疲れて歩くのが嫌になったり、「やっぱりロープウェイで行けばよかったかもしれない」と考えたりしたかもしれません。
このように経験した事実と、その中での自分の感情の動きを書いていきます。このとき、他の人が普通は考えないような自分の独自の視点や考え方が書かれていると、より面白味のある、引き込まれる内容にできるでしょう。
エッセイの本文を書き終わったら、推敲してみます。エッセイは日常の話題や食事、旅行など身近な話題をテーマとなることが多いです。
読者にも知識がある分、内容のチェックが辛口になる可能性もあるため、誤字や脱字、同じ話の繰り返しになっている箇所や、矛盾点がないかをしっかりチェックしましょう。
せっかく面白い内容になっても、誤字や脱字で読者の気が散ってしまってはもったいないので、注意したいポイントです。
エッセイのタイトルを考えます。ユニークなタイトルであれば、読む前から読者の興味を惹けるでしょう。
内容を読み終えた後で「なるほど」と思うような、少し謎めいたタイトルにするのも面白いです。普通ならしない言い回しや、気になる単語を使うといいでしょう。
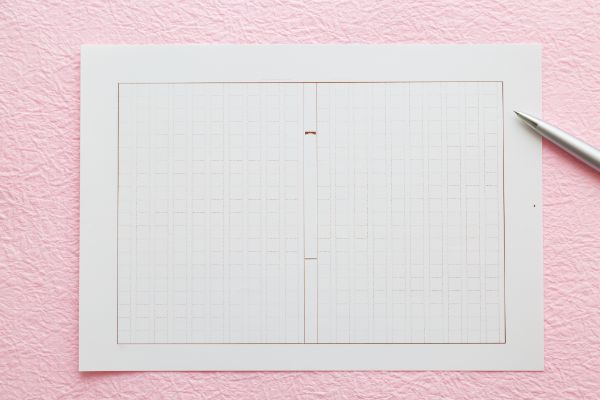
ここからは、エッセイを書くときのポイントをご紹介します。
エッセイでは、自分の言葉で書く方が読者の心に訴えかけられる文章になります。自分はわかっても読者が理解できないかもしれない難しい言い回しや専門用語よりも、わかりやすい言葉で書きましょう。
もしも読者が理解できないと考えられる言葉を使う場合は、説明を付け加えるようにします。
テーマとして題材についての基礎知識や、著者であるあなたや登場人物についての情報など、エッセイの理解に必要な内容を入れる情報を散りばめると、読者は文章に入り込みやすくなります。
すべてを細かく書く必要はありませんが、くどくなりすぎない程度に必要な情報を入れましょう。
エッセイに文字数の制限はありませんが、長くなるほど内容をきれいにまとめるのが難しくなるため、最初は短めがいいでしょう。
自分の体験や考えを書くエッセイは「誰が書くか」ということが重要なポイントです。芸能人やスポーツ選手など、著名人であれば長文のエッセイでも読んでもらえますが、全く知らない人の長文のエッセイを読もうという人はなかなかいません。
日本人は、平均して1分間に600文字程度読めるといわれています。エッセイの文字数の目安としては、2〜3分で読み切れる1200〜1800文字ほどにするのがおすすめです。

エッセイをもっと面白くするために、いくつかのコツをご紹介します。
面白い体験をしたことがある人は、それについて書くと面白いエッセイにできます。他の人が経験したことがないような珍しい体験や、レアな出来事はそれだけで読者の興味を惹けるテーマです。
専門的な内容になる場合は、読者の理解を深めるための情報を入れるのを忘れないようにしましょう。
どんなエッセイにしようか迷ったときは、エッセイの鉄板といわれる失敗ネタや笑える話がおすすめ。失敗したときの話や、ドジな話は誰でも気軽に面白がって読める題材です。
教訓やためになる知識なども盛り込みやすいので、迷ったときはぜひ失敗ネタでエッセイを書いてみてください。必ずしも自分が体験した話ではなく、家族や友達の話など、自分の身のまわりで起きた失敗でもOKです。
読者が共感しやすいテーマや内容を選ぶと、興味を持ってもらいやすくなります。思わず「あるある」と頷いてしまうような内容であれば、読者はかつての自分の経験を思い起こしながら、エッセイを読み進めていけるでしょう。
テーマ選びに迷ったときは共感されやすく、読者の記憶や経験を呼び起こすようなテーマがおすすめです。
エッセイを書く人は、好奇心旺盛な人が多いです。いろいろなことに興味を向け、好奇心を持って取り組めば面白い経験ができ、自然とエッセイのネタが増えていきます。
身のまわりで起こることに関心を持ち、「なぜ?」「どうして?」と掘り下げていくことで書きたいテーマが見つかりやすくなるでしょう。
エッセイの中に会話文を入れると、全体に生き生きした雰囲気が生まれます。また、誰かが会話している言葉を入れることで、読んだときに情景の浮かぶリアリティある文章になるので、ぜひ会話文を入れてみてください。
エッセイは自由に書いてOKですが、1行目が非常に重要です。読者の心を惹き付け、印象が残る書き出しを考えましょう。
いきなり唐突な文章から始めたり、「バシャーン!」のような擬音から始めたり、会話から書き出してみるのも効果的です。
エッセイは結論も大切です。最終的に「オチ」のある話の方が面白く、すっきりと読ませられます。逆に、あえて問題を投げかけて終わる書き方もあります。
エッセイの最後の3行は全体の印象を大きく左右する部分です。じっくり考えて、自分なりの考えをまとめましょう。

ここからは、エッセイの書き方を学ぶ方法をご紹介します。
エッセイをもっとうまく書きたいと思ったら、プロの面白いエッセイをたくさん読むといいでしょう。面白い文章をいくつも読んで、構成や語り口、書き出しや締めくくり方を学びます。プロのエッセイを例文として、真似をして自分のエッセイに生かしてみるのもいいでしょう。
また、エッセイの書き方について解説されている本もあります。エッセイを書くための理論や技術など、基礎からしっかり理解したい人におすすめです。
エッセイは、プロでも一発書きではすぐに面白い文章は書けません。構成を作り、書き直しや推敲をして、やっと一つのエッセイになります。
最初から面白い文章を書こうと意識し過ぎず、自分の伝えたいテーマを盛り込んだ作品をいくつも書いて、完成させたら読み返してみる。そうすることで自分の文章の特徴や改善点を見つけられます。
エッセイのテーマは自分の日常など、身近なものでOK。語り口も形式も自由なので、エッセイを書いてみたい人は、まずは気軽に挑戦してみましょう。
エッセイは日記ではなく、人に読まれることが前提なので、執筆時は読者を意識して書くことが欠かせません。自分が書きたいことを、他人が読みたくなる文章にすることが大切です。
ハルメクのエッセイ講座
↑山本ふみこさんが紹介!【ラジオエッセイ】だから、好きな先輩↑
驚きの軽さ&使いやすさ!
1本で7つの効果ハルメクが厳選した選りすぐりの商品
なるほど! エッセイと日記は違うものなんですね。混同してました。
大人にナ(成)五段活用 ① 【大人に成らない】 【大人に成ろう】 ② 【大人に成ります】 【大人成った】 ③ 【大人に成る】 ④ 【大人に成るとき】 ⑤ 【大人に成れば】 ⑥ 【大人に成れ】 私と他者との心の対応において、六態様がある。私をAとし、観察者をBとして観察者の子供の頃(過去)の私に対する印象と齢を経てからの両者の会話を挙げみる。 B 「その事(ある事案)について、A君その事について【大人に成ろう】としたかい。」 A 「【大人に成ろう】としたかったが、【大人に成らない】ことにしているよ。」 ①の用例は、両者の事案に対する心の意識が相違している場合である。 B 「その事(ある事案)について、A君その事について【大人に成ります】って言ってくれたがどうかい。」 A 「B君の言うように、その事はその通りだしその事に関して【大人成った】よ。」 ②の用例は、両者の事案に対する心の意識が合致している場合である。 B 「A君は、立派な【大人に成る】と見込んでいたがどうかなぁ。」 A 「B君そらそうだ、あれからそれ相当の時間が経過しているから立派かは別にして、【大人に成る】って当たり前だよ。」 ③の用例は、両者の時間の経過に対する共通の認識を確認した場合である。 B 「A君、【大人に成るとき】は子供の頃と違って人それぞれの心情の襞が違って現れるが一番の襞は何かね。」 A 「B君、一番の襞は万人に共通する心だよ。」 ④の用例は、人それぞれの環境等による人間形成の結果の問いの場合である。 B 「その事(ある事案)について、A君その事について【大人に成れば】分かってくれると思っていたがどうかね。」 A 「【大人に成れば】って言ったって、私の心情の一番の襞で理解すると、【大人に成れば】って言われても難しいよ。」 ⑤の用例は、人それぞれの心情の襞で照らし合わせると相違している場合である。 B 「その事(ある事案)について、A君その事について【大人に成れ】と言ったがどうかね。」 A 「【大人に成れ】と言われそうかと思ったが、心情の襞で照らし合わせると相違しているよ。」 ⑥の用例は、人それぞれの心情の襞では、両者同じ心情を共有できない場合である。 万人に共通する心(心情の襞)とは、これをメタ数学として【身体化された心】から『大人にナ』を見てみる。 フランシスコ・ヴァレラ+エヴァン・トンプソン+エレノア・ロッシュ著田中靖夫訳の【身体化された心仏教思想からのエナクティブ・アプローチ】にマルティン・ハイデガーの「存在の問い」の【惑星思考】がある。 水無田気流さんが、ハイデガーの「先駆的決意性」で死生観を西欧思想は肉食系死生観、東洋思想は草食系死生観と述べておられる。 京都学派の思想に傾注する佐伯啓思先生もコラム「西洋と異なる思想 今こそ」で「日本で唯一の哲学者」と称される西田幾多郎は、西洋の論理を【有の論理】日本の論理を【無の論理】と呼んだりもしたと記している。同じ土壌の中で西谷啓冶は、ハイデガーの「存在の問い」の【惑星思考】の呼びかけに精通した。そのサワリを記すと、「・・・主体は客体化される主体と主体化される客体のいずれにもなる。」とある。 『大人にナ』のA君とB君の会話におけるA君の心情の襞をメタ数学の基底として西洋思想と東洋思想の融合としての【惑星思考】で探る。 物事をありのままに見るこれを自然主義としよう。A君がありのままに見えた事を言葉でB君に表象してみても、A君とB君の生を受けてからの環境(氏より育ち)に支配されたそれぞれの言葉の表象は違うのである。 しかし、数学の言語での表象は、万人に共通する心でなければならない。だから、『大人にナ』の事案で掲げた①⑤⑥についての内容が、数学の言語で表象されるなら解決するはずである。④については微妙(判断し難い)である。 新井紀子先生は、数式は、「宇宙人にも分かるように」と言われる。 森田真生氏は、「数学の演奏会」等精力的にライブ活動でしばしば自然数の表象を【身体化された心】で捉えようとされている。 人は、この自然数の一次元としての離散的な物理的集合の序数としての123・・・との視覚から【身体化された心】で表象の記号として認知(ラベル化)する。 このラベル化された数字を【身体化された心】の万人に共通する価値の順序としての表象に用いるとする。これを一次元の数とする。 二次元の数として物理量の面積を数で表象できる。 三次元の数の価値として、一次元の数と二次元の数の乗積として表象できる。 そこで、有限個の一次元の集合の表象された自然数の人の思考した大小(価値)比較の一次元の要素の組み合わせと三次元の要素の組み合わせの思考結果としての三次元の大小(価値)比較を数学は、『量化素子』で真理を明示しうるのだ。これは、二次元の数の減少を【身体化された心】として捉える事だったのだ。 そのエナクティブ・アプローチからの創発は、一・二・三次元の数のそれぞれの次元の数の組み合わせが『離散的有限個の有理数の多変数創発関数論』を醸成していたのだ。 チョット昔の風景を再現する。レオポルド・インフェルト著市井三郎訳の「ガロアの生涯神々の愛でし人」の一八三一年一月一三日の一九歳のエヴァリスト・ガロアの講義の聞き手(A)の呟きを記す。 「・・・数学は、われわれの感覚印象の世界に訴えることのない唯一のものであります。」 数学は、惑星思考の【身体化された心】から探れるのじゃないの? 「数学の研究が、知識というよりは真理の探究を目指している・・・」 数学は、【身体化された心】のオエセル(光明)かも知れない? 「・・・一挙にすべての数学的真理を認識しうる人がいるとすれば、その人はわずかの原理と均一な方法とから、それらのあらゆる真理を厳密に機械的に演繹できるでしょう。」 数学は、【身体化された心】のオエセル(光明)から『離散的有限個の有理数の多変数創発関数論』から群を知らしめているのではないか? 鷲田清一先生の「折々のことば」の拾いに、マックス・ピカートの言葉の 「非連続の世界においては、精神は存在しえない」 を眼にし、つくづく数学は、ミステリーだなー・・・と。 何故なら、非連続の世界を【身体化された心】で捉えると連続の世界が顕現してくる、これ即ち精神の世界への突入ではないか。数学は、精神に生きる生き物だと。 また、数の世界では、一次元の数と二次元の数の解析接続を【身体化された心】からの【惑星思考】により正比例と反比例を量化すると・・・。このことから創発関数論の孵化係数は、一次元の数と二次元の数をアーベル群化する幾何学的創発係数とおぼしき【e‐2】を確かめることができる。 マックス・ピカートのこのソースは、「われわれ自身のなかのヒトラー」で「連関性を欠いた人間」に連続性がない。なるほど ゝ 健全な「精神は存在しえない」って言うことなのですね。 離散的有限個の有理数の多変数創発関数論に出くわしたことは いろはかるたに 「犬も歩けば棒に当る」 人生こんなもんっていう コッチャ ヽ ・・・と。 しかし、いろは歌に込められた呪文は裁かれねばならない。 合掌