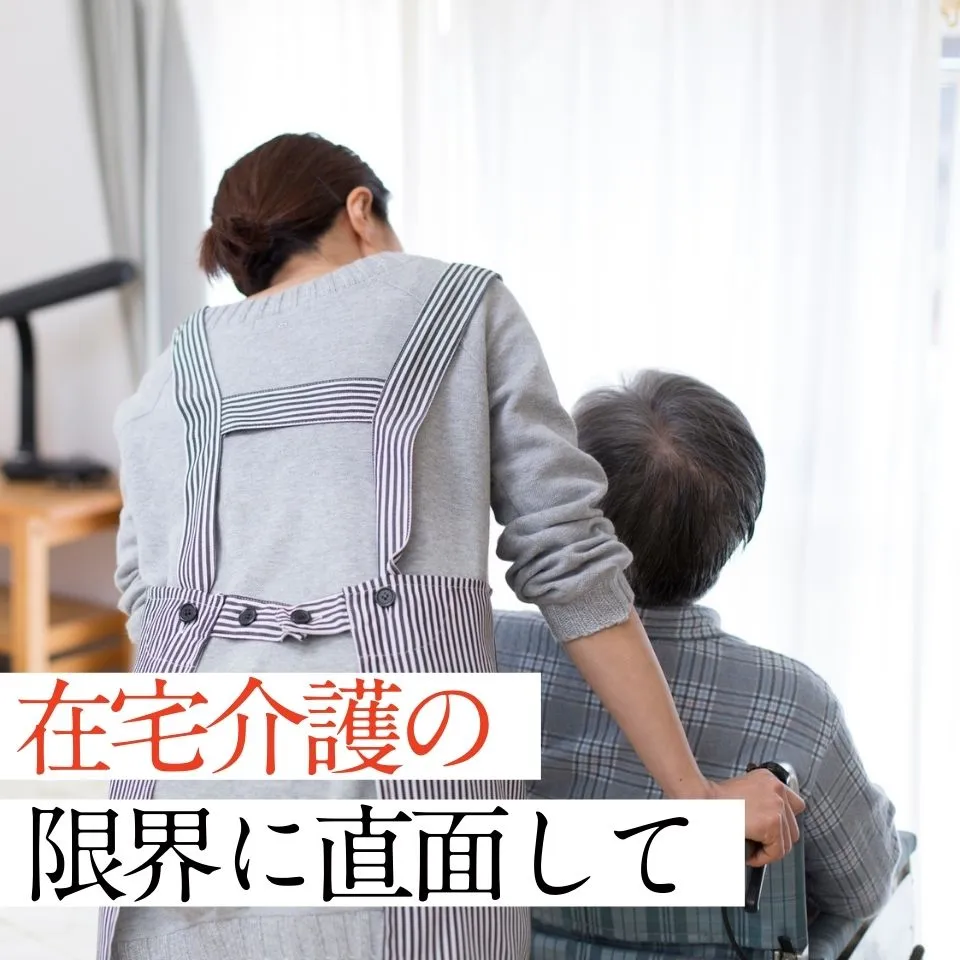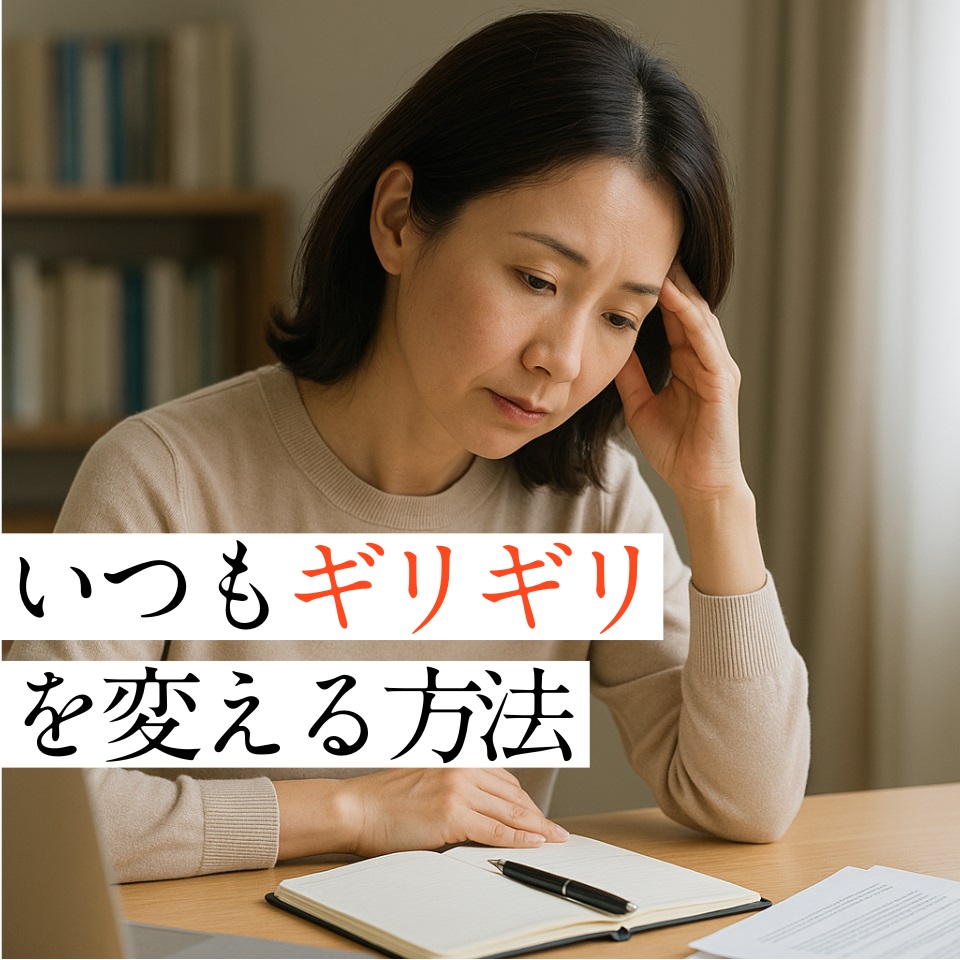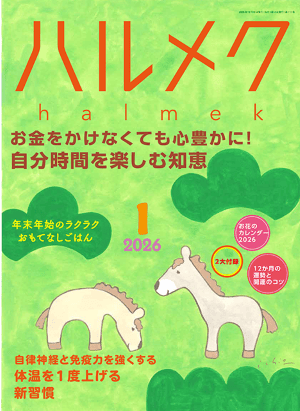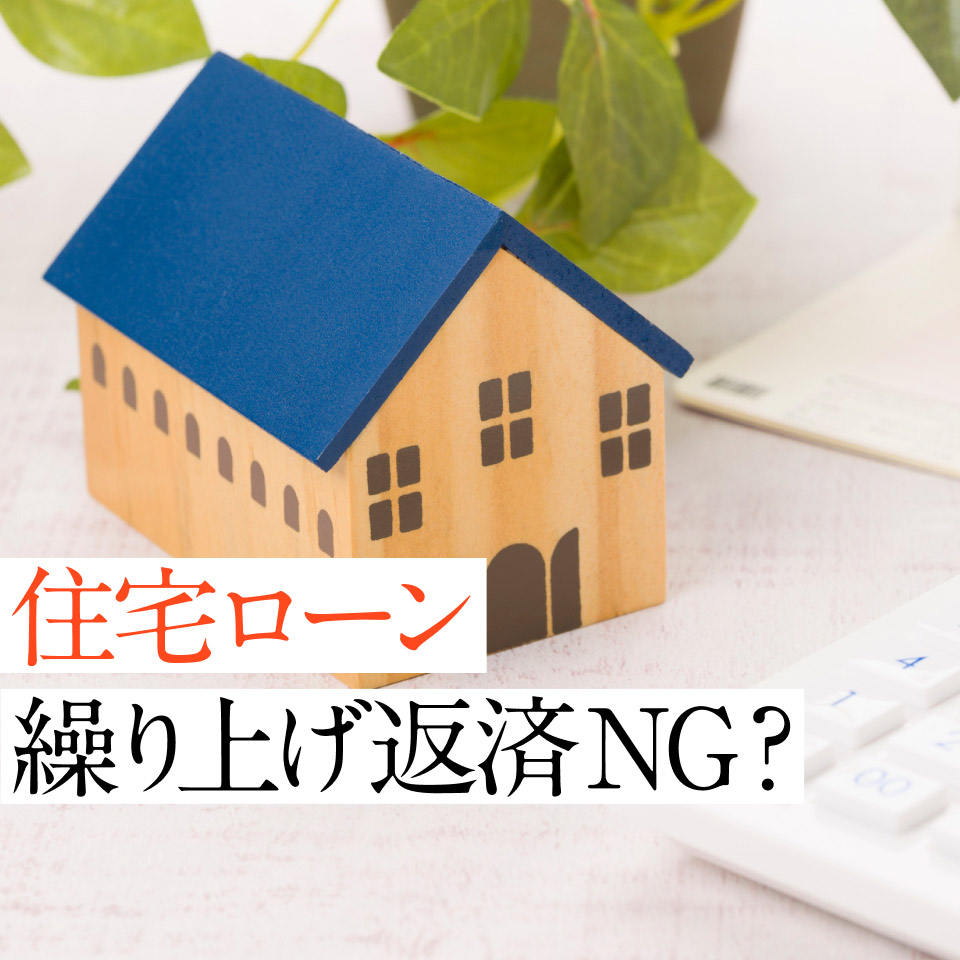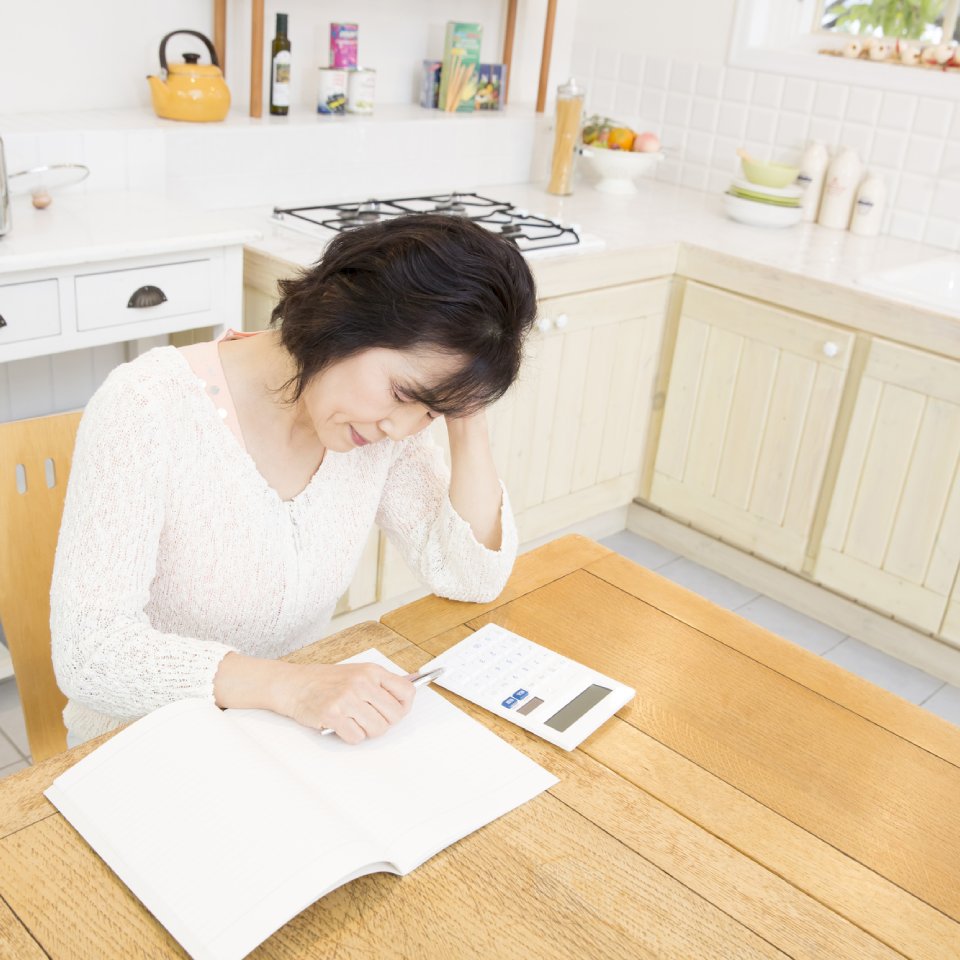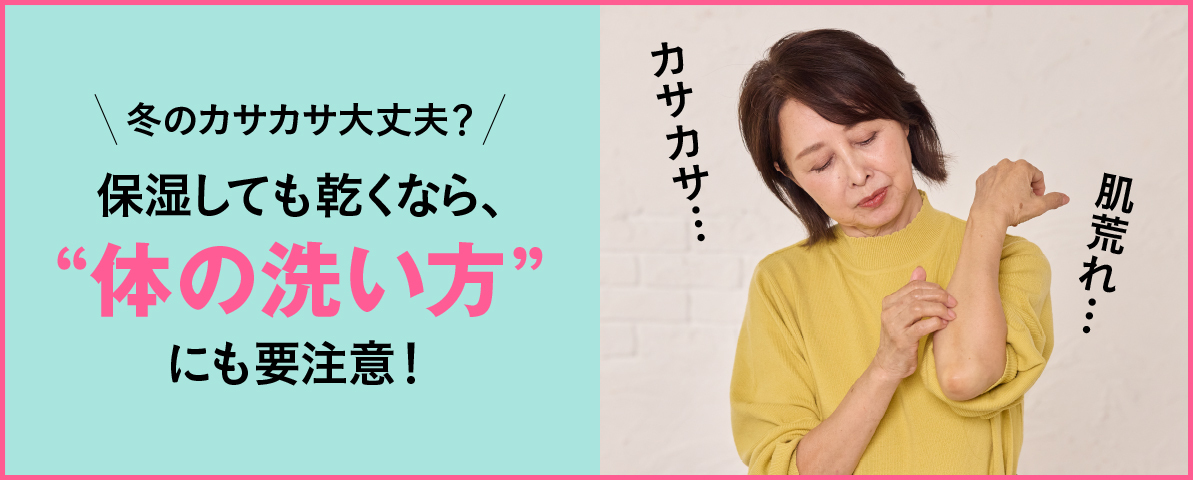~「今から備える」お金の知識~
50代女性のための老後資金&年金生活 基本用語集【2025年度版】
50代女性のための老後資金&年金生活 基本用語集【2025年度版】
公開日:2025年06月18日

年金に関する用語
国民年金
国民年金は、すべての日本国民が20歳から60歳まで加入する年金制度です。自営業者や専業主婦などの方が支払う保険料によって形成され、老齢基礎年金として受給されます。
出典:厚生労働省
厚生年金
「厚生年金」は会社員や公務員が加入する年金制度で、保険料は月給に応じて計算され、事業主と労働者で半額ずつ負担(労使折半)します。支給開始年齢は65歳で確定しています。ただし「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」は段階的に縮小され、男性は2025年度、女性は2030年度で支給が終了します。
出典:厚生労働省
年金見込額
「ねんきん定期便」に記載される年金見込額は、給与水準が今後横ばいで推移し、60歳まで年金に加入すると仮定して計算された金額です。
40代まで通知されていた「加入実績に応じた額」に比べると「見込額」はより実態に近く、将来(2021年4月1日現在の50代の多くは65歳から)受け取れるおおよその年金額を把握できます。
出典:りそな銀行
遺族年金
公的年金の加入者が亡くなった際、その家族(主に配偶者や子ども)を支援する制度です。「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、条件や受給額は年金加入期間や家族構成によります。
出典:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_013.html
寡婦年金
寡婦年金は、国民年金第1号被保険者として保険料を10年以上納めた夫が亡くなった場合、その夫と10年以上婚姻関係があり、生計を維持していた妻に対して支給される年金です。
支給期間は妻が60歳から65歳になるまでで、金額は夫の老齢基礎年金額の4分の3です。ただし、夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがある場合や、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は、支給対象外となります。
出典:日本年金機構
基礎年金番号
基礎年金番号は、年金加入記録を管理するための個人専用の識別番号です。日本年金機構により、原則として1人につき1つの番号が付与されます。
令和4年4月以降、新たに年金制度に加入する方には、従来の「年金手帳」に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。一方、既に年金手帳を持っている方はそのまま引き続き保管してください。
出典:日本年金機構
物価スライド
年金額は、物価の変動に応じて改定される「物価スライド制」が採用されており、前年の消費者物価指数の変化に基づき翌年4月に自動的に調整されます。これは公的年金の特徴で、私的年金にはない制度です。
加えて、平成17年から導入された「マクロ経済スライド」により、年金財政の均衡を保つ必要がある場合、物価の伸びより年金額の伸びを抑える調整が行われる仕組みも取り入れられています。
出典:日本年金機構
老後資金に関する用語
退職金
退職金制度は、一定の勤続年数や業績に応じて退職時に金銭を支給する仕組みで、約80%の企業が導入しています。ただし法律上義務ではなく、内容は企業ごとに異なります。計算方法は主に年功制、ポイント制などがあり、相場は勤続年数や学歴によりますが、大卒で約2,200万円が目安です。
制度の有無や詳細は「退職金規程」を確認することで明らかになりますが、途中で変更される場合があるため定期的な確認が重要です。
出典:三井住友銀行
老後資金モデルケース
総務省による調査では、夫婦の年金生活に必要とされる生活費は毎月約22万円程度が目安となっています。ただし住まい・健康状態によって増減があります。
出典:総務省統計局
高年齢者雇用継続給付
60歳以降に再雇用などで働く場合、給与が一定額減少していると、その差額を補填する給付金制度(雇用保険制度の一部)です。60~65歳未満で賃金が60歳到達時の75%未満となった場合に、賃金の最大10%(令和7年3月31日以前は15%)が支給されます。
また、特別支給の老齢厚生年金を受給している場合、給付を受けると年金の一部が停止され、停止額は賃金(標準報酬月額)の最大4%(令和7年3月31日以前は最大6%)となります。
出典:日本年金機構
医療費控除
医療費控除は、本人や家族の令和6年中に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得から差し引ける制度です。申告には「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付し、領収書は5年間保管が必要です。また、セルフメディケーション税制との併用はできず、選択後の変更は認められません。
出典:国税庁
高額療養費制度
医療費が1か月で一定額を超えた場合、その超えた分を支給し、負担を軽減する制度。上限額は年齢や所得に応じて設定されており、条件を満たせばさらに負担が軽減される。世代間の公平を保つため、負担能力に応じた適正な負担が求められる。
出典:厚生労働省
セルフメディケーション税制
健康維持や病気予防のための一定の取組を行っている方が、1年間に12,000円を超える対象医薬品を購入した際に受けられる所得控除制度です。この制度を選択すると通常の医療費控除は受けられないため、どちらを適用するか注意が必要です。
出典:国税庁
資産運用に関する用語

iDeCo(イデコ)
自分の掛金を運用しながら資産を形成する年金制度です。掛金の拠出は原則65歳まで可能(条件あり)で、60歳以降に老齢給付金を受け取れます。ただし、一度給付金を受け取ると掛金の拠出はできなくなります。
主に20歳以上65歳未満の公的年金の被保険者が加入でき、老後の豊かな生活を目指した資産形成の方法として推奨されています。
出典:iDECO公式サイト
NISA(ニーサ)
毎年一定額までの投資に対する運用益や配当が非課税になる制度で、個人の資産形成をサポートするために設けられた仕組みです。通常、株式や投資信託の利益には税金がかかりますが、NISAを利用することで税負担を軽減できます。
2024年から、つみたてNISAや一般NISAが「新NISA」に一本化されました。資産の長期的な運用を行う方や、初心者でも手軽に投資を始めたい方に特に適しています。
出典:金融庁
分散投資
複数の資産(株式、債券、不動産など)や地域、時間に分けて投資することでリスクを軽減する資産運用の方法です。これらを組み合わせた運用計画を「ポートフォリオ」と呼び、安定的な資産形成を目指す上で重要な手法となります。
出典:金融庁
確定給付型年金
企業が従業員に将来の給付額を約束し、給与や勤続年数に基づいて高齢期に年金を支給する制度です。運用リスクは企業が負担し、「基金型」と「規約型」に分かれます。
また、厚生年金基金も類似の制度で上乗せ給付を行いますが、運用負担の大きさから現在は導入企業が減少傾向にあります。
今回、50代女性に向けて老後資金と年金生活に役立つ重要な用語を解説しました。これらを早めに理解しておくことで、安心できるライフプラン設計が可能になります。
迷った場合は専門家の助言を取り入れながら、ぜひご自身の生活設計に活用してください!