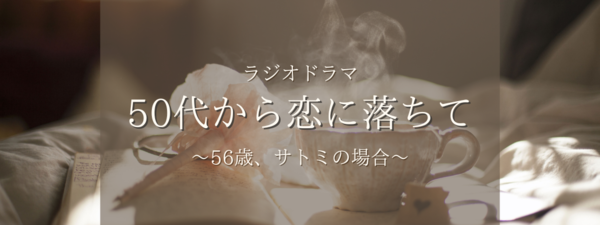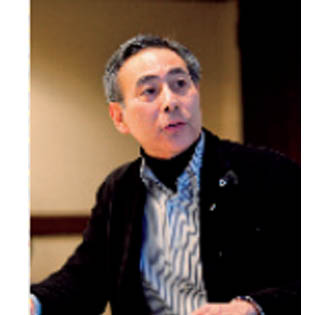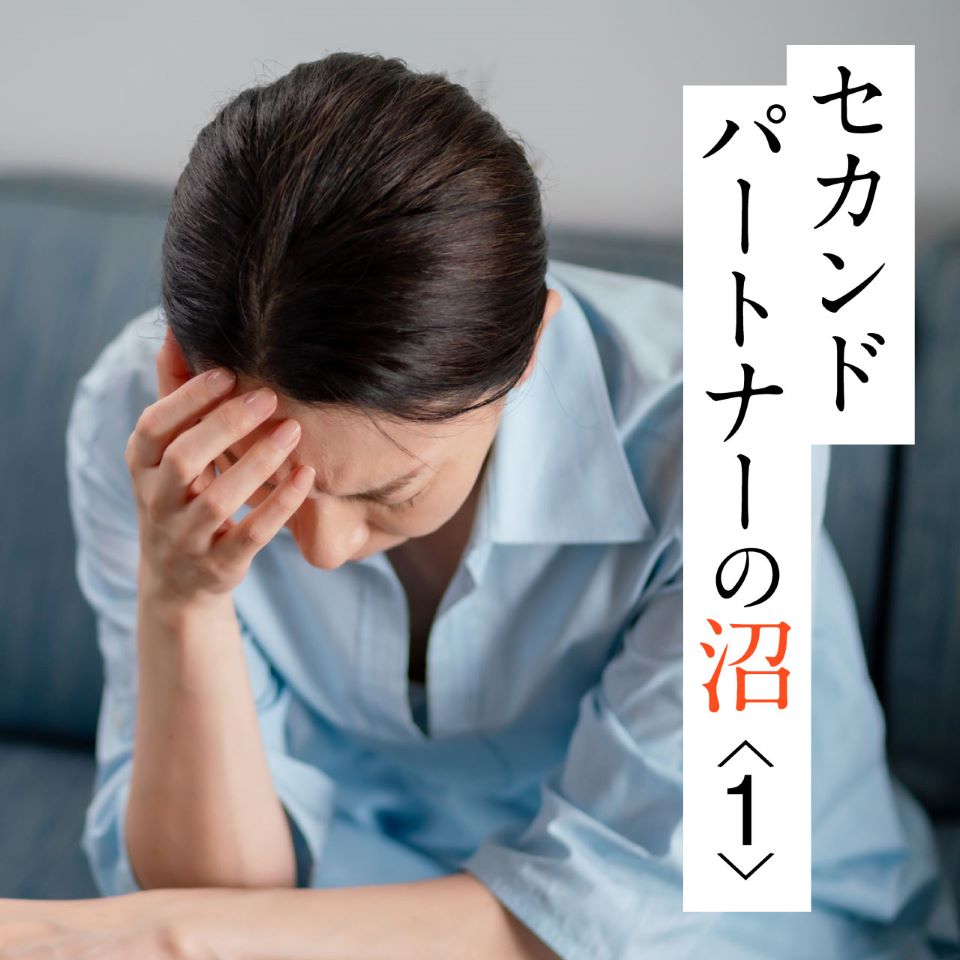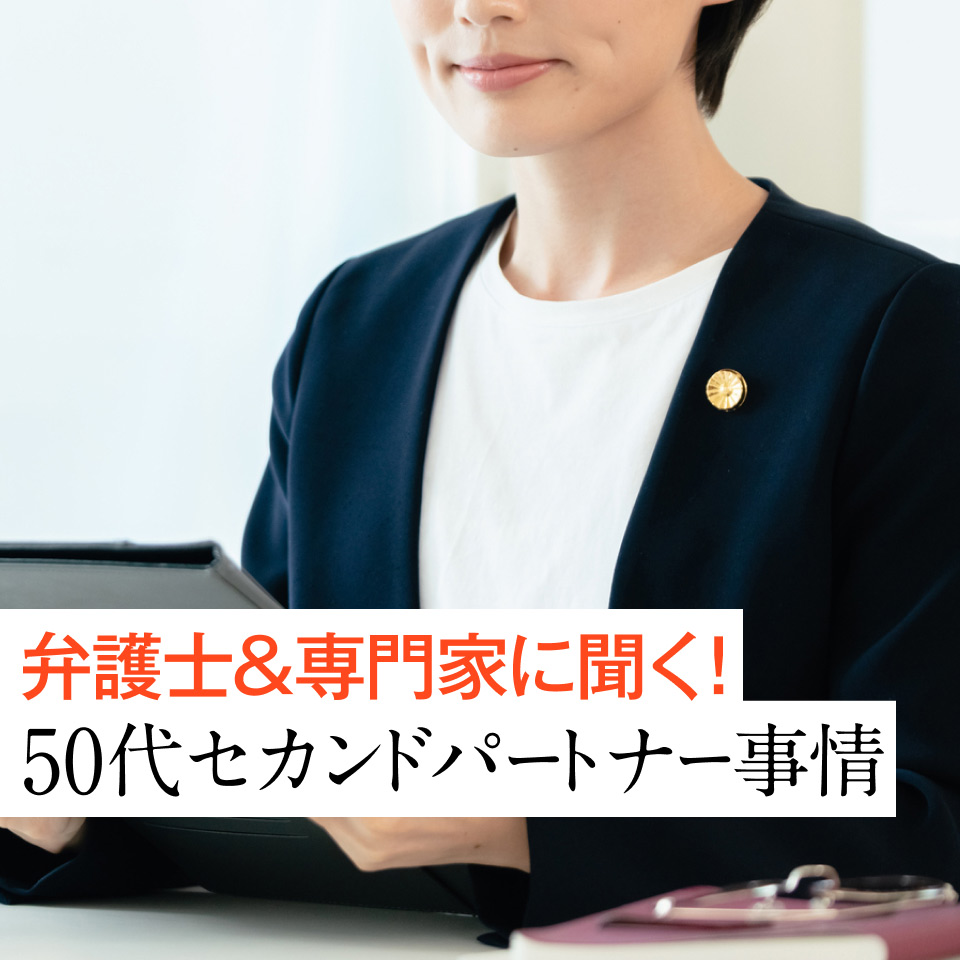しんどい夫婦関係、問題の解決策は?(1)
命名医師が語る「夫源病」の原因は夫のモラハラにある
命名医師が語る「夫源病」の原因は夫のモラハラにある
更新日:2025年02月10日
公開日:2020年12月19日

夫源病は消えない、むしろ増えている

私が『夫源病 こんなアタシに誰がした』(大阪大学出版会刊)という本を出版してから約10年になります。一時的な流行なら、もう「夫源病」という言葉は消え去っているはずです。しかし、このコラムのように夫源病に関する取材の依頼は後を絶ちません。ウィキペディアにも「夫源病」が掲載されており、そこには幅広い方からの情報が掲載され、命名者の私が説明してきたこと以上に、よく説明されています。
さて、このように「夫源病」は減少するどころか、最近はますます増えているように感じています。
そもそも夫源病とは何でしょう? 男性には大変失礼なのですが、夫の心ない言動が妻のストレスとなって引き起こす体調不良のことです。体調不良には動悸、胃痛、不眠、血圧の上昇、気分の落ち込み、頭痛など、さまざまな症状が当てはまります。
当たり前ですが、「夫源病」は正式な医学用語ではありません。しかし、すべての世代の妻に「夫源病」が起きる可能性があります。その中でも特徴的な年代があります。
夫源病になりやすい世代とは?
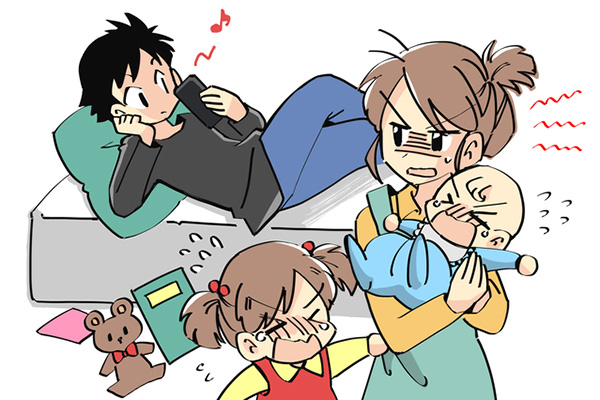
まずは、子育て世代。子育て中の、夫の心ない言動で妻の体調が悪くなる場合です。以前の女性なら経済力も乏しく、離婚すると幼い子どもを抱えて生活できないので辛抱されていたと思います。最近の女性は経済力もあり、辛抱して人生を台無しにするのは嫌だと言うことから離婚を決意される方も少なくありません。そのためにシングルマザーが増えてきたのかもしれません。
子育て世代の不平不満は若い時だけに影響するのではなく、中年期や熟年期にも大きな影響を与えているようです。次に気を付けなければいけないのは子どもがある程度大きくなった中年期でしょう。子どものためにとがんばっていた妻も子育てが一段落し、自分の人生を見つめ直す時期になっています。この時に夫との関係が悪ければ、別居や離婚を考えるかもしれません。
そして1番危険なのは熟年期です。特に定年後はかなり危険な時といえます。
夫に不満があっても「亭主元気で留守がいい」と、すれ違いの生活をしていたのが、定年により一日中夫と顔を突き合わせなければならなくなります。仲の良い夫婦でさえ息が詰まると言うのですから、関係が悪くなった夫婦なら想像を絶するくらいつらいものだと思います。
夫源病の原因は夫の「モラルハラスメント」
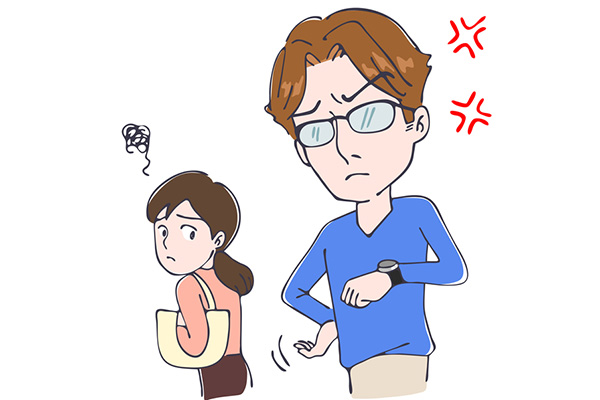
では、夫源病の原因は何でしょうか? ひと言で言えば「モラルハラスメント」、いわゆる「モラハラ」でしょう。はっきりと暴力を伴うDVなら警察などに相談しやすいと思いますが、言葉や態度によるDV、これがモラハラにあたるのですが、加害者である夫もあまり気が付いていないようです。
妻を家政婦のように扱う
上から目線や支配的な言動がモラハラに当たります。特に妻が専業主婦なら、家事をやるのは当たり前と考え、妻を家政婦さんのように上から目線で使い倒すのは大変危険です。さらに料理やお茶を入れるのが当たり前と思っているので「ありがとう」という感謝の言葉もかけません。夫にすれば「言わなくてもわかっているだろう」と思うのですが、夫婦間でも感謝の言葉は大切です。
妻の行動を管理する
妻の不満で大きいのは、夫が妻の行動を管理することです。夫からすれば心配をしているだけだと言いますが、妻が外出するたびに「どこに行くのだ?何時に帰ってくるのだ?」としつこく尋ねることはありませんか? また専業主婦の妻が仕事を始めようとしても、あまり良い顔をしません。
自分を良い夫だと思い、上司面をする
そして妻が旅行に行くのを「許可しています」とか「好きなようにさせてやっています」のように、自分では良い夫と思っている節があります。しかし、この言動でもわかるように、自分が妻の上司であるような振る舞いをするので妻のストレスは溜まるばかりです。
モラハラ夫は意識を変えないといけません
妻に体調不良が起きており、自分もこれらの言動に心当たりがある夫は、なるべく早く意識を変えないと妻が別居を始めたり、離婚を言い出したりするかもしれません。これからも男性(夫)にとっては、つらい話が続くかもしれませんが、夫婦生活を長く維持するためには必要なことだと思ってご辛抱ください。
次回は、妻は夫にどうやって気付いてもらえばいいのか、夫源病の解決策をお伝えしていきます。
石蔵文信さん(いしくら・ふみのぶ)さんのプロフィール

1955(昭和30)年生まれ。大阪大学人間科学研究科未来共創センター招へい教授。循環器内科が専門だが、早くから心療内科の領域も手がけ、特に中高年のメンタルケア、うつ病治療に積極的に取り組む。01年には全国でも先駆けとなる「男性更年期外来」を大阪市内で開設、性機能障害の治療も専門的に行う(眼科イシクラクリニック)。2022年10月ご逝去。
■もっと知りたい■
- その体調不良は夫源病?原因チェックリストと対策方法
- 夫源病連載2 夫源病の改善方法は我慢し過ぎないこと
- 夫源病連載3 妻側が配慮したい、男性の更年期とは?その原因は
- コロナ禍で離婚の意思が高まった50代夫婦の関係性
- コロナ禍の50代夫婦!以前の関係性にはもう戻れない
- 卒婚とは?50代で見直した新しい夫婦の形
- 介護別居からの卒婚!距離感が心地いい夫婦の形とは?
- 【体験談】離婚ではなく家庭内別居を選んだ夫
夫以外の人と恋に落ちて…50代の恋【ラジオドラマ】
ハルメク365で大人気の恋愛ルポが、ラジオドラマになりました!(全4回)
<あらすじ>
主人公は、平凡な毎日を送ってきた専業主婦の56歳サトミ。
結婚して28年、「もう恋愛には縁がない」と思っていた彼女が、ふとしたきっかけで数十年ぶりに激しい恋に落ちていく…。
ラジオドラマはこちらから!>>
記事で読みたい方はこちら!>>