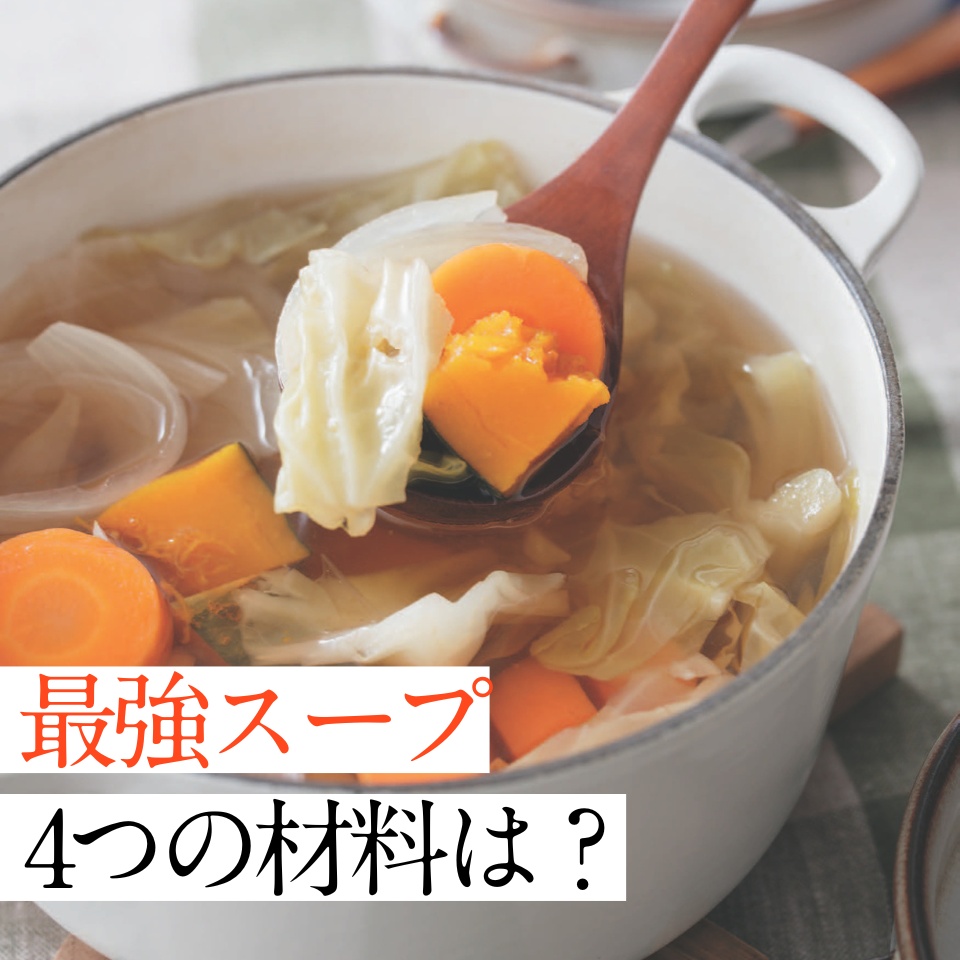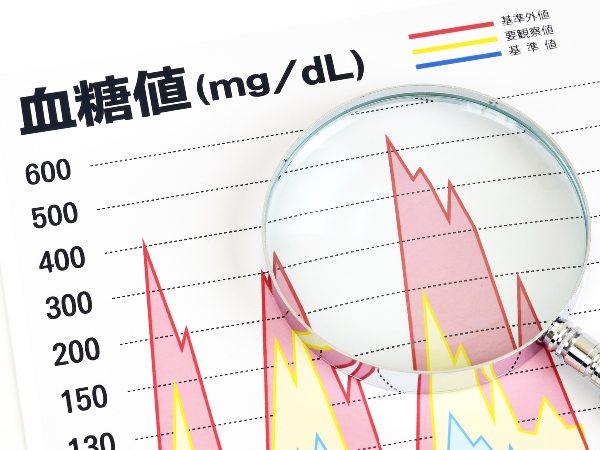むくみ解消・高血圧に効果的?取り過ぎはNG?
カリウムの多い食べ物は?不足・過剰摂取の影響も
カリウムの多い食べ物は?不足・過剰摂取の影響も
公開日:2023年08月15日

カリウムとは
カリウムとは、人間の体の生命維持に欠かせない必須ミネラルの一つです。体内に最も多く存在するミネラルで、細胞の浸透圧を調整し、体内の水分を一定に保つ働きがあります。
カリウムの働き
ここでは、カリウムの効果についてチェックしてみましょう。カリウムには、以下のようなさまざまな働きがあります。
- 細胞の浸透圧の調整
- 体内の水分保持
- 酸塩基平衡の維持(酸性物質とアルカリ性物質のバランスを保つ)
- 神経刺激の伝達
- 心臓機能・筋肉機能の調節
- 細胞内の酵素反応の調節
- エネルギー代謝への関与
- 腎臓でのナトリウムの再吸収を抑制・排出を促すことで血圧を下げる
カリウムには体内の過剰なナトリウム(塩分)を体外に排出する作用があり、血圧を下げる効果がある栄養素です。
ナトリウムには水分をため込む性質があるため、塩分を過剰に摂取するとむくみが起こることに。カリウムはむくみ解消効果が期待できる食べ物としても知られています。
カリウムの1日の摂取量の目安

カリウムの1日の摂取量の目安は、健康な人とカリウム制限が必要な人の場合では違いがあります。ここから、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
健康な人の場合
厚生労働省が公表する「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によれば、18歳以上の1日の目安量(体内のカリウム平衡を維持するために適正と考えられる量)は女性は2000mg、男性は2500mgとなっています。
また、生活習慣病の予防を目的とした1日当たりの摂取量の目標量は18歳以上の女性では2600mg、男性は3000mgとなっています。
WHO(世界保健機関)が2012年に提案した高血圧予防のための摂取量は、男女ともに1日3510mgの摂取を目標にするといいと紹介されています。
カリウムは、腎機能が正常で、サプリメントなども飲んでいない場合は通常の食事で過剰摂取となるリスクは低いため、耐容上限量は設定されていません。
厚生労働省が行った「平成30年国民健康・栄養調査」によれば、20歳以上のカリウムの1日あたりの平均摂取量は以下のようになっています。
【女性のカリウムの1日あたりの平均摂取量】
- 20〜29歳……1830mg
- 30〜39歳……2023mg
- 40〜49歳……1996mg
- 50〜59歳……2260mg
- 60〜69歳……2536mg
- 70歳以上……2473mg
【男性のカリウムの1日あたりの平均摂取量】
- 20〜29歳……2160mg
- 30〜39歳……2197mg
- 40〜49歳……2163mg
- 50〜59歳……2373mg
- 60〜69歳……2670mg
- 70歳以上……2714mg
カリウム制限が必要な人の場合
腎臓病などによって腎機能に問題がある場合は、医師の判断によってカリウム制限が必要になることがあります。
健康な人の場合、カリウムを含む食品を取り過ぎたとしても尿として排出されます。しかし、腎臓が悪くなるとカリウムの排出がうまくできず、体内にたまってしまうことになるためです。
ただし、カリウムが少な過ぎても体によくありません。カリウムそのものが腎臓にダメージを与えるわけではなく、血液中にカリウムが蓄積し過ぎると心臓の不整脈につながるため、制限が必要になるというわけです。
「慢性腎臓病に対する食事療法基準2014年版」では、CKD(慢性腎臓病)のステージによる食事療法のカリウム摂取量を、以下のように紹介しています。
【CKDステージによる食事療法基準(カリウム)】
- ステージ 1(GFR≧90)……制限なし
- ステージ 2(GFR 60~89)……制限なし
- ステージ 3a(GFR 45~59)……制限なし
- ステージ 3b(GFR 30~44)……2000mg/日以下
- ステージ 4(GFR 15~29)……1500mg/日以下
- ステージ 5(GFR<15)
血液透析(週3回)……1500mg/日以下
腹膜透析……制限なし(高カリウム血症の場合は血液透析と同様に制限)
カリウムが豊富な食べ物

カリウムは、野菜や果物、芋、海藻、豆類などに豊富に含まれています。また、生鮮食品に多く含まれており、加工・精製が行われると含有量が少なくなることもカリウムの特徴の一つです。
ここからは、多く流通している食材からカリウムが豊富な食べ物とカリウムの含有量をランキング形式でご紹介します。(参照:文部科学省「食品成分データベース」)
野菜類
【カリウムを多く含む野菜類ランキング(可食部100g当たりの含有量)】
- 切干しだいこん(乾)……3500mg
- ドライトマト……3200mg
- パセリ(葉・生)……1000mg
- ブロッコリー(花序・焼き)……820mg
- ふきのとう(花序・生)……740mg
- かぶのぬかみそ(/根・皮なし)……740mg
- ほうれんそう(葉・冬採り・生)……690mg
- えだまめ(冷凍)……650mg
- 切りみつば(葉・生)……640mg
- にんじん(根・皮・生)……630mg
芋類
【カリウムを多く含む芋類ランキング(可食部100g当たりの含有量)】
- じゃがいも(乾燥マッシュポテト)……1200mg
- さつまいも(蒸し切干)……980mg
- 凍みこんにゃく(乾)……950mg
- フライドポテト(市販冷凍食品を揚げたもの)……660mg
- セレベス(球茎・生)……660mg
- さといも(球茎・生)……640mg
- やつがしら(球茎・生)……630mg
- きくいも(塊茎・生)……610mg
- ながいも・やまといも・いちょういも(塊茎・生)……590mg
- フライドポテト(生を揚げたもの)……580mg
果物類
【カリウムを多く含む果物類ランキング(可食部100g当たりの含有量)】
- バナナ(乾)……1300mg
- あんず(乾)……1300mg
- ドライマンゴー……1100mg
- いちじく(乾)……840mg
- なつめ(乾)……810mg
- 干しぶどう……740mg
- プルーン(乾)……730mg
- 干しがき……670mg
- アボカド(生)……590mg
- バナナ(生)……360mg
海藻類
【カリウムを多く含む海藻類ランキング(可食部100g当たりの含有量)】
- 刻み昆布……8200mg
- 板わかめ……7300mg
- 干しひじき(ステンレス釜・鉄釜・乾)……6400mg
- まこんぶ(素干し・乾)……6100mg
- がごめこんぶ(素干し)……5700mg
- 利尻こんぶ(素干し)……5300mg
- 乾燥わかめ(素干し)……5200mg
- 削り昆布……4800mg
- いわのり(素干し)……4500mg
- あおさ(素干し)……3200mg
豆類
【カリウムを多く含む豆類ランキング(可食部100g当たりの含有量)】
- 粒状大豆たんぱく……2400mg
- きなこ(青大豆・脱皮大豆)……2100mg
- いり大豆(黒大豆)……2100mg
- 黄大豆(国産・乾)……1900mg
- べにばないんげん(全粒・乾)……1700mg
- いんげんまめ(全粒・乾)……1400mg
- あずき(全粒・乾)……1300mg
- おから(乾燥)……1300mg
- ひよこ豆(全粒・乾)……1200mg
- そらまめ(全粒・乾)……1100mg
カリウムの効率的な摂取のポイント
カリウムは水溶性のミネラルで、水に溶け出す性質があります。調理方法によっては栄養素が失われてしまうため、摂取時には工夫をするのがおすすめです。
以下は、カリウムの効率的な摂取のポイントです。
- 生のまま食べる
- 電子レンジで加熱する
- 煮汁ごと食べられるように調理する(煮物やスープなど)
- 加工・精白されていない食べ物を選ぶ
カリウムは、水にさらしたり茹でたり煮たりすると溶け出すため、サラダのように生で食べるとしっかり栄養素を摂取できます。カリウムは加熱では減少しないため、電子レンジで加熱するのもおすすめです。
また、煮汁ごと食べられる煮物や、味噌汁などのスープにカリウムが豊富な野菜を入れても効率的に摂取できます。加熱調理すると野菜はかなりカサが減るため、量をたくさん食べられない人にもおすすめの調理法です。
ただし、スープはナトリウムの取り過ぎにつながることも。味が濃くなり過ぎないように薄味を心掛けるといいですよ。
カリウムの取り過ぎを避けるポイント
カリウムの取り過ぎを避けたい場合は、以下のような工夫をしてみましょう。
- 水にさらす
- たくさんのお湯で茹でこぼす(茹でてゆで汁を捨てる)
- 食材の水気をしぼる
- ドライフルーツは避ける
「カリウムの効率的な摂取のポイント」の項目で紹介した内容とは正反対で、水にさらしたり、茹でこぼしたりすることで食材のカリウム含有量を減らすことができます。
なお、カリウムは加熱しても壊れないため、注意しましょう。
カリウム不足・過剰摂取の影響

ここでは、カリウム不足・過剰摂取の影響について解説します。
カリウムが不足した場合
カリウムが不足した場合は脱力感や筋力低下、筋肉の痙攣や麻痺、食欲不振、不整脈が起こることがあります。さまざまな原因によって、血液中のカリウムの濃度が低くなった状態のことを「低カリウム血症」といいます。
なお、カリウムは多くの食品に含まれており、通常の食事をしていればほとんど不足することはありません。
カリウムを過剰摂取した場合
腎機能が正常で、カリウムのサプリメントを飲んでいるなどのケースを除けば、通常の食事でカリウムの過剰摂取になるリスクは低いとされています。
しかし、サプリメント服用や腎機能低下の影響などで血液中のカリウム濃度が高くなると「高カリウム血症」となることがあります。
高カリウム血症では、手先のしびれや麻痺、筋力の低下などが現れます。重篤な場合は命にかかわる不整脈や心停止を起こすこともある症状です。
腎機能が低下していたり、腎臓に障害がある場合は、医師と相談しカリウムの摂取量に注意しましょう。
カリウムは自分に合った適量を摂取することが大切
カリウムは、健康の人の場合は不足や過剰摂取の心配はほとんどありません。しかし、腎機能低下が見られる場合などはカリウムの摂取量を制限されることがあります。
また、サプリメントなどを服用している場合も過剰摂取に注意が必要です。
■もっと知りたい■