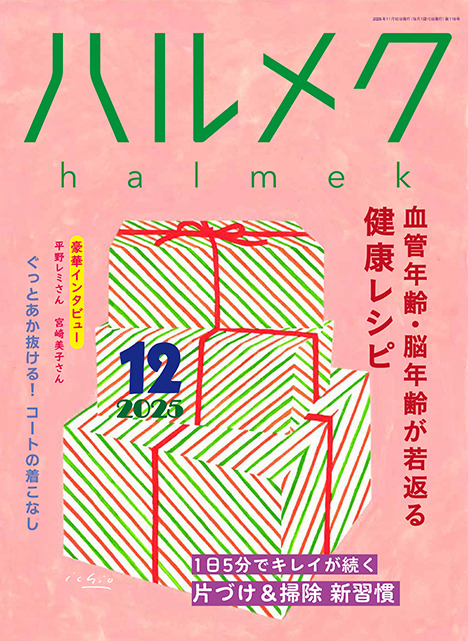更新日:2024年02月29日 公開日:2020年02月29日
素朴な疑問
4年に一度ある「うるう年」とは?

こんにちは! 好奇心も食欲も旺盛な50代主婦、ハルメク子です。
うるう年は、4年に1度、2月が28日ではなく29日まである年ですね。小学校の頃、うるう年の2月29日生まれの子が同級生にいて、「誕生日じゃないのに28日にプレゼントもらえていいなー」なんておバカなことを考えていました(笑)
でも、正式に年齢は増えているのかしら? 今、ワタシと同じ年よね? そもそも、うるう年ってなんなの!? 気になったので調べてみました。
現在ワタシたちが使っている暦は、古代ローマで使われていたとされる暦が元になっています。紀元前8世紀頃の「ロムルス暦」では月は10しかなく、今の1月と2月に当たる月は無かったんだそうです。
「ロムルス暦」の後に使われるようになった「ヌマ暦」では、1月と2月が追加されましたが、政治的・経済的な混乱があり、「ヌマ暦」は正しく定着しませんでした。
ローマの政治家、ユリウス・カエサルが、紀元前45年から「ユリウス暦」を制定し、その後、紀元前1世紀から「太陽暦」が使用され始め、現在に至るまで使用されています。
「太陽暦」では、1年は365日とされています。これは、地球が太陽の周りを1周するのにかかる日数。しかし、実際は365日としてカウントするのに、1年あたり6時間足りません。そのため、6時間×4年=24時間(=1日)として、4年に一度、1年に1日を足すことで暦がズレないように調節しました。そのため、うるう年は4年に一度なんだそうです(へ~、知らなかった!)。
ローマ時代は、1年の終わりは2月と考えられていたので、2月の最終日(2月28日)の次の日に日数を加えることでうるう年を実施していました。なるほど! だから、2月29日なのですね!
ちなみに、うるう年の調整は完璧ではありません。うるう年を設定したことで、実は1年に約11分、時間の増やし過ぎになっているのだそう。その誤差を修正するために「西暦の年号が100で割り切れる、もしくは、400で割り切れない年はうるう年にならない」というルールができました。なんとこれは16世紀にすでに始まっていました! 上記の例外ルールを当てはめると、2100年、2200年、2300年はうるう年になりません。
うるう年というと、何となく東洋の風習のように思っていたけど、実は古代ローマから始まったものなんですね。うーん、奥が深い……。でも、4年に一度しか来ない2月29日が誕生日の人って、年齢をどう計算するんでしょう?
これについては法律で定められています。2月29日生まれの人は、うるう年でない年は、2月28日の24時をもって1歳年齢が増えると決まっています。運転免許証の更新についても誕生日に関する規定があります。免許の有効期限は誕生日から起算して1か月を経過する日と定められています。更新年がうるう年ではない場合、2月29日が誕生日の人は、2月28日生まれの人と同じ扱いにするという規定があるそうです。免許証の有効期限が1日早くなってしまうのは少し気の毒な気もしますが、法律上、止むを得ないのかもしれませんね。
※この記事は2020年2月の記事を再編集して掲載しています。
■人気記事はこちら!
参照:ベネッセ教育情報サイト

イラスト:飛田冬子