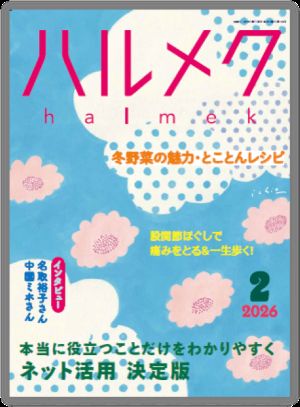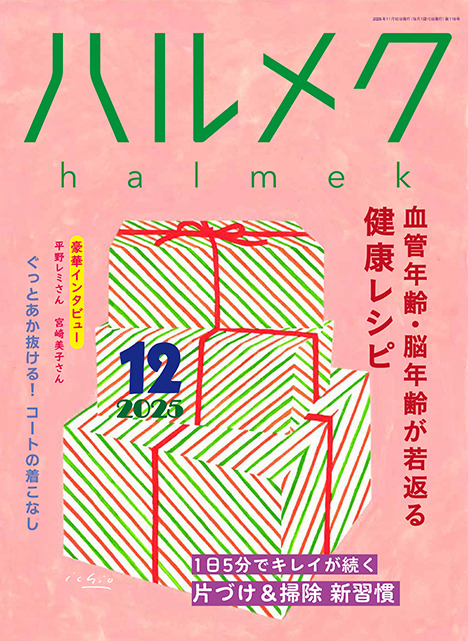更新日:2025年02月24日 公開日:2023年02月06日
素朴な疑問
窓の結露、放置するとどうなる?
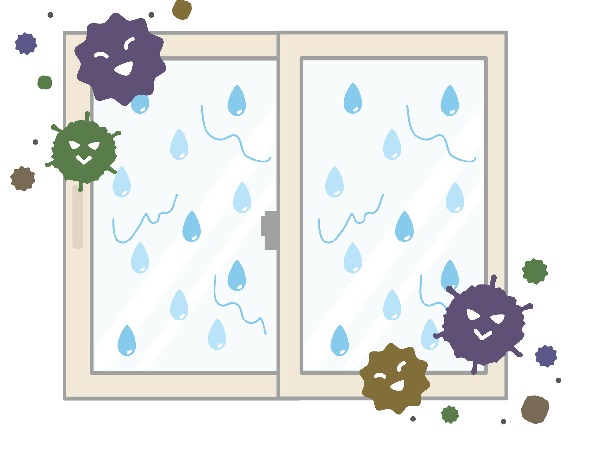
こんにちは! 好奇心も食欲も旺盛な50代主婦、ハルメク子です。
冬になると気になる窓の結露。ワタシは、毎朝せっせとタオルで拭きとっています。そうそう、お友達がリフォームで、結露対策として内窓をつけたんですって! ワタシも「ラクしたい~リフォーム~」と主人に相談してみたら。
「別にそのままにしておけばいいじゃん。いつかは乾くでしょ」って言うんです(怒)。放っておいたらダメなんだから! でもなんでダメなのかしら? そもそもどうして冬だけ結露ができるの? 気になったので調べてみました!
教えて!結露ができる仕組み・原因

結露は、暖かい空気が冷えて飽和水蒸気量を超えてしまうことで発生します。
飽和水蒸気量とは、空気に含まれる水蒸気が限界となる量のことです。空気中に含むことが可能な水蒸気量は決まっていて、これを超えると水蒸気が水滴に変化します。
飽和水蒸気量は、気温が高いと多く、低いと少なくなります。
つまり、暖かい空気が冷やされるとそれに伴って飽和水蒸気量も低下するため、行き場を失った水蒸気が結露となって目に見えるようになるのです。
結露が起こりやすい場所

結露が起こる場所としてすぐに思い浮かぶのは窓ガラスですが、以下のような場所にも起こる可能性があります。
- 窓のサッシ
- 玄関のドア
- 家具の裏側
- クローゼットや押し入れ
- 部屋の隅
- 壁 など
結露が発生しやすいのは、温度の差が生じやすい場所です。
冬はエアコンやヒーター、ストーブなどを使います。温める仕組みなどが異なるため、どの暖房器具を使用したかによって住宅内部の水蒸気量も変化します。
また、暖房器具に加えて加湿器を使用している場合も、温度や湿度の差が生じやすく、窓以外の場所にも結露ができやすくなるので注意が必要です。
結露を放置するとどうなる?

結露をただの水滴だと思って放置してしまうと、以下のような悪影響が出る可能性があります。
【人体への影響】
- シックハウス症候群
- アトピー性皮膚炎
- アレルギー性皮膚炎
- 小児ぜんそく
結露が起こりやすい場所は、湿度が高くカビが発生しやすい環境です。
気温20〜30度で湿度60〜80%になると、カビが発生するとダニも繁殖しやすくなるため、室内環境が悪化して人体に悪影響を及ぼすこともあります。
【建物への影響】
- 家具や壁紙にカビやシミなどが発生
- 木材が腐って家の耐震性や耐久性が低下
- シロアリによる食害の可能性
窓の桟やフローリングなど木材の部分は、結露によって増えた建物内の水分に長時間さらされると腐ってしまい、家を傷める原因になります。
また、湿った木材はシロアリの大好物でもあるため、食害が発生してしまう恐れも。
結露は人体や建物に悪影響を及ぼす危険な存在になりえます。できるだけ発生させないよう、こちらの記事を参考に対策をしてみてくださいね。
※この記事は2023年2月の記事を再編集して掲載しています。
■人気記事はこちら!
- 窓掃除のコツは順番!サッシ・網戸・ガラスをキレイに
- エアコンの掃除頻度は?掃除しないとどうなる?
- 加湿器の白いカルキ汚れはどう掃除すれば取れる?
- 知ってるようで実は知らない?素朴な疑問ランキング ベスト100
参照:窓リフォーム研究所

イラスト:飛田冬子