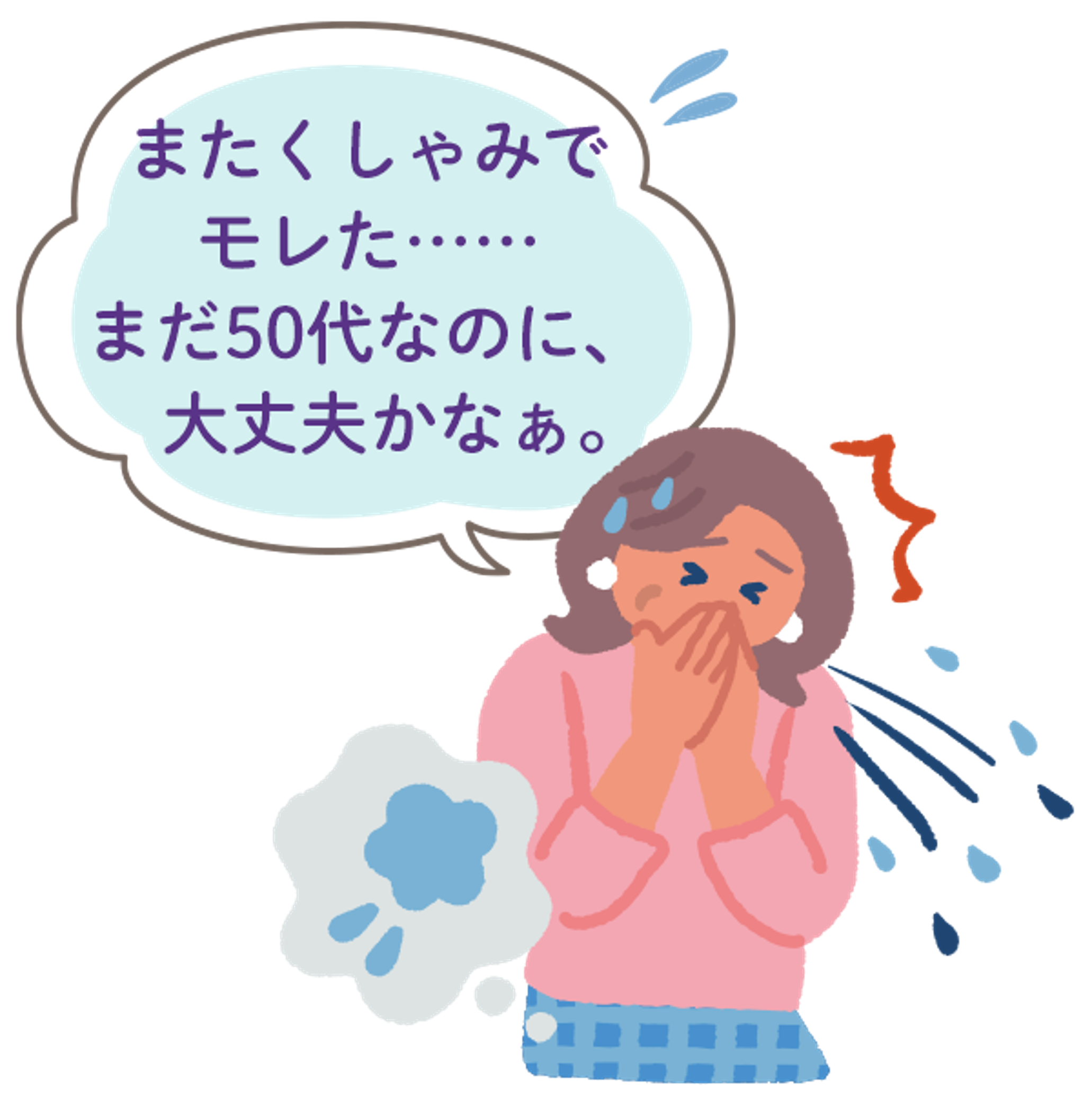
50代で8割以上!?尿モレの悩み
ヒトに話しにくい尿トラブルの話…「私だけ?」とお悩みの方も多いのでは?50代ハルトモさん達にアンケートを実施し、実態を調査しました!
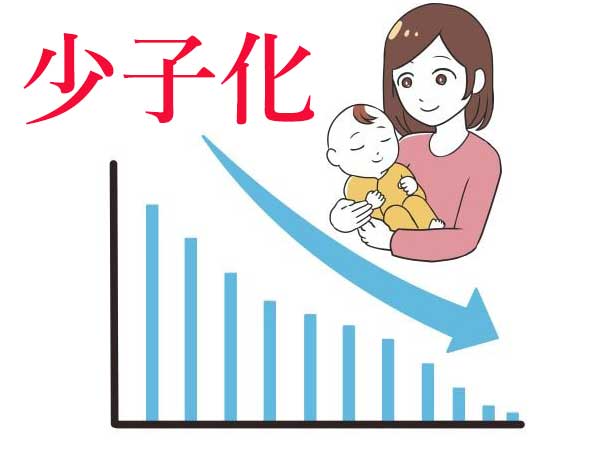
公開日:2021年06月24日
中国は一人っ子政策が廃止されても少子化
「一人っ子政策」が廃止されて5年が経過した中国。2人目の子どもを持つことが認められるようになったにもかかわらず、新たに生まれる子どもの数が激減しています。受験・就職競争が激しさを増し、育児中の親もプレッシャーにさらされているようです。

2021年5月中旬に発表された中国の国勢調査の結果は、中国の国内・国外に衝撃を与えました。統計の信ぴょう性に疑問の声はあるものの、2020年に生まれた赤ちゃんの数は2016年から30%以上減少していたからです。
中国政府は2016年に40年近く続いた「一人っ子政策」を廃止。この5年間は、すべての夫婦が2人目の子どもを持つことを認められていました。

そのような状況にもかかわらず少子化が加速していることから、英米の主要メディアは、中国の出生率の低下を招いた社会背景を以下のように報じています。
結婚にお金もかかり、育児にもお金がかかる。キャリアプラン、ライフプランを設計するにあたり「夫婦1組に子ども1人」という生活様式が多くのカップルにとって自然な形になっていると考えられます。

さて、少子化につながる問題の中でも、国民の高学歴化による教育コストの高騰と競争の激化は、子育て中の親にとって重大なトピックとなっているようです。子どもが安定的な雇用につくためには学歴が必要で、学歴を得るためには幼い頃から勉学に励む必要があるからです。
中国には「望子成龍(子ども学問や仕事で大成することを親が願うこと)」「孟母三遷(教育のために良い環境を選ぶことが大切)」という故事があり、「子どもの成功は親次第」というプレッシャーを親自身が抱えています。
過去に行われた比較調査によれば、中国系の母親は、ヨーロッパ系、アフリカ系の母親と比べて子どもの成績と親の自尊心がより強く結びつく傾向が見られたといいます。子どものためだけでなく、自分たちの体面のためにも子どものやるべきことを親が厳しく選択・管理・強制しているケースもあるようです。

こうした管理型の教育の成功例も多くあるのでしょうが、しばしば欧米メディアでは、スパルタ教育を徹底する「タイガーマザー」、支配的で過保護な「ヘリコプターペアレント」といった言葉とともに中国式の育児を批判する記事も見受けられます。「中国式の支配型育児と欧米式の個性尊重型育児は、どちらが正しいのか?」という議論が巻き起こることもありました。
いずれにせよ、「子どもを育て上げるには、子どもの教育を細かく管理し、多額の教育費を投じることが必要」というプレッシャーによって、「1人の子どもを育てあげること」の負担感が増大しているのかもしれません。

一方で、最近まで「育てられる側」だった若年層の間には、競争や周囲のプレッシャーからの逃避現象がみられるようです。2021年5月に中国のSNSで拡散された、消費しない・恋愛しない・働かない「寝そべり族」の存在は、日本でも大きな注目を集めまています。
幼い頃から常に管理され続けた子どもたちの中には「親の前でだけがんばって勉強をする子がいる」と警鐘を鳴らすコラムもあり、若年層にとっては「がんばった先に得られるもの」が見えにくくなっているというインターネット上の投稿も見られます。

ここまで中国の事情について述べてきましたが、安定した職に就くために大学の学位や専門スキルが必要になり、若年層が安定雇用に就くのが難しくなっている現象は、日本を含めたアジア諸国でも起こっています。
「ロストジェネレーション」「氷河期世代」いう言葉が広く使われるようになっている日本、恋愛・結婚・出産を手放す「三放世代」という言葉が生まれた韓国は、「出生率の低迷」という類似の課題を抱えています。
格差拡大、競争激化、親の過保護化、教育費の高騰、若者の諦観、少子化……。文化的な背景は異なっても、こうしたキーワードは、根底でつながっているようにも思えてきます。
■もっと知りたい■
■参考サイト■
驚きの軽さ&使いやすさ!
1本で7つの効果ハルメクが厳選した選りすぐりの商品