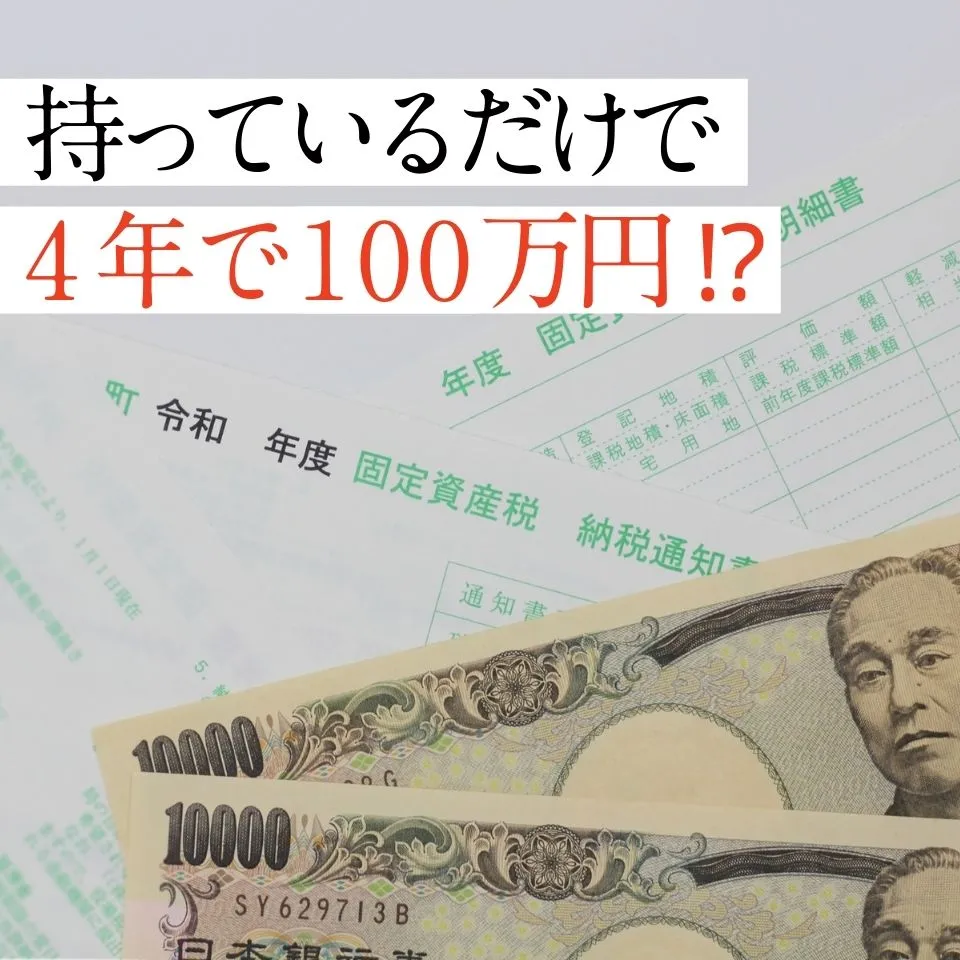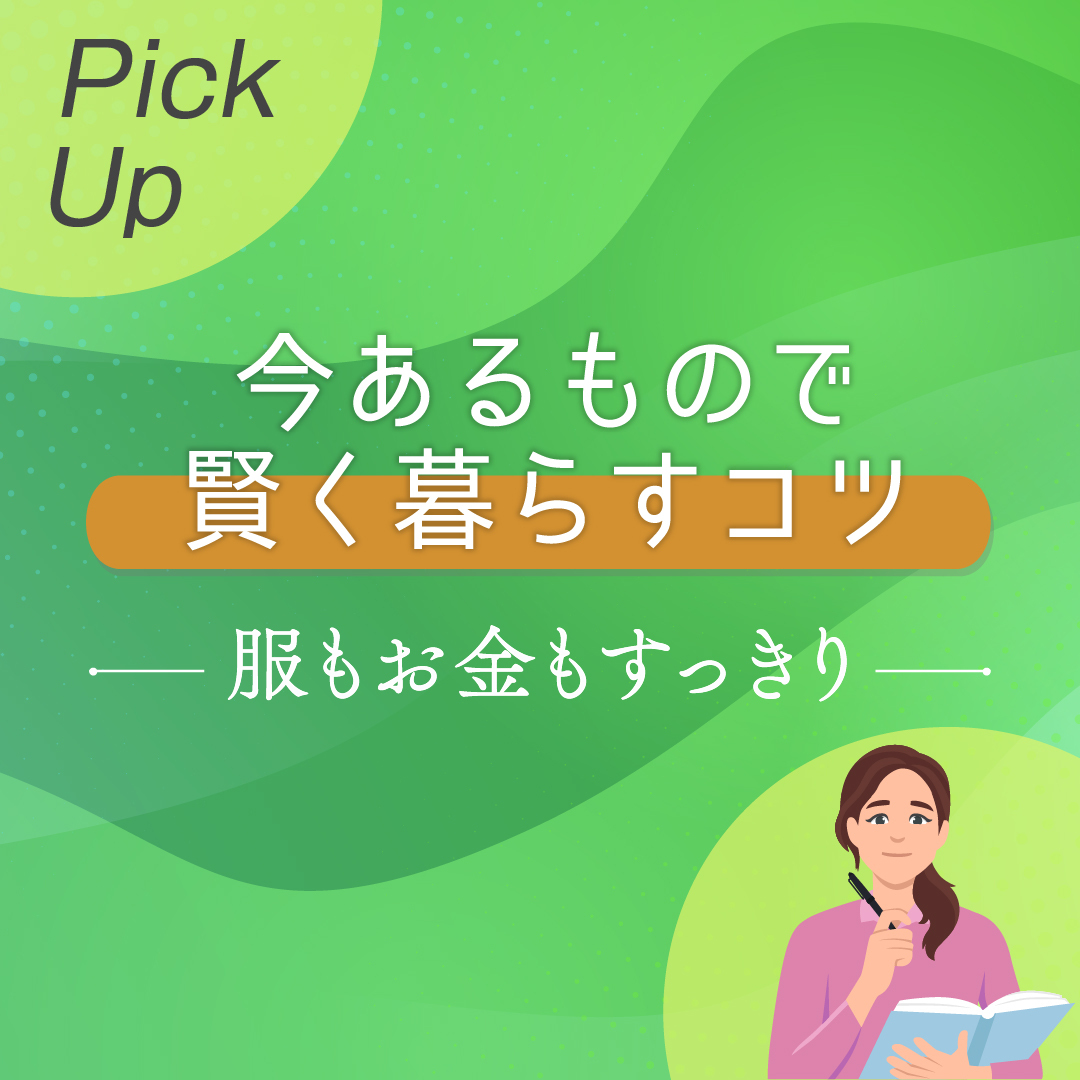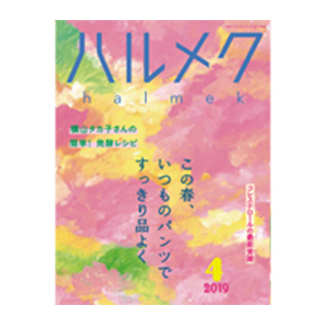菊池和子さんのWEBレッスン#16「寝ながら体操」
うつ伏せの「きくち体操」!体の状態をチェック
うつ伏せの「きくち体操」!体の状態をチェック
公開日:2023年08月05日

菊池和子(きくち・かずこ)さんのプロフィール

1934(昭和9)年生まれ。日本女子体育短期大学卒業。体育教師を経て「きくち体操」を創始し、以来50年以上、毎日の授業、ラジオ、テレビ、講演などを通して指導にあたる。神奈川・東京に直営教室を持つ。『毎日のきくち体操』DVD、『「意識」と「動き」で若く、美しく!きくち体操』、『立ち方を変えるだけで「老いない体」DVD付き』(ともにハルメク刊)など著書多数。
きくち体操とは?
きくち体操は、形、回数を目標にして動かすのではなく、脳で自分の体を感じ取って動かします。「体は、あなたの命そのもの。今日から一緒に動かしましょう」(菊池和子さん)
「動かしたことで少しでもよくなっている」と感じることが大事

以前ご紹介した寝たままできる動きの仰向け編に引き続き「寝たままできる動き」の第2弾。今回はうつぶせ状態です。
私たち人間の目は前側についていますから、どんな行動も自然と前側で背中を丸めて行いがちです。ご飯を食べるのも、文字を書くのもみんな腕を前に出して行うでしょう?ですから、どうしても前かがみの姿勢になってしまうのです。
前かがみの姿勢を放っておくと、うつぶせになったときに肩も背中もきつく感じるのです。ちょっとうつ伏せになってみましょう。

※ケガや病気などで体を痛めている場合は、無理して動かさず医師の指示に従ってください ※うつぶせの動きは、床や畳など体が沈まないところで行いましょう
弱らせているところがないか、体をチェック

まずは、弱らせているところがないか体をチェックします。一緒に動いてくださいね。
うつぶせに寝て、おでこを床につけます。あごやほっぺではありませんよ。そして、手と足の指先を遠くへ伸ばしていきます。簡単そうですが、実はこれだけで大変な動き。初めての人は、つらくて30秒ももたないかもしれません。
そのままあごを引き、肩甲骨を寄せてください。さらに、お腹を引いて腰とお尻に力を入れる。おでこがつけやすくなりましたか?
うつぶせだと自分の体を見ることができません。その分、脳を使って体を動かしましょう。寝たままの動きでも、全身に力がついていきます。
脳で意識するポイント
うつぶせになり、両手両脚を伸ばして、下記の6つのポイントができているか確認しましょう。できていないポイントは、より意識を向けて動かしていきましょう。

- 左右の腕の長さは同じ
→長さが違う人は骨盤がゆがんでいませんか - ひじは伸びている
→伸びていない人は、呼吸が浅くなっていませんか - おでこは床についている
→ついていない人は、頭を支える首の筋肉が弱っていませんか - 腕がつけ根から伸びている
→伸びていない人は、猫背になっていませんか - 内臓は苦しくない
→苦しい人は、ぽっこりお腹になっていませんか - 足首は伸びている
→伸びていない人は、つまずきやすかったりしませんか
いかがでしたか?できなかったポイントを改善するために、次回紹介する3つの動きを今日から少しずつ取り入れて、体を動かしていきましょう。
毎日続ければ、必ず体は応えてくれる
きくち体操には、腕を上に上げるなど、誰もが簡単にできそうな動きが多くあります。「大丈夫、これくらいならできるはず」と、鏡の前で実際にやってみたら(今回ご紹介する動きは鏡の前では難しいかもしれませんが)、思いのほか「腕が上がっていない!」とか「ひじがぜんぜん伸びていない!」と、自分自身にびっくりするかもしれません。
でも、それはチャンスなのです。若いときのように動けていない自分に気が付けたということは、そこからもっとよくしていける、ということなのですから。
ただ、途中で諦めて、やめてしまうのはダメ。どの動きでもいいので、毎日、「昨日よりも体がよくなっている!」と実感できるように動いてください。毎日動けば、必ず、体はよくなっていきます。さあ、今日、今から、さっそく動いてみてください!
※ケガや病気などで体を痛めている場合は、無理して動かさず医師の指示に従ってください
※うつぶせの動きは、床や畳など体が沈まないところで行いましょう
取材・文=岡島文乃、井口桂介(ともにハルメク編集部) 撮影=中西裕人 ヘアメイク=南場千鶴 モデル=太田伸子 イラストレーション=浦恭子
「きくち体操」は、雑誌「ハルメク」で毎月好評連載中!ハルメク365本会員(有料)なら、電子版でお読みいただけます。詳しくは、こちらをご確認ください。