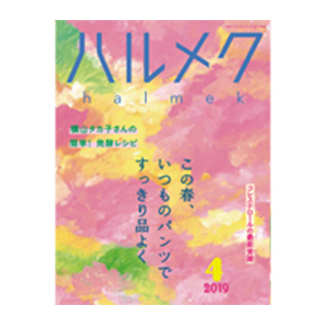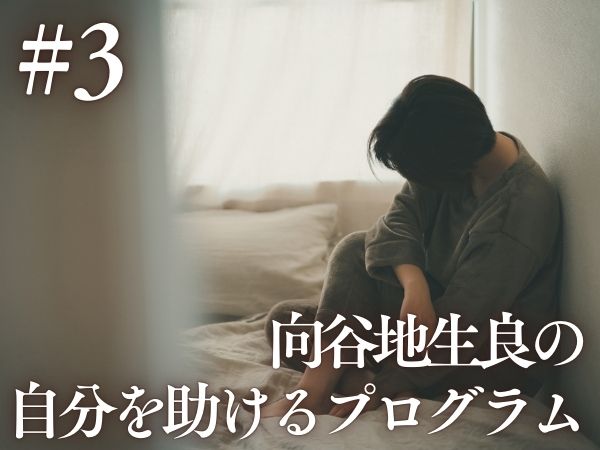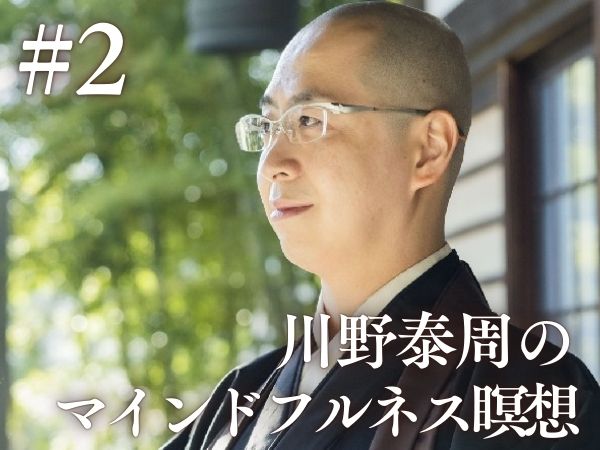向谷地生良さんの自分を助けるプログラム(2)
実践できる!向谷地さんの問題を手放すためのワーク
実践できる!向谷地さんの問題を手放すためのワーク
公開日:2021年08月14日

「弱さの情報公開」のやり方とは?

私は、統合失調症など心の病を抱えている人たちと一緒に行動しています。どうすれば、お互いが生きやすくなるのかを考え、試行錯誤してきました。その答えの一つが、「弱さの情報公開」であることは前回お話ししました。弱さの情報公開とは、自分が抱えている悩みや苦労を表に出すことで、自分だけで抱えていた悩みや苦労を、みんなで抱えていくものです。今回はその方法をお伝えします。
まずは、浦河べてるの家(以下べてる)で行われている弱さの情報公開の場「当事者研究」が大切にしていることを紹介します。
1.本人と「問題」を切り離す
ある「問題(苦労)」があり、それをどうしようかと話し合うとき、なりがちなのが、「本人に問題がある」という考え方です。これを防ぐために人と問題を切り離します。
例えば、月末になると必ず「金欠」になってしまう人がいたとします。そのとき、「金欠を繰り返すAさん」ではなく、「金欠を防ぎたいが、防げない苦労を抱えているAさん」と、「金欠」と「本人」を切り離すのです。
2.自分の病名「自己病名」を考える
抱えている苦労に自分で「名前」(自己病名、苦労ネーム)をつけます。べてるでは「月末金欠バクハツタイプ」や「人間アレルギー症候群」など、さまざまな病名や苦労ネームがあります。ユーモア感覚で名前をつけることで、自分の問題と距離を取ることができます。
また、この場を「当事者研究」と名付けているのは、問題を「自分の心の問題」ではなく「研究テーマ」と捉えることで、あたかも実験を行うように、取り組むことができ...