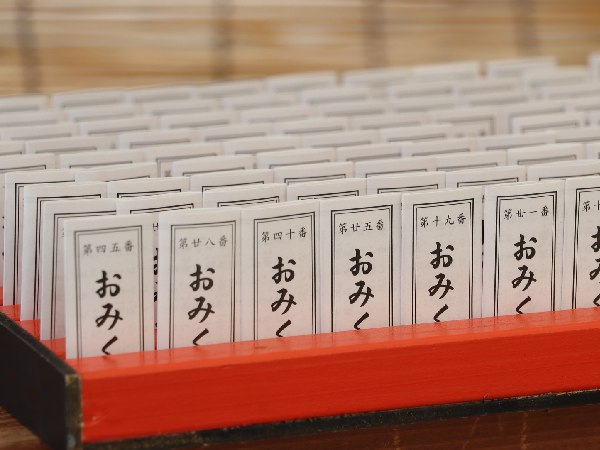更新日:2023年12月31日 公開日:2020年12月27日
素朴な疑問
古いお札やお守りはどうやって処分したらいいの?

こんにちは! 好奇心も食欲も旺盛な50代主婦、ハルメク子です。
年末の大掃除をしていたら、机や引き出しからお守りやお札がたくさん出てきました。子どもの合格祈願、懐かしい~。ご利益のおかげか無事に合格したので、もう必要なくなったんだけど……。
これらのお守りやお札はどう処分したらいいのかしら? そもそも、お守りやお札って期限はあるの? 長く持ち続けてしまったけど、大丈夫だったのでしょうか……。気になったので、調べてみます!
お札やお守りに期限はあるの?
初詣などでいただいたお札やお守りは、持ち主の身代わりとして災厄を受けたり、下界の気にさらされて、徐々に効果が薄くなるといわれています。そのため、最大限のご利益を受けるには、1年間を期限として新しいものに替えるとよいそうです。
縁結び、安産祈願、合格祈願など、特定の目的に限定されたお札やお守りも、基本的に1年間が目安です。ただし、1年以内に願いがかなったり、目的が達成された場合は、その時点でお礼も兼ねて、お寺や神社へお返し(返納)しましょう。
1年というのはあくまでも目安であって、1年以上たつとご利益や効果がなくなるわけではありません。また、お札やお守りを扱っているお寺や神社によっても考え方が変わるようなので、気になる場合は、お札やお守りをいただいたお寺や神社に確認するとよいでしょう。
七五三でいただくお札やお守りは期限がないといわれています。こちらは、一生大切に手元に置いても構わないのだそうです。
お札やお守りの返納の仕方
古いお札やお守りは、お寺や神社に返納するのが安心です。いつでも受け付けてくれるそうですが、初詣のタイミングで返納して、その日に新しいお札やお守りをいただくとよいでしょう。
返納するのは、境内の「納付所」「お焚き上げ」などと書かれた場所です。わからなければ、寺務所や社務所に聞くと教えてくれます。そうそう! さい銭箱に入れるのはマナー違反なので注意してください。
購入したお寺や神社にお返しするのが一番ですが、遠方の場合は郵送するか、他のお寺や神社にお願いしましょう。
郵送で返納する方法
- 宛名は、お寺や神社に「御中」を付ける。
- お札やお守りを封筒に入れて、「お札(またはお守り)在中」と記す。
- お寺なら「焼納希望」、神社なら「お焚き上げ希望」と記載して、今まで守っていただいたお礼の言葉などを添える。
返納料は不要なことが多いですが、納めたい場合は現金書留にします。金額は、お札やお守りと同額程度でいいようです。
他のお寺や神社に返納する方法
- お寺でいただいたものは、同じ宗派のお寺へ、神社でいただいたものは、同じ神様を祭っている神社へ返納する。
- 「神社」「宮」「天神」などと書かれていたら神社へ。
- 「寺」「院」「山」などと書かれていたらお寺へ。
返納以外の処分方法
返納以外には、「どんど焼き」に持参して、門松やしめ飾り、書き初めなどと一緒に、お焚き上げしてもらう方法があります。どんど焼きは、地域によって「道祖神祭」「左義長(さぎちょう)」「鬼火たき」などとも呼ばれています。
どんど焼きは、一般的に1月15日前後、第2日曜か月曜日に行われることが多く、当日に行けなくても、事前にお納め所を設置していることがあるそうです。
自分で処分する場合は、お札やお守りを白い半紙に包み、粗塩をかけて清めます。お清めをしたら、燃やすか、そのままゴミとして処分しても大丈夫です。
古いお札やお守りを処分するときは、感謝の気持ちを込めましょうね。
※この記事は2020年12月の記事を再編集して掲載しています。
■人気記事はこちら!
参照:cotonara

イラスト:飛田冬子