作家・寮美千子さんと考える「音に出す言葉の力」#3
少年刑務所で気付いた「人間の本質は優しさ」
少年刑務所で気付いた「人間の本質は優しさ」
更新日:2021年05月14日
公開日:2021年03月20日

直球な詩を作った少年は悪い魔法がとけた
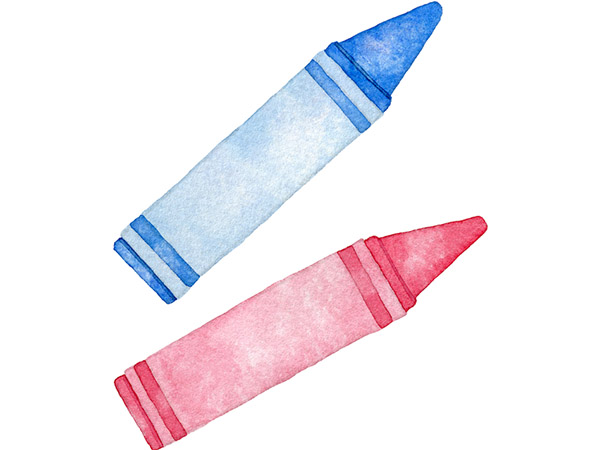
刑務所の少年たちが書いてくれた詩の中に、こんな一編がありました。
「すきな色」
ぼくのすきな色は
青色です
つぎにすきな色は
赤色です
確かに私は少年たちに、「書きたいことが見つからなかったら、好きな色について書いてきてください」と言いました。とはいえ、こんな直球の詩が来るとは思わず、のけぞりそうになりました。コメントに困っていたら、受講生がみんな手を挙げるのです。
...
























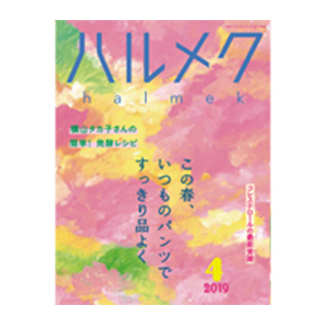



















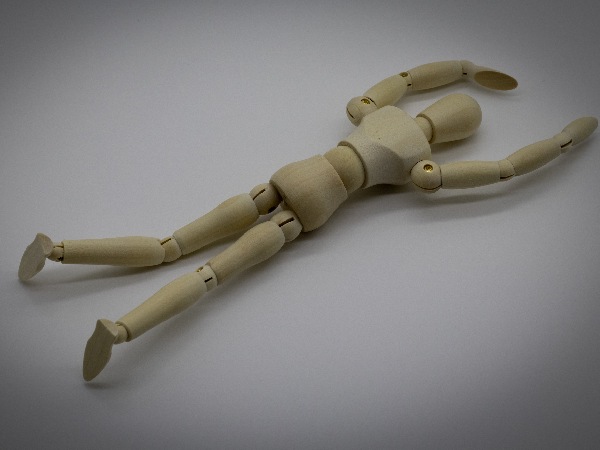











これからも、何度も読み返したいインタビューです。心が洗われました。