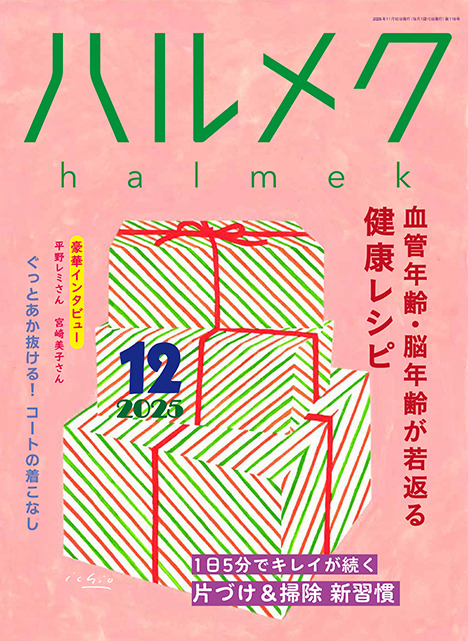公開日:2019年07月23日
素朴な疑問
浴衣を着るときのマナーってあるの?

ここ数年、浴衣に半衿(はんえり)や足袋(たび)という夏着物風の浴衣が流行っているようです。浴衣に白足袋と下駄なんてすてきですね! 何より、年とともに、首元やうなじ、裸足を見せることに躊躇していたワタシにはうれしい流行です。
夏着物風の浴衣なら、ビアガーデンや屋台以外の飲食店にも入りやすそうですが、知人のお宅にお邪魔する場合は? レストランは? そういえば、浴衣は元々寝間着だったという説も聞いたことがあります。浴衣を着るときのマナーが心配になってきたので、調べてみました。
浴衣のルーツは平安時代。貴族が蒸し風呂で着用していた「湯帷子(ゆかたびら)」という麻の着物だったと考えられています。室町時代になると、汗を吸いやすい木綿の湯帷子が登場し、寝間着や普段着としても着られるようになったそう。
平安時代は貴族文化だった蒸し風呂と湯帷子ですが、室町時代末期から江戸時代にかけて、庶民の間に「湯屋」と呼ばれる文化が広まり、一般の人々にも湯帷子が普及しました。最初、湯屋は蒸し風呂でしたが、徐々に裸でお湯に浸かるスタイルに進化したようです。
江戸時代末期になると、湯帷子は名前を変えて浴衣と呼ばれ、普段着としても着用されたといいます。お祭りやお花見といったイベントに、おそろいの浴衣で出かけるなんて流行もあったそうです。(楽しそう!)
明治時代には、浴衣はすっかり夏の普段着として定着します。その証拠に、当時の文学作品からは、気軽な外出着を表す意味として「浴衣がけ」「湯帷子がけ」という言い回しが多く見受けられます。
例えば、夏目漱石の『行人』に「夕飯前に浴衣がけで、岡田と二人岡の上を散歩した」という一節があります。
また、芥川龍之介の『出帆』には「やはり浴衣がけの背の高い男が、バトンを持っているような手つきで、 拍子 ( ひょうし ) をとっているのが見える」とあります。
浴衣は湯上り着や寝間着がルーツですが、江戸時代からは普段着に格上げされ、明治時代は外出着としても着用されていたのですから、少なくとも「外に着て行くのは恥ずかしい」なんてことはないみたいでひと安心!
とはいえ、よそ様のお宅に裸足でお邪魔するのは、さすがに気が引けます。茶道を習っている友人に確認したら、浴衣に限らず和服に慣れた人は、「常に足袋の替えを携帯するのがマナー」なのですって(履き物を脱ぐときに履き替えるんだとか)。
また、フォーマルなドレスコードが設けられたレストランや料亭は、Tシャツやハーフパンツ、サンダルが禁止されています。したがって、ごく普通の浴衣姿も歓迎されないでしょう。綿コーマの浴衣はTシャツ、素足に下駄はサンダルと同様ですし、半衿なしはカジュアルさのアピールだからです。
浴衣でかしこまった場所へ出るなら、絹紅梅(きぬこうばい)やちぢみなどの高級浴衣に半衿、白足袋に草履といった夏着物風のアレンジが必要なのですね。ちなみに、夏着物と浴衣の違いは、「生地に透け感があるのが夏着物、ないのが浴衣」です。
■人気記事はこちら!
- 食事の際、箸袋を箸置きにするのはマナー違反?
- せきやくしゃみのエチケットとは?
- 年賀状はいつまでに返せばいいの?
- 初詣はいつまでに行くのが正しいの?
- 親として、祖父母としてふさわしい、結婚式の服装とは
- 知ってるようで実は知らない?素朴な疑問ランキング ベスト100
『着物の辞典』
大久保信子(著)池田書店,2011年

イラスト:飛田冬子