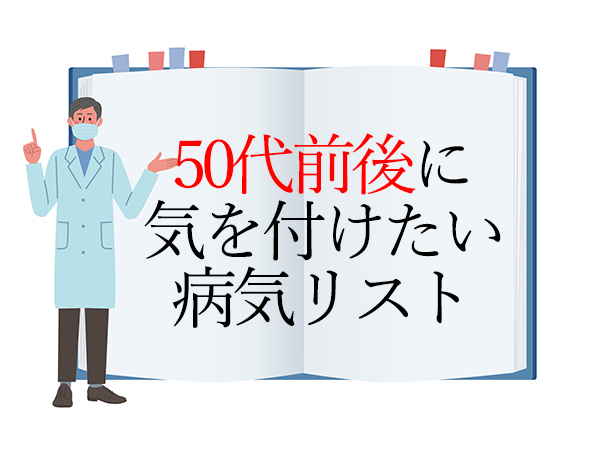更新日:2025年06月23日 公開日:2022年07月18日
素朴な疑問
カレーの食中毒に要注意!症状や予防法は?

こんにちは!好奇心旺盛な50代主婦、ハルメク子です。
我が家ではカレーが大人気。たくさん作れば翌日も楽しめるし、アレンジも効く便利な料理ですよね。特に「2日目のカレー」は味が馴染んでさらにおいしい!でも最近、「一晩寝かせたカレーに食中毒のリスクがある」と聞きました。
そこで今回は、カレーで起こる食中毒の原因やリスク、そして安全に楽しむための保存方法を調べてみました。
「2日目のカレー」での食中毒の原因は熱に強いウェルシュ菌
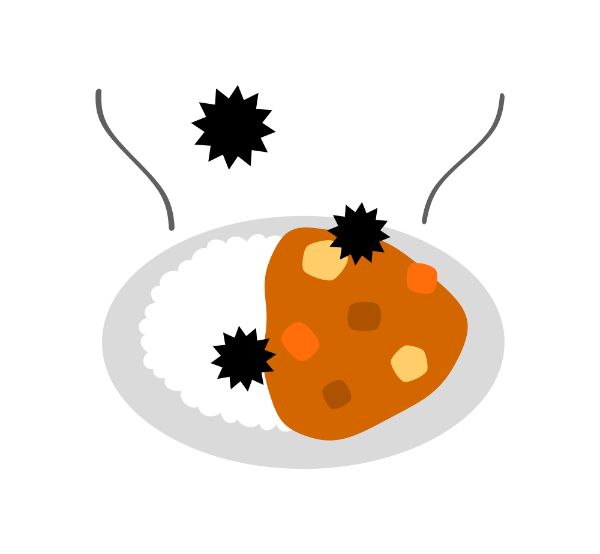
カレーで食中毒が起こる原因は、熱に強い「ウェルシュ菌」と呼ばれる細菌です。菌は熱に弱いといわれているため「煮込めば大丈夫」と思う人もいるかもしれませんが、ウェルシュ菌は煮込んでも生き残る厄介者!。この菌は以下のような特性を持っています。
食品に付着する
肉、魚介類、野菜などカレーの材料に自然に含まれています。
熱に耐える
煮込んでも死滅せず、100℃で数時間加熱しても生き残る「芽胞(がほう)」という殻を作ります。
繁殖の至適温度帯
12~50℃で増殖しやすく、特に43~45℃で活発に増えます。夏場の料理では、この温度帯が維持されやすいため、リスクが高まります。
ウェルシュ菌は「カレー」だけでなく「シチュー」や「肉じゃが」など、たくさん作る煮込み料理でも発生する可能性があります。保存方法に注意が必要ですね。
ウェルシュ菌食中毒の症状とは?
ウェルシュ菌による食中毒は「給食病」とも呼ばれることもあります。これは、大量調理された食品で特に発生しやすいことから呼ばれる名称です。
主な症状は次のとおりです
潜伏期間
6~18時間(平均10時間)。
主な症状
腹痛、下痢。嘔吐や発熱はほとんど見られません。
治りやすい特徴
発症から1~2日で回復することが多い。
注意が必要なのは、子どもや高齢者、基礎疾患がある人です。これらの方は重症化するリスクがあるため、しっかり予防対策を講じることが大切です。
カレーの食中毒を防ぐための2つの重要ポイント

「作り置き」や「翌日も食べる」場合には、次の対策をすることで食中毒リスクを減らせます。
1. 適切な保存方法
カレーを清潔な保存容器に小分けし、急速に冷やして保存します。冷蔵または冷凍保存で菌の繁殖を抑えることができます。
2. 十分な再加熱
保存したカレーを食べる際は、全体がぐつぐつ煮立つまでしっかり加熱します。かき混ぜながら再加熱することで、全ての部分に均一に熱を行き渡らせるのがポイントです。
また、カレーは腐敗していても見た目や臭いの変化がわかりにくい場合があります。保存状況に少しでも不安がある場合は食べずに処分しましょう。
カレーは便利でおいしい料理ですが、適切な保存方法と十分な再加熱が欠かせません。みなさんも「2日目のカレー」を安全に楽しむために、ぜひこれらのポイントを実践してくださいね!
■人気記事はこちら!
参照:近畿農政局

イラスト:飛田冬子