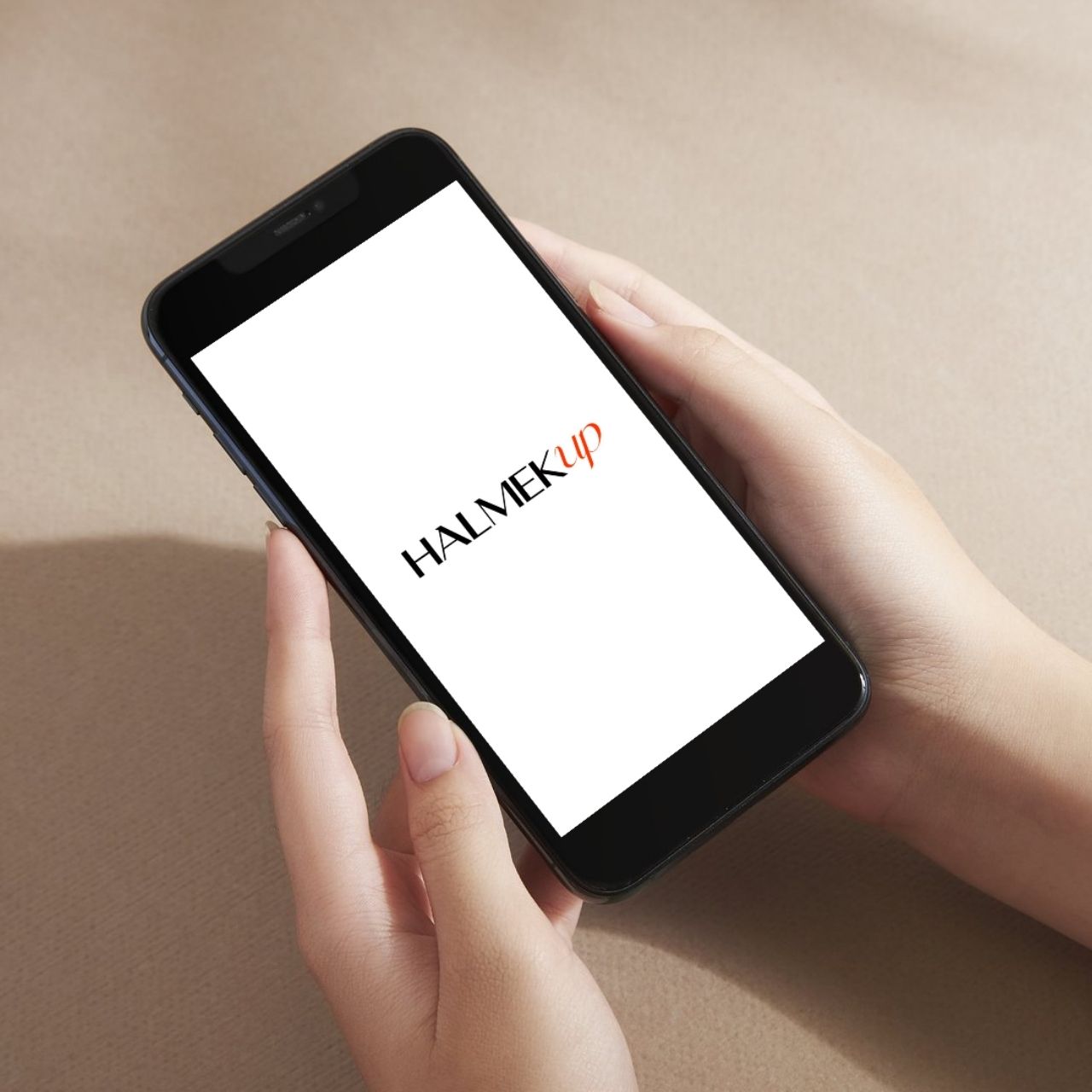母の数年ぶりの買い物は、100円均一のポーチだった
2018.08.01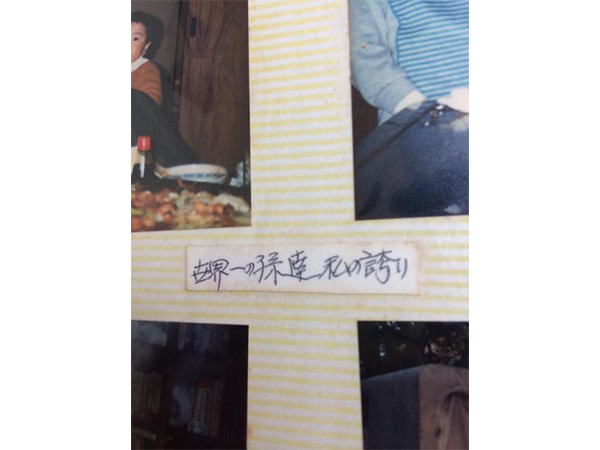
2018年09月02日
追伸。―おかんへ―
悲しい病気、認知症。3人の母と娘の名前を、何度でも
面と向かってはなかなか言えない、でも確かに胸の中にある母への感謝や、母への謝罪――。「追伸。」と題し、母を中心とした家族とのエピソードをつづります。明確なはずなのに、なぜかいつも難しい、親子や家族の関係。共感してもらえればなによりです。
悲しい病気
ぼくに向かって、祖母はしゃべり続ける。
「しげちゃん、この前あそこに行ったばってん……」「お父さん、お父さん、ずっとこげん言いよったよね……」。
施設の食堂から、祖母の自室へと移動する。祖母の腕をとり、亀よりものろい歩みで、ゆっくりと。祖母からは少し、つんとすえるような臭いがする。
短いはずの廊下が、延々と続く1本道かのように感じた。その道のうえで、不意にあふれ出す幼かったころの記憶。
祖母はまるまると太っていた。頬を寄せられると、お化粧の匂いがした。博覧強記で、いろんな四字熟語やことわざを教えてくれた。「ケンちゃん、あんたは賢かねぇ!」と、スポーツ刈りの頭をジャリジャリと撫でてくれた。散髪は毎度、祖母の手によって行なわれた。
「重症・軽症」、「重傷・軽傷」。病気やケガは、「重い・軽い」の形容詞で表されることが多い。だが、祖母の患う病気を表すのには「重い」というより、「悲しい」の方がふさわしいのかもしれない。
「しげちゃんあんたの……」、ぼくに向かって、祖母はしゃべり続ける。
おばあちゃん、おれは「しげちゃん」じゃなかよ、「ケンちゃん」よ……。
認知症は、悲しい。
祖母の笑顔
妻と娘を連れて、祖母を見舞った。2015年の話だ。幼子を連れての飛行機はなかなか勇気がいるもので、娘が産まれ1歳をすぎて、ようやく福岡へ帰省できた。
「もう、私の名前も呼んでくれん」。毎日のように施設に通う母はそう言っていた。夏がくるたびに「この夏は乗り切れんかもしれん」とも。
何度か訪れたことがあった祖母の自室。窓が広く、光がよく入る。
「じゃあ、○○さん、ゆっくりね」と、施設の方が祖母の名前を呼び、肩をたたき、部屋を出ていった。部屋で唯一の笑顔が、なくなった。
ソファに座り、聞き取れない声で、それでもなにかをしゃべり続ける祖母。その顔は終始しかめ面だ。祖母の肩に、母が腕を回す。
「ほらおばあちゃん。ケンちゃんが帰ってきたよ!おばあちゃん、ケンちゃんのこと大好きやったろう?」
「○○さん(妻の名前)も来てくれたとよ」
「おばあちゃん、久しぶり。ケンスケよ」。祖母はごにょごにょとなにかをつぶやくだけ。しかめ面で。
「最近はコミュニケーションもとれんくてね……」と、母は宙に向かって苦笑いを向けていた。
そのとき、抱っこ紐から解放された娘がよたよたと部屋を歩き始めた。
思いついたように、母は「おばあちゃん、あなたのひ孫よ。会いにきてくれたとよ!」と祖母の肩に力を入れる。持参の布のボールで遊びだす娘に、「ひーおばあちゃんに、どうぞ、して」と妻が促す。おぼつかない足取りで、おむつで膨らんだおしりを振りながら、娘が祖母の前に立つ。
「どうじょ」
祖母は、にっこりと微笑んだ。
奇跡の全貌
「あれはもう奇跡やったとよ」
のちのちも母は繰り返しそのときの話をする。
「だって食事のときも、スプーンを向けてもなんにも反応せんかったとよ。でもあとのきは……」。電話をするたびにしつこく言われるので、今は少し鬱陶しくも感じるが、でもやはり、あれは奇跡だったのだと思う。
娘が差し出したボールを、祖母は受け取った。受け取って微笑んで、“会話”をしたのだ。
「ありがとう」
「あんた、かわいかね」
「どこから来たとね?」
妻が娘のそばにしゃがんだ。
「よこはま、だよね」、と妻がゆっくりと言う。
「あんたどこの子ね」
「おなまえは?」と妻が娘に聞く。「○○ちゃん」、と片言で、自分の名前を「ちゃん付け」にして娘が返す。
また祖母が、にっこりと笑った。母が祖母の肩から腕を離し、そのまま両手で顔をおおった。
「ちょーだい!」と、唐突に娘が手を差し出した。
そしてぷくぷくの小さな両手に、しわだらけの手からボールがのせられた。
母はソファを離れ、部屋の隅でぼくらに背を向け、声を上げて泣いた。
祖母。母。妻。ぼくは遠巻きに、その3人の母を眺めていた。
奇跡の光景を、眺めていた。
消えない記憶
祖母の自室の壁にはところ狭しと写真が飾られ、何冊もアルバムが置かれている。ぼくはそれらを見て回りながら考える。
悲しい病気、認知症。
若年性、という言葉もある。いつかぼくも、そうなってしまう可能性がないとは言い切れない。本当かどうかは知らないが、新しいことは覚えられない、でも昔の記憶は忘れない、そんな話を聞いたことがある。
ならば、絶対に忘れたくない。ここにいる、3人の母と、娘のことは。
唇が動きを覚えてしまうくらいに、今のうちから何度も何度も、呼んでおきたい。
「おばあちゃん」「お母さん」「妻の名前」。3人の母とそして、「娘の名前」を。
アルバムに貼られた、祖母のメモに目がとまる。視界がにじむ。
『世界一の孫達 私の誇り』
祖母の頭の中ではきっと、小学生のころのぼくが走り回っているはずだ。そう思った。「忘れるわけがなかろうもん」、得意げにツンと顔を上げてみせる、祖母の笑顔が浮かぶようだった。
ぼくのことを今「おまえ」と吐き捨てるあなたも、ぼくにとっては「誇り」です。
ここからは余談です。
祖母が唯一呼べる名前がある。それが、「しげちゃん」。すでに亡くなっている祖父の名前ではなく、母を含め親戚一同、その正体は誰も知らない。身内の中では「初恋の男性なのではないか」という話で落ち着いている。
当時は戦時下、それでも。
少女は甘酸っぱさを胸に抱き、ドキドキとキラキラを繰り返していたのかなぁ。