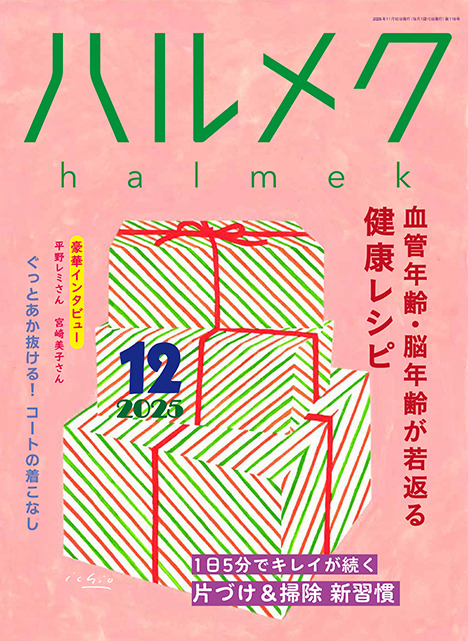公開日:2021年05月26日
素朴な疑問
食べ合わせが悪い食べ物の組み合わせって?

こんにちは! 好奇心も食欲も旺盛な50代主婦、ハルメク子です。
よく「AとBは食べ合わせがよくない」などと言いますよね。食べ合わせの良し悪しって本当にあるのかしら? この機会に調べてみようっと。
食べ合わせとは?
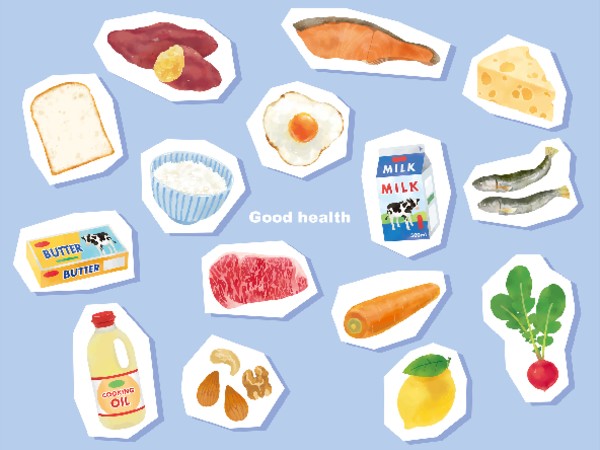
「食べ合わせ」とは、2つ以上の食材を組み合わせて食べること。それによって、栄養素が体内に吸収されるのを促進させる「相乗効果」だけでなく、体内に吸収されるのを阻害してしまう「相殺効果」もあります。
では、どんな食べ合わせがよくないのか、見ていきましょう。
カルシウムと食べ合わせが悪いもの
骨や歯の健康、神経や筋肉のバランスに欠かせないカルシウム。「牛乳やチーズ、ヨーグルトなどの乳製品や小魚、大豆製品、野菜」などに多く含まれています。
これらカルシウムを含むものと食べ合わせが悪いものが、リンを含んでいる「インスタント食品やスナック菓子」です。食品添加物に含まれるリンは、1:1の割合以上で摂取すると、カルシウムが排出されてしまいます。
他にも「カフェイン」も同様にカルシウムの排泄を促す効果があり、食べ合わせには注意が必要です。
さらに、「玄米や枝豆」に含まれるフィチン酸や、「ホウレン草」に含まれるシュウ酸によってカルシウムが体内へ吸収されにくいという特徴もあります。
鉄分と食べ合わせが悪いもの
鉄分を多く含む「赤身肉やレバー、魚介類、大豆製品、穀物、海藻類」などは、「コーヒーや紅茶、玄米、大豆、イモ類」などとは食べ合わせが悪いと言われています。
コーヒーや紅茶に含まれるタンニンや、玄米に含まれるフィチン酸、食物繊維などは、鉄分の吸収を妨げる効果があります。食事中はほうじ茶や麦茶の方がいいですね!
ここでもう少し、鉄分を深堀りしてみたいと思います。貧血予防に大切な鉄分には、動物性食品に含まれるヘム鉄と、植物性食品に含まれる非ヘム鉄があります。ヘム鉄は、非ヘム鉄に比べて数倍吸収されやすいため、効率的に鉄分を摂取できます。
鉄分を効率的に摂取できる調理法があります。それは、鉄製の鍋やフライパンで調理すること。調理中に鉄が溶けて手軽に鉄が摂取できます。とくに、酸味のあるお酢やケチャップを使った料理がおすすめです。
ビタミンB1と食べ合わせが悪いもの
体内で糖質を分解してエネルギーに変える役割を担うビタミンB1は、「肉類、魚類」に加え、「米ぬかや小麦胚芽などの穀類」などに多く含まれています。
これらと相性の悪い食材は、「エビやカニ、貝類、淡水魚、ワラビやゼンマイなどの山菜類」です。その原因は、これらの食材に含まれているチアミナーゼ(アノイリナーゼ)がビタミンB1を分解してしまうからです。
しかし、チアミナーゼは、熱に弱い特性があるため、加熱調理によってその悪影響を低減させることができます。
ビタミンB1の不足は、疲労感や倦怠感など、神経に悪影響を及ぼします。さらに思考力の低下やイライラの原因になることもあるので、効率よく摂取しましょう。
食べ合わせがよくないというのは、「本来取れるはずの栄養素が取りにくくなってしまう」という意味があったのですね。気になる栄養素や、しっかり取りたい栄養素から順番に相乗効果、相殺効果を学びつつ、日々の食生活で実践していけるといいですね。
■人気記事はこちら!
- ルビーカカオってどんな味?
- 食事ダイエットのやり方!糖質制限や断食も要注意
- そうめんと冷や麦の違いは?
- アイス、ジェラート、シャーベットの違いは何?
- 元コンビニ店長がオススメ!絶対ハマる定番スイーツ5
- 知ってるようで実は知らない?素朴な疑問ランキング ベスト100
参照:食べ合わせ大百科

イラスト:飛田冬子