公開日:2019年07月30日
素朴な疑問
血管年齢の意味や測定の仕組みとは?若返りの方法は?
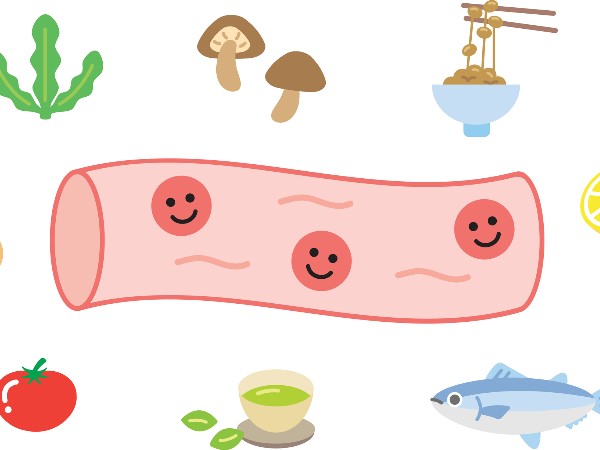
こんにちは! 好奇心も食欲も旺盛な50代主婦、ハルメク子です。
最近よく「血管年齢」という言葉を耳にします。血管に年齢があるの? 実年齢より上だったり下だったりすると、どうなるのかしら? 年齢という言葉に敏感なお年頃ですから、さっそく調べてみました!
血管年齢とは?
血管年齢というのは、全身に張り巡らされている血管の弾力性を調べて、血管の老化度を測ろうというもの。血管の弾力性が年相応かどうかをチェックして、血管の健康度を年齢に見立てて割り出します。具体的な検査方法として、血管の硬さ(動脈硬化の進み具合)を目安に、センサーに指先を入れて、脈拍の波形から血管年齢を測る検査などがあります。なぜ血管年齢が重要かといえば、実は、血管はワタシたちの健康を左右する存在だからなんです。
お肌や内臓と同じように、全身の血管も年齢とともに老化しています。若い血管は弾力があってしなやかに動き、酸素と栄養をスムーズに送り出して全身に行き渡らせます。けれど加齢とともに血管が弾力を失って硬くなると、酸欠や栄養不足に陥って内臓や筋肉が衰えたり、動脈硬化が進行します。その結果、脳卒中や心筋梗塞、狭心症など、さまざまな健康リスクを招いてしまうんだそう(怖い!)。
アメリカの内科医ウイリアム・オスラー博士が「人は血管とともに老いる」という言葉を残しています。血管をいかに若々しく保つかが健康の秘訣、という考えから近年は「血管年齢」が意識されるようになったのですね。
ある調査で30代の男女300人の血管年齢を調べたところ、血管年齢が実年齢を上回っていた人は全体の4割以上に上ったそうです。ワタシたちの血管は、思っていた以上に老化が進んでいるのかも!? お肌や髪の健康は常に意識していたけれど、血管の健康には無頓着だったわ。これからは血管のアンチエイジングも意識しなくっちゃ!
血管年齢を下げるには運動と食事の見直しを
それでは、血管を若々しく保つためにできることってなんでしょう? ポイントは「内皮細胞の活性化」。血管は3層構造になっていて、最も内側にあって血液に直接触れているのが内皮細胞です。血管を硬くする原因になる外敵から身を守り、血液をサラサラに保つ働きをする内皮細胞を元気にすることが重要ということなんですね。
キーワードは「食生活」と「適度な運動」。血管の老化は偏った食事や高血圧、肥満、ストレスなど、生活習慣病に起因するものが多いんだとか。塩分を減らして魚や大豆を多く取り、食事は腹八分目をキープしたいものです。息が弾む程度の運動を週3回程度行うように心掛けましょう。
血管年齢を下げる食生活
まず食事で取るべき成分を紹介します。血管をしなやかにする横綱級の食材は魚。EPA(イコサペンタエン酸)は血液や血管壁の細胞に入り、血栓や炎症を抑える働きをする脂肪酸の一種です。接種目安は1日1g以上。体内でEPAに変化するオメガ3系の植物油、例えばアマニ油、エゴマ油、シソ油など(1食小さじ1~2杯)でもいいでしょう。ただし熱に弱いため、ドレッシングやソースにしたり、みそ汁に加えたりして使います。調理油はEPAの働きを妨げないオリーブオイルや米油がおすすめ。
次に食物繊維。水溶性食物繊維を多く含むオクラなどねばねばした野菜、海藻類を主食の前に食べれば、血糖値の急上昇を抑えられます。また、色が濃い野菜には抗酸化物質のフィトケミカルが豊富。葉野菜は両手に1杯、火を通したものは片手に1杯を目安に取りましょう。
そして血管をしなやかにする成分にも注目。血圧を下げる効果のあるLTP(ゴーダチーズ、ブルーチーズなど)、血糖値の上昇を抑えるケルセチン(玉ネギ、キヌサヤ、アスパラガスなど)、酢酸(酢など)、クロロゲン酸(1日3~4杯までのコーヒー、ゴボウなど)もおすすめです。
血管年齢を下げる運動
ここでは、テレビを見ながらなど、日常生活に取り入れやすく毎日続けやすい体操を紹介します。動脈を広げ、血管内に血栓などができるのを防ぐ血管若返り物質である一酸化窒素というものがあるのですが、「血流を一度止めて、再開させるとき」、多くの筋肉で作られる「ブラジキニン」という物質によって分泌がアップします。「締めて、緩める」運動が、ポイントです。
「ボートこぎ体操」
1.姿勢をまっすぐにして、お腹に力を入れて立ちます。斜め上を見上げて、腕を目の高さに上げます。手は軽く握ります。
2.ボートをこぐように腕を後ろに引き、肩甲骨の間に深い「谷間」が寄るように意識したら、肩を下向きに回しながら最初の1の姿勢に戻ります。10回を目安に行い、逆回しもします。
「クラゲ体操」
1.足を軽く開き、体を安定させます。腕はリラックスさせたまま、ひざは曲げずにゆっくりとかかとを上げ、つま先で立ちます。
2.次にかかとを下ろしてゆっくりとつま先を上げ、かかと立ちします。きつい人は台などに手をついて行ってもOKです。
いきなり生活を変えるのではなく、無理なく長く続けることが大切!毎日続けて、めざせ血管年齢30代!
■人気記事はこちら!
参照:雑誌「ハルメク」2016年12月号~2017年2月号「血管年齢を若返らせよう!血管美人プロジェクト」

イラスト:飛田冬子
















































