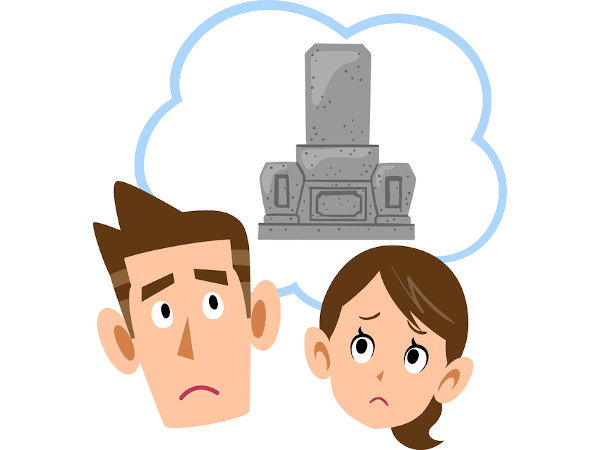公開日:2023年05月23日
素朴な疑問
忌中(四十九日まで)にやってはいけないことって?

こんにちは! 好奇心も食欲も旺盛な50代主婦、ハルメク子です。
仲の良いお友達同士でディナーの予定があったのだけれど、そのうちの1人から「今回は参加できなくなりました」とメッセージが送られてきました。
他の友達によると、「忌中で参加できないと言っていた」とのこと。忌中は、親族が亡くなったあとの期間だということはわかるのだけれど、具体的にしてはいけないことがあるのかしら? 自分の身にもいつ起こるかわからないので、調べてみました。
忌中とは?

故人が亡くなってから、四十九日法要が行われるまでの期間を「忌中(きちゅう)」と言います。
仏教では、死者の魂が次の行き先(六道)のどこに行くか決まるのが、49日目の判決の日とされているため、その期間は故人が極楽浄土に行けるようにと追善供養を行います。
さらに、古くから「死」は穢れ(けがれ)と考えられていて、穢れを他人に移さないように家にこもるというのが一般的な忌中の考え方です。
学校や会社の「忌引き(きびき)」とは、もともとは忌中に家にこもるための休みでしたが、今では身内に不幸があった際、葬儀に参列するための休暇として使われています。
忌中にやってはいけないことって?

忌中は以下のような行事は控えるのが一般的です。
- お正月のお祝い
- 結婚式の出席
- 新年会や宴会、パーティーの参加
- 神社への参拝
- 飲み会
お正月や結婚式といったお祝いの席は、大切な人が亡くなって悲しんでいる期間とも言える忌中は避けましょう。また、神社は穢れを持ち込まぬよう敷地内に入ったり、鳥居をくぐったりすることを禁止しています。
それ以外にも、忌中に外出することそのものが、外出先に穢れを拡散させてしまうという理由から、外出は控えるべきとされています。
近年そういった考え方を重視していない人も増えてきているため、柔軟に対応して問題ないこともありますが、一緒に出掛ける人や参加する人の考え方とは異なるケースもあるため、予定はキャンセルするのが無難でしょう。
四十九日の法要までにすべきことは?

忌中は、初七日や四十九日の法要を手配したり、毎日お水やお線香をあげたりして、故人に思いを馳せます。
また、忌中が開けたら香典返しを送る必要があるため、準備をしておくと良いでしょう。
■人気記事はこちら!
参照:おうち整理士

イラスト:飛田冬子