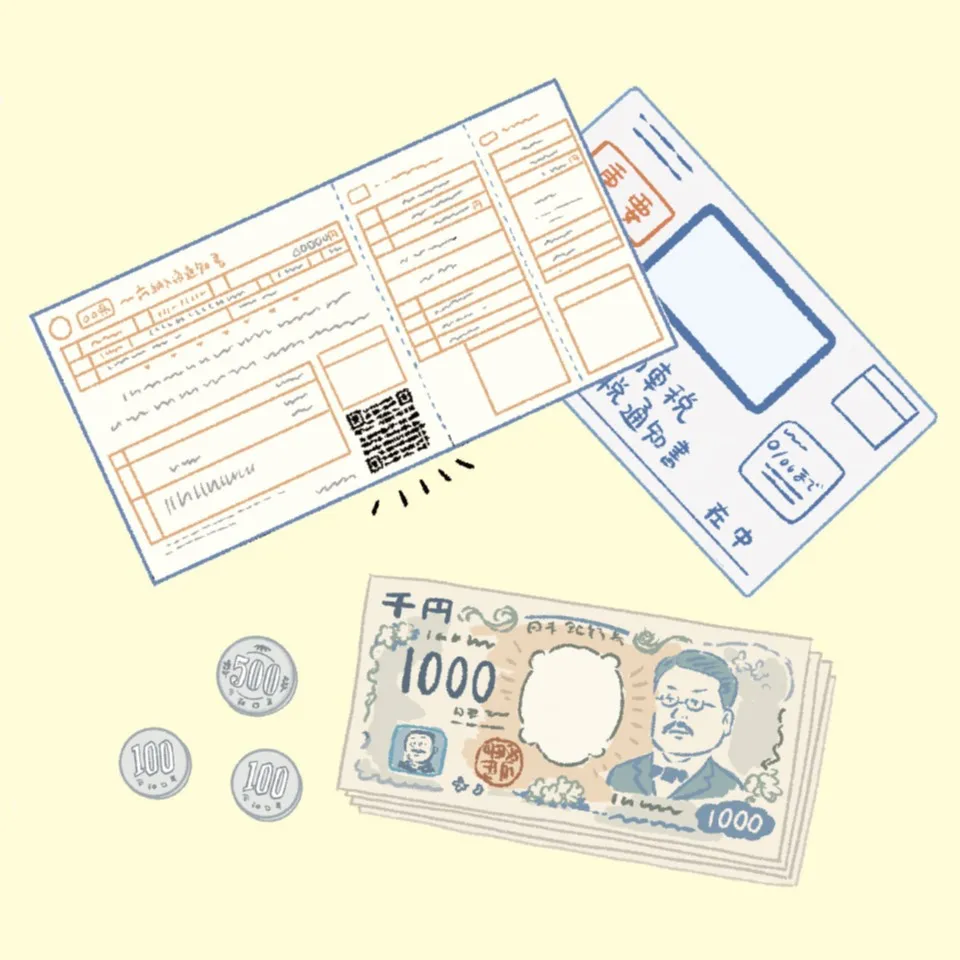
税公金をスマホで払うと…
税公金の支払いはスマホからが圧倒的にラク&お得!「ゆうちょ銀行」では抽選で毎月1万名様に1,000円が当たるキャンペーン実施中!

公開日:2024年01月30日
孤独死を減らしたい…看取り士が考える幸せな逝き方
「最期は自宅で」と願いながらも叶わない人々が絶えない中、その人が望む場所で、安心して尊厳のある死を迎えられるように支援をしている「看取り士」の柴田久美子さん。さまざまな経験を経て今、死の意味やその迎え方、そして生きる喜びについて伺いました。

岡山県のとある住宅地の一角。編集部が取材のために訪れると、「愛というのは……」と柴田久美子さんの声が聞こえてきました。「看取り士」を目指す人たちのための講座の最中でした。
年間140万人以上が亡くなる社会で、柴田さんは人々の最期を見送る「看取り士」として活動し、その育成に取り組んでいます。「これまで育ててきた看取り士は約2200人。私自身も300人ほどの方を看取ってきました」

看取り士の活動は多岐にわたります。
まず余命宣告をされた患者の自宅を訪問し、その人の望む最期について思いをじっくりと聞きます。そして亡くなる直前は24時間態勢で寄り添い、患者に家族がいる場合は動揺する家族を支えながら、家族が患者にゆっくり感謝の言葉を伝え、触れ合えるようにサポートします。
家族がいない場合は看取り士が患者の手を握り、肩を抱きます。病院や施設ではなく自宅で最期を迎えたいという人が多いことから、自宅で過ごせる環境をつくるためにケアマネジャーや看護師らと連絡を取り合い、介護保険サービスだけでは在宅で過ごすには足りない場合は「エンゼルチーム」というボランティアチームが自宅を訪問し、身辺のサポートを行います。
他にも医師との相談や葬儀社との打ち合わせ、お通夜や葬儀の対応などあまりの活動内容の広さに驚きますが、柴田さんは「私たちが目指すのは尊厳のある旅立ち。誰だって亡くなるときくらいわがままを聞いてもらっていいはずです」と話します。
「人生の99%が不幸でも最期の1%が幸せなら、その人の人生は幸せなものになると私は思うんです」
介護保険サービスや終末期医療(ターミナルケア)などの知識を活用し、その人が望む形で旅立てるようにサポートする柴田さん。しかしそのキャリアの始まりは、意外なところにありました。
「私は専門学校を卒業すると、当時日本にできたばかりのマクドナルドに入社しました。最初は秘書課にいたのですが、現場に出たくて店舗に異動。店長にもなり、無我夢中で働きました」。
急速に成長していた当時のマクドナルドでの仕事はとにかく「スピード」と「効率」重視。あまりの忙しさに、店舗用の冷凍庫の上で寝ていたこともあるといいます。
キャリアウーマンとして充実した日々を過ごしていた柴田さん。しかしその忙しさは徐々に心身の健康を脅かします。
「結婚して子どももいたのですが、家庭を顧みる余裕がなく、やがてストレスからお酒に走るようになりました。そしてある日、衝動的に大量の睡眠薬を飲んでしまったのです」
救急搬送されて一命をとりとめたものの、夫には「もう一緒にはいられない」と告げられ、家族と離れることになります。そこで選んだのが介護の世界でした。

「私は父を小学6年生のときにがんで亡くしたのですが、父が最期に私の手を握り、『くんちゃん(久美子さんの愛称)、ありがとう』と言って旅立っていきました。そのとき、父の手がだんだん冷たくなっていくのですが、私は心が温かくなっていくような感覚があったのです。
死は単なる悲しいことではなく、遺された人にエネルギーを渡す“命のバトン”だと感じました。離婚により家族を失った私は人の死に寄り添いたいと思い、介護の道に入りました」
40歳を前にヘルパーの仕事を始めた柴田さん。ただし、介護の世界で壁にぶつかります。
「『最期まで一緒にいるからね』と約束していた施設の利用者の方も、容態が悪くなれば緊急搬送され、病院で亡くなってしまうのです。誰もいない病室でチューブにつながれたまま息を引き取る人もいました」
病院のない離島ならばその人が望む形で見送れるだろうと島根県の離島に移住するものの、老人ホームもない島では自力での生活ができなくなると本人の希望とは別に本土の病院に搬送されるケースが絶えず、「島での最期を望んでいた100歳のおばあちゃんが『私は悪いことをしていないのに』と悲しげに言い、運ばれていったことが忘れられません」と振り返ります。
目の前の一人を救えないことに衝撃を受けた柴田さんは、看取りの家を設立します。島に移住して4年目のことでした。


「看取りの家ではヘルパーとボランティアがそこで暮らす人が自然死を迎えられるように最期までサポートしました」
臨終の場で死にゆく人が安心して旅立てるようにと腕に抱き、看取り士を名乗るようになったのもこの頃からです。
看取り士というと「なにそれ?」と言われることも多かったそうですが、応援してくれる人が次第に増えて60歳のときに日本看取り士会を設立。現在は後進の育成に励んでいます。
「実は看取り士になりたいという人の約6割は看護師です。医療の世界では死を敗北とする風潮があり、家族も患者に対して胃ろうなどの措置を行うか医師から判断を求められると『何もしないのはよくないのでは?』と迷ってしまうケースが多い。そうした現状を目の当たりにし、“よりよい死”とは何かと悩み、患者や家族に寄り添いたいと思うのでしょう」

柴田さんは講演などを行った際、気になることがあると言います。「講演の後に話しかけると、私の連絡先を書いた名刺をお守り代わりに欲しいという方がよくいるのです。今は元気だけど何かあったら誰かに相談したい、見守ってほしいという人が多いのでしょう」
一人暮らしのシニア世代が増える中、看取り士会ではおひとり様を見守るサービスや、買い物や病院に同行する「暮らしサポートサービス」、そして看取りや納骨まで行うサービスも行っています。
「この、納骨まで行うサービスは33万円です。ボランティアチームによる生活の支援やお通夜や葬儀の対応まで行うので正直なところまったく利益にはならないのですが」と笑い、こう話します。「こうやって利用してくれる人はいいんです。心配なのは、相談もせず誰にもつながらないまま亡くなってしまう人。寂しいですし、その後を片付ける人のためにも、やっぱり孤立死は止めたいんです」
さまざまな死を見届けてきた柴田さん。死は怖くはないのでしょうか、と尋ねると「怖いと思っているうちは、まだ死なないですよ。旅立つ人を見送っていると、穏やかに亡くなる人がとても多いです」と答えた上で、「とはいえ」と続けます。
「この数十年で、日本の社会は死を遠ざけてきました。かつては家で死ぬのが当たり前で誰しも死が身近にありましたが、今では子どもたちが親戚の亡くなる瞬間を見ることもほとんどないでしょう?
死を怖いと感じるのは、そのように死を遠ざけ、いつかどこからかやってくるものだと思っているからではないでしょうか。
死は生と表裏一体です。私たちは既に死とともにあり、たまたま今生きているにすぎません。死と、偶然手にしている“今”を感じることは、生きる幸せを感じることにもつながります。だから私は毎朝目覚めるたびに幸せだと感じるんです。ああ、今日も生きているって」

現在では人が亡くなると、遺体をすぐにドライアイスで冷やすケースがほとんどですが、柴田さんはなるべく遺体を冷やすのを待ってもらうと言います。
「先日、12歳の少年が新型コロナの緊急搬送中に亡くなり、亡くなった後に家族から看取り士への依頼をいただいたのですが、葬儀社さんと相談してドライアイスをいったん抜きました。
ちょうど中学校に入学するタイミングだったので、着るはずだった制服を身に着け、2人の祖母が彼を抱きしめるのを待ってから、お通夜は死後5日目に行いました。亡くなった方に触れながらゆっくりとお別れをすることは、遺された家族の悲しみを癒やすのにも有効です」
この春からは、ペットの最期を支えるためのサービスを始めると話す柴田さん。「ペットも大切な家族。その死を一緒に支えたいんです」と話します。旅立つ命や遺された家族に寄り添う柴田さんの挑戦はまだまだ続きます。

39歳
介護施設で働く
福岡県の介護施設のヘルパーに。充実した時間を過ごす一方、本人が望まない形で亡くなるケースも多く、誰もが理想の最期を叶えられるようにしたいと考える。
50歳
離島に移住し、看取りの家を設立
島根県隠岐郡の知夫里島に移住。島の看取りの実情を知り、看取りの家を設立。「看取り士」を名乗るように。
60歳
本土で看取り士会を設立
2012年に鳥取県で設立し、14年に岡山県に拠点を移す。関東や関西などにも支部が広がり、研修を通じて看取り士の育成に励んでいる。
1952(昭和27)年、島根県生まれ。日本マクドナルド入社後、レストラン経営を経て介護施設のヘルパーに。ケアマネジャーや介護福祉士の資格を取得。98年島根県の離島に渡り、2002年に看取りの家を設立。12年に日本看取り士会を、20年に株式会社日本看取り士会を設立。
株式会社日本看取り士会
取材・文=大矢詠美(ハルメク編集部) 撮影=キッチンミノル
※この記事は雑誌「ハルメク」2023年6月号を再編集、掲載しています。
驚きの軽さ&使いやすさ!
1本で7つの効果ハルメクが厳選した選りすぐりの商品